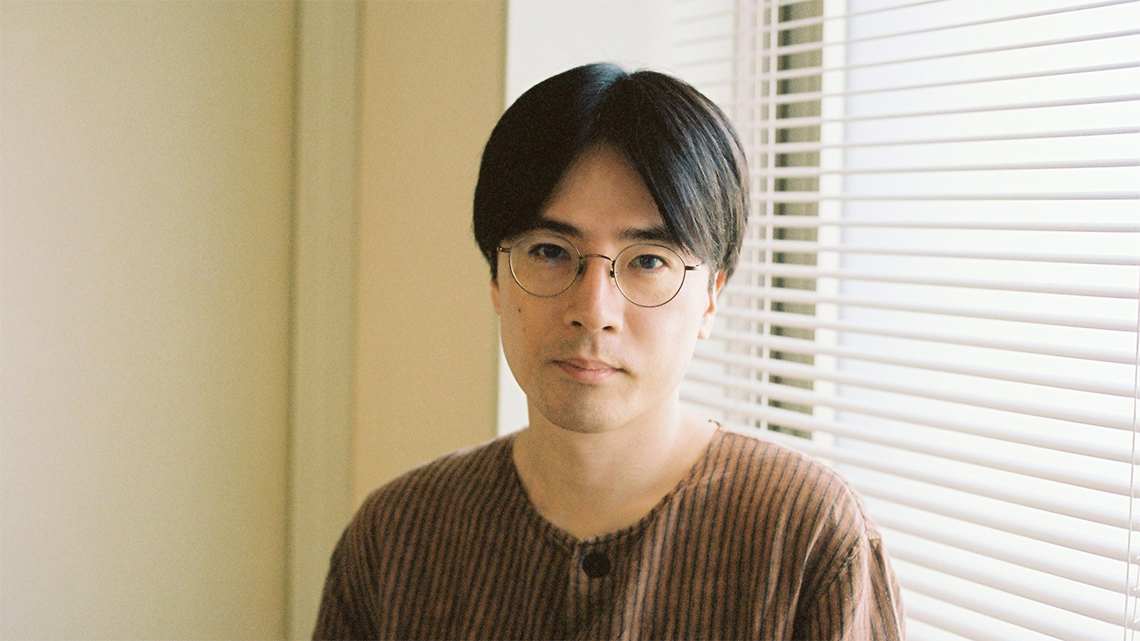
演劇から映画へと表現の場を広げながら、独自の美学を貫く玉田真也監督への期待が、近年の日本映画界で静かに高まっている。松田正隆の戯曲「夏の砂の上」を原作とした待望の映画化作品『夏の砂の上』(7/4公開)は、愛が欠落した人々の再生を描きつつ、どこか懐かしさも感じさせる独特の質感を持った作品だ。オダギリジョー、髙石あかり、松たか子、満島ひかり、という豪華キャストが織りなす人間関係を軸に、傷として残る記憶と時間の止まった人生を描いている。
本作は玉田監督が2022年に自身の演劇ユニット「玉田企画」で舞台化した同作品の映画版であり、演劇では描ききれなかった「余白の部分」を映像で表現することに挑戦した意欲作。長崎という土地の坂と階段を効果的に活用した画面構成や、光と闇が共存する独特の映像美は、人間描写をさらに深く掘り下げる。社会を前進させる情報発信を行う「あしたメディア by BIGLOBE」では、本作の公開にあわせ、玉田真也監督へのインタビューを、映画解説者・中井圭との対談形式でお届けする。

雨が一滴も降らない、からからに乾いた夏の⻑崎。幼い息子を亡くした喪失感から妻・恵子と別居中の小浦治。働いていた造船所が潰れても新しい職を探さず、ふらふらしている治の前に、妹の阿佐子が、娘の優子を連れて訪ねてくる。阿佐子は、1 人で博多の男の元へ行くためしばらく優子を預かってくれという。こうして突然、治と姪の優子との同居生活がはじまることに......。
-----------------------------------------------------
7月4日(金)全国公開
出演:オダギリジョー 髙石あかり 松たか子 森山直太朗 高橋文哉 篠原ゆき子 / 満島ひかり/ 光石研
監督・脚本:玉田真也 原作:松田正隆(戯曲「夏の砂の上」) 音楽:原 摩利彦
製作・プロデューサー:甲斐真樹 共同プロデューサー:オダギリジョー
製作:映画『夏の砂の上』製作委員会
製作幹事・制作プロダクション:スタイルジャム
配給:アスミック・エース
(C) 2025映画『夏の砂の上』製作委員会
-----------------------------------------------------

詩的な言葉を持った戯曲との出会い
中井: ぼくは、2022年に玉田さんの演劇ユニット「玉田企画」で上演された舞台「夏の砂の上」(作:松田正隆)を観て、素晴らしかったという記憶があります。玉田さんは、その戯曲を今度は映画にしていますが、この戯曲の何がそこまで玉田さんを惹きつけているのでしょうか。
玉田: この戯曲を最初に読んだのは、随分前です。大学で演劇を始めて戯曲を読みあさっていた時期に出会って、めちゃめちゃ面白いなと思いました。とくにセリフが面白くて、突如として飛躍する瞬間があるんです。日常的なやり取りが描かれているのに、詩のような強度のあるセリフが急に出てきて、それがひとつの世界に収まっている。
この詩みたいなセリフがなぜ必要なのかというと、社会化されていない部分が出るから。言い換えると、他者と共有できない部分ですね。共感ができるということは、その時点でもう社会化されています。渦巻いている感情みたいなものが吹き出すときは、日常の言葉じゃ足りないんだと気づきました。それは詩のような強度を持つ言葉になるんですよね。
自分もそこまでいけるフィクションを作りたいと思ったし、この戯曲を手本にし続けています。
演劇から映画へ――余白を描く挑戦
中井: 舞台で上演された「夏の砂の上」は、演劇として既に完成しているという印象でした。それを改めて映画にしたのは、なぜですか。
玉田: 映像化しようと思い始めたのは、演劇制作のタイミングからですね。当時、稽古前に演出プランを考え、稽古時にその演出プランを崩しながら再構築していきました。その過程で、この戯曲が持っている独特の余白にぶつかりました。
この戯曲には場面ごとに時間の経過があって、たとえば2週間が一気に経過するような形で時間が流れていく。そして演劇上で実際に描いているのは、経過した先の数十分間という短い時間なんです。だから、その部分だけを観ても理解できないことが多い。その上、この人物はどうしてこんなこと言うんだろう、というセリフが多い戯曲で、それは劇中に描かれていない「余白の2週間」を想像しないことには絶対に分からない。俳優も役作りするときに、どういう状態でこの言葉を言ったのだろうと想像しないことには、演じることができません。
だから、演出家も俳優も、稽古中に余白を想像する作業を行い、お互いに共有していました。そして、想像するほどに、描かれていない余白部分がどんどん面白くなっていきました。その余白の部分を実際に描くことによって作品に強度をもたらすんじゃないか、と演劇の稽古をしながら思っていたので、これを映画化しようと考えました。

演劇と映画の違い――カメラがもたらすもの
中井: 玉田さんは演劇と映画の両方に取り組んでいますが、両者は芸術の形式として違いがあります。キャリアを積んできて、差異をどう考えていますか。
玉田: 両方を作り始めてから、正直なところ、あまり違いが分からないなと思っていました。でも、最近、演劇と映画の演出について改めて考えることがあったんです。
この前、ジャ・ジャンクーの『新世紀ロマンティクス』(2024年)を観ました。その中では、労働者のおじさんたちが弁当を食べているシーンや、おばあちゃんたちが作業しながら歌い出すシーンをカメラが撮っています。彼らが俳優なのか、本当にその場にいた人を撮っているのかは分からないけど、そこにカメラがあるということ自体、不自然なのに、撮られている様が自然に見えたんです。そこで、監督がその撮られている被写体の人たちとちゃんと関係性を作っているか、こういう場所にカメラを置いたら撮られていることを意識しなくていいといった環境づくりが重要だと気づきました。そういった関係や環境を作ることで、欲しい空気を引き出していくのが映画の演出なのかもしれないと思いましたね。
中井: 演劇の場合、俳優たちの目の前にはお客さんがいて、その上でどう演じるかを意識している。しかし、映画の場合は、作り方によってカメラを意識させないことが可能なんじゃないか、あるいは俳優ときちんと繋がれているかどうかが重要になってくる、ということですね。
玉田: 映画は、カメラがあるのが本当に大きいです。演劇の場合、極端に言えば、俳優の身体とセリフがあれば成立するんですよ。強度の高いセリフと精度の高い身体があって、場を支配するエネルギーが出ていれば、2時間観ることができる。仮にストーリーがなかったとしても観れるんです。それが演劇の面白さだと思います。
でも、映画は観客との間にカメラが入る。カメラが入るということは、監督がいま見たいものは何か、ということへの意識が強くなければいけない。その意識によって映画になっている、という感じがします。
中井: 観客の立場から言うと、演劇の場合、自分の目は自分でコントロールできるので、自分が見たい場所にフォーカスが合う。だけど、映画は監督が見せようとしているものを見せられる。だから画面に対する意識は、映画の方が作家性がより強く出ていくのではないかと思っています。

愛の欠落と再生、そして傷として残る記憶
中井: 映画『夏の砂の上』を拝見し、これは愛が欠落している人たちの再生の物語だと思いました。ただ、そうであっても、彼らの状況が大きく好転しているとも思えないところに、ままならない人生を感じています。玉田さんはこの映画をどう捉えていたのでしょうか。
玉田: どれだけ不条理なものに巻き込まれ、人生なんて虚無だと思っていても、どこかで他者とのつながりを強烈に求めてしまうのが人間です。作品のあらすじを読むと寂しい話だと思いますが、物語の中の人たちには大きなエネルギーがあります。彼らから様々な感情が湧き出ていますが、それらは目の前の人と繋がりたいという気持ちが引き出しているものです。虚無感は人生につきものだと思いますが、個人にフォーカスしたときの他者と繋がりたいという湿度も同時にある作品だと捉えています。
中井: 動かない時間に取り残される人の寂しさが、この映画にありました。
玉田: この物語は、ある雨の日の出来事が原因で時間が止まってしまった、オダギリジョーさん演じる小浦治の話だというのがベースにありました。だから、この映画の冒頭に入れた雨のシーンは、過去の雨なんです。あの時間で治の人生はストップしていて、止まった時間をどう動かしていくかを映画で描こうと考えていました。
中井: そして、この映画は傷の物語でもありますね。
玉田: そうですね。この物語を通して、傷がたくさん出てきます。人や家の柱、長崎という街が抱えた深い傷があります。傷が残るのは、忘れないことだと思っています。たとえば、家の柱に数字を書いた傷がありますが、その家には、(背丈を測ったであろう)その子の存在が残り続けている。玄関を見上げたときに雨漏りのしみがあるのは、きっとあの大雨の日についたものなんじゃないか、というように痕跡は残っていきます。この映画で治のもとから様々な人々が去っていくけど、何かが残っていく。確かにその時間があったことが、傷という形で残っていくんだ、とぼくは思いました。
中井: 本作は忌憚なくいうと、DEIを全面的には意識していない、ある意味で現代っぽくない雰囲気がありますね。どこか懐かしさのような。時代の中における、この作品の立ち位置をどう感じていますか?
玉田: オダギリジョーさんも「2000年代初頭の映画のにおいを感じる」と言っていました。ぼくも、学生時代に映画を観始めた当時の、好きだった日本映画の雰囲気をダイレクトに出せる映画になると思いました。
確かに、国際的に評価されている映画やヒットしている映画は、社会問題や多様性の問題をテーマに取り込んで、エンタメとして昇華してみせているものがすごく多い。ある意味で、海外映画祭で評価されるためのひとつの条件にもなっていると感じます。ただ、それらも素晴らしいと思う一方、それだけがすべてじゃない、とも思うんですよ。

オダギリジョーという磁力が集めた奇跡のキャスティング
中井: この映画、異様とも思えるほどすごいキャスティングです。ただ、映画の規模感などを考えると、通常これだけのキャストは集まりません。背景には何があったのでしょうか。
玉田: オダギリジョーさんの存在が大きいと思います。この映画は、主演のオダギリジョーさんが、共同プロデューサーにもなっています。オダギリさんは、この作品に対してすごく思い入れがあって、そこに動かされて「参加したい」と思ったキャストが多いように感じています。
中井: オダギリさんはキャスティングの部分でも、かなり関与してくださったのでしょうか。
玉田: そうですね。オダギリさんには主演を打診して、引き受けていただきました。その後、プロデューサーなど一部スタッフでロケ地の長崎に行ったのですが、オダギリさんも来るとおっしゃって。「そんなことあるんだ」って思いましたね。オダギリさんは、その時点ではまだプロデューサーじゃなく、俳優として参加していました。
現地でみんなでご飯を食べているときに、キャスティングの話になりました。そこでオダギリさんが「この人、この役に合うと思うんですけど、どう思います?」と何人も提案してくれて。「キャスティングも協力しますよ」とまで言ってくださって、最終的にはこの映画にプロデューサーとしても参加するという話になりました。
中井: 面白いですね。ぼくが個人的に、俳優としてのオダギリさんがこれまで演じた役で印象的なのは、中野量太監督の『湯を沸かすほどの熱い愛』(2016年)や同じ中野さんの新作『兄を持ち運べるサイズに』(11/28公開)で演じた、不完全性が強い父親像です。この映画でも、完璧とはとても言い難い男を演じていますが、玉田さんは、どうしてこの映画でオダギリさんを主役に据えようと思ったのですか。
玉田: まず最初に、オダギリさんが頭に浮かんだんです。戯曲では主人公の年齢が37歳ですが、人生を達観して諦めの状態になっている男の姿をいまの37歳が演じるにはちょっと若すぎると感じました。そこで、40代後半ぐらいの俳優で考えたときに、まず最初にオダギリジョーさんが浮かんできました。
ぼくが学生時代に観てきた日本映画の中のオダギリさんのイメージで言うと、たとえば青山真治監督の『サッド ヴァケイション』(2007年)や西川美和監督の『ゆれる』(2006年)。とくに『ゆれる』の後半、すさみきっているオダギリジョーがもう少し歳を取ったらどうなっているだろう、というイメージと繋がっていった気がします。あと、そんなオダギリジョーが長崎の街に溶け込んだとき、『ゆれる』とはまた全然違うものに変容するだろうなと。それが今回演じる治になるだろうと想像しました。

髙石あかりという発見と、俳優たちとの関係性
中井: オダギリジョーさん以外にも、松たか子さんや満島ひかりさんをはじめ、キャスト陣の実力が圧倒的ですが、その中でも個人的に白眉だったと思うのは、優子を演じた髙石あかりさんです。優子役はどうして髙石さんだったのでしょうか。
玉田: 優子役はオーディションで決めました。たくさんの方と会った中で、最後に髙石さんと会いましたが、頭二つ三つ抜けて違ったんですよね。
中井: オーディションでは「部屋に入った瞬間に分かる」みたいな話も聞いたことがありますが、実際はどういう感じでしたか。
玉田: 入った瞬間とまでは言わないですけど、第一声で分かる。映画でも使っているワンシーンをテキストで読んでもらうんですけど、ひと言でしゃべった時点で「ああ、もうこの人がいい」というくらい違ったんですよね。たとえば、つまらない映画を観たとき、ワンカット目から「これやばいかも」と思う。そういう感覚って大抵2時間ずっと続くじゃないですか。面白い映画のときも「これいいかも」と思ってたら、それが2時間続く。今回もそれと近い感じで、髙石さんの第一声がよくて、そのまま最後までずっとよかった、という感じです。
中井: 優子がイマイチだったら、この映画そのものが終わってしまうくらいの重要な立ち位置でした。オダギリさんと髙石さんの掛け合いは現場でどう見ていたのでしょうか。
玉田: すごく相性が良いなと思いました。髙石さんは、メディアを通じての印象だけ見ていると活発そうに見える。でも、撮影現場でたまに休憩時間に喋ると、意外と人見知りなんです。無防備に開いているよりも、ちょっと警戒心があって閉じている感じがしたんですよね。もちろん相手との関係性にもよると思うんですけど。
それに対して、オダギリさんってちょっと陰がある感じがするじゃないですか。でも、ご本人はすごくオープンなんです。明るいコミュニケーションを取るスタイルではないですが、人との交わり合い方も自分なりに持っていて、人たらし的な魅力がある人だなと思います。そんなふたりの対照的な感じがすごく良くて。そういうふたりだから良いバディになる感じに近い。人としての相性の良さも感じて、それが芝居にも出ています。
中井: 俳優の演出は、細かく指導をしたのでしょうか。
玉田: 最初の方はしっかり指導したんですよ。間とかもすごく伝えました。でも、だんだんやらなくなっていきましたね。演劇で演出するときのぼくの癖だと思うんですけど、外側から造形しようとする。演劇の場合は、1カ月くらい稽古をするから、外側からのディレクションに対して、俳優たちが馴染んでいく時間があります。でも、このやり方は映画では良くないかもと思いました。それよりも俳優たちが持っているものをうまく引き出せる環境を整えているほうが、演出として有効なのかもと思って、だんだん動線くらいしか言いませんでした。撮影中盤くらいからは、彼らの映画のトーンに対する理解が膨らんでいって、むしろ何も言わなくなったほうが演技が良くなっていくのが面白かったです。

長崎の坂と階段が生み出す、映画的な空間演出
中井: 長崎というロケーションが、本作において不可欠だったと感じます。とくに、土地の特徴でもある坂や階段を意識的に上り下りするという行為を撮っていて、その見せ方が本作を映画にしていると思いました。演出面の意図を教えてください。
玉田: 坂って、面白いんですよね。高低差があることで、のぼったり降りたりという行為が生まれる。そして、上に立っている人、下に立っている人の存在で、映画の匂いがするんですよね。
中井: 家の場所が良いですね。家の前に坂や階段があります。道の傾斜の途中に家があることで、辿り着いた先ではなく、まだ過程である人生を想起させます。オダギリさんが家に向かってとぼとぼと坂や階段を上っていくバックショットも良くて、彼自身が抱えてしまった虚しさみたいなものが、坂や階段をのぼる足取りや、背中に表現されています。
玉田: そうですね。そして、上下があることで人物の状態や関係性を表せます。松たか子さん演じる恵子が去っていくシーンがありますが、彼女は坂を下っていく。そこで、逆に坂を上ってくる優子とすれ違いますが、上に辿り着いた優子が、下にいる恵子に向かって「おじさんのことは私が面倒見ますから!」と叫びます。ここでは、下に恵子がいることがすごく重要なんですよね。あれを平地で言ってたら、あの感じが全然伝わらない気がする。下にいる恵子がそれを聞いて、また下っていくという一連で、この物語から降りていくという感じが表せます。階段や坂って、演出上の人間関係を伝えるときの装置として、すごく良い。

演劇的な奥行きと、環境の中で描かれる人間
中井: 他にも、撮り方で気になったのは画面の奥行きなんですよね。通常、登場人物を横の位置に並べるものが多いと思いますが、この作品では、明確に奥にいる人物と手前にいる人物という形で並べている印象がありました。その意図はどういうことでしたか。
玉田: 奥行きで見せるのが好きなんです。まず、縦のストロークがあるロケ地を選び、奥でも何かが動いている。ひとつの画面の中に情報が多くあってほしくて、奥でも時間が動いていることを意識しています。同時に両方がひとつの画面に映っていて、奥にあるものが手前側に影響することで、手前の芝居が変わったり、フレームの外側にあるものが関わったりしてくることが面白いと思っています。
中井: それは演劇的だと思っています。演劇では、板の上でそれぞれが独立して他者に関係してくることが良くあると思います。この映画でいうと、治が遅れてやってくる会社の飲み会のシーンは、まさにそうだと思います。森山直太朗さん演じる陣野が画面の奥の方から手前にいるオダギリさんをチラチラ見ている。そして奥から手前にやってきて治に干渉する。その様子は画面にずっと映り続けていていました。このシーンは、いくつか必要なショットを組み合わせることでも成立したと思うんですよ。でも、そうしなかったのは、どこか演劇的な見せ方だなと思いました。
玉田: あのシーンは、カットを割ったらいいんじゃないかと助監督に言われました。あのシーンは要素が多いんですよね。その中に陣野という重要な人物もいる。普通はひとりひとり、カメラで抜いていったら良いと思います。でも、あの場で起きているダイナミズムの中にいる治、というものを撮りたい。だから、動線を整理して、情報を順番に出していけばワンカットで撮れるんじゃないかと考えていました。
中井: なるほど。会社の飲み会の座り位置も良かったですね。治が画面手前側のちょっと外れたところに座っているのが、彼の抱える孤独を示している。奥の喧騒があって、手前が静寂であるというところに、彼の心情や立ち位置みたいなものが見えてきました。
カメラの置き場所と被写体との距離感も面白かったです。クロースアップは少なめで被写体と距離がある見せ方だったように感じました。被写体に寄って見せる行為は、演劇ではできません。演劇は観客が見る位置から被写体までの距離が決まっているので、そこに演劇独特の見せ方があります。一方、映画だと観客の目の代わりとなるカメラの位置を監督が変えられる。演劇ができなかった超クロースアップをやることも可能です。しかし、映画にした際にあまりやっていないのは、被写体と距離を取りたかった、ということでしょうか。
玉田: 環境の中にいる人を、環境全体で撮るようなショットが欲しかったんです。撮りたいものは生活で、人間の気持ちにフォーカスをあてるというより、家の中で動いている人を撮ることで浮かび上がる、その人の本当の気持ちを撮りたいと思っていました。

光と闇が共存する映像美と、死の気配を漂わせる空間
中井: 照明と色彩の設計も面白いです。家の中は、とくに夏の日差しを意識していると思いますが、じわじわと締め上げるような暖色の印象があります。そして、終盤のあるシーンでは、心情変化に伴うカタルシスとともに、若干青みがかかってくるというように、配色が変えられていたと思います。
玉田: グレーディングに関しては、(撮影の)月永雄太さんがやってくれました。ロケハンに行く前に、月永さんと照明の秋山恵二郎さんと3人でご飯を食べながら、ルックの話をしたんです。そのときに、明るいところと、めちゃくちゃ濃い闇が同時に共存するようなショットにしたい、という話をしました。
参考作品として、是枝裕和監督の『幻の光』(1995年)があります。闇が印象的な映画ですね。この映画は、石川県の輪島市の古い日本家屋が舞台になっています。日本家屋はふすまを全部開け放つことで広い座敷にできるけど、奥の方には光が入らない。一方で手前は縁側になっていて光が差し込む。ひとつの空間の中に光と闇が共存していく感じを、今回の映画でやりたかった。
色合いについても、『幻の光』は奥能登が舞台で寒い時期の物語だったので、画面が寒い色合いなんですよ。今回は、あの『幻の光』のショットを、夏の日照りが続いて水も出ない長崎の中で撮りたい、という話をしました。それを踏まえて、月永さんが暑苦しい中での闇を作ってくれて、あの色合いになったんだと思います。

中井: 舞台となる家はどうやって決めたのでしょうか。
玉田: あの家、実はすぐ決まったんですよ。制作部の中村哲也さんが何週間か前からいろいろ探してくれたんですけど、メインロケハンに行った初日、空港の駐車場で車に乗るなり、いきなりその物件の資料を渡されました。それで、すぐ行ったんですよ。そこですごく良いなと思いました。
まず雰囲気もイメージにすごい合っていて、縦の奥行きもある。玄関を開けた目の前がひらけているというのは、家から外を覗く雨のシーンが撮れる。駐車場や雨降らしに水をためるプールを置くスペースもあって撮影条件も満たしていました。
中井: イメージどおりだったんですね。ぼくはこの家の間取りと、それを活かしたシーンが面白いと思いました。とくに気になったのは、玄関横の部屋でオダギリジョーさんと松さんがもみ合うシーンです。その部屋は、高石さん演じる優子と高橋文哉さん演じる立山が、性的な行為を開始する場所でもあります。どこか異質だったと感じていますが、あの空間は一体何だったのでしょうか。
玉田: あの部屋から死の気配を感じています。実は、治と恵子の息子のものが置いてある部屋でもあります。優子があそこで性行為をしようとするのも、いつ見つかっても構わない、という破滅に向かう感覚があります。彼女は「白く白く光って消えてしまうといい」と言いますが、別にいつ自分が消えてもいいという感覚で生きている。だから、いつ人が入ってくるか分からないような場所が必然な気がしました。
中井: ふすまを半ば閉めて、影だけ見せる演出だったのはなぜですか。
玉田: この映画の全体を通して、決定的な何かが起きるシーンは、遠くからそれを目撃してしまったという距離感を意識しています。肉薄していくように撮るよりも、どこか冷めた視点で決定的なことが起きてしまった様子をカメラでおさえる、というアプローチが作品のトーンとして必要だと感じていました。
中井: なるほど。こうやって演出について精緻にお話を伺っていくと、映画『夏の砂の上』は、一見すると地味でオールドタイプに見えるかもしれないですが、あらゆるところが映画的で、演劇的要素も感じさせ、玉田さんのキャリアを踏まえた細やかなこだわりが詰まっていますね。
玉田: ありがとうございます。確かに、物語として驚くような展開のある映画ではないかもしれませんが、環境を含めて人間をしっかり描くことこそ武器だと思いながら作っていました。おそらく咀嚼には少し時間がかかる映画ですが、その分、咀嚼しがいがある作品だとも思っています。

玉田真也監督と向き合って印象深かったのは、分かりやすさに迎合することなく微細な部分まで徹底的にこだわる一方で、他者の意見に真摯に耳を傾け、スタッフとの協働を通じてより良い作品を生み出そうとする姿勢を持っていること。自らの表現軸を保ちながらも全体の調和を重視する、絶妙なバランス感覚の持ち主だった。演劇的な奥行きのある画面構成や、長崎の坂と階段を効果的に活用した映画的な空間演出は、単なる技術的な選択ではなく、登場人物の心情や関係性を視覚的に表現する監督の哲学から生まれている。
本作が示すのは、現代の映画界における、評価のための多様性重視の潮流とも一線を画した、人間の普遍的な孤独への眼差しである。「咀嚼しがいがある作品」という監督の言葉が示すように、この映画は即座の感動よりも、観た後にじわじわと心に残る余韻を重視している。単純化することを避け、痛みを伴い、考え続けることを要求する表現のあり方は、他者とのつながりを手軽に希求する現代の観客にとって、実は必要な映画体験なのかもしれない。
取材・文:中井圭(映画解説者)
編集:大沼芙実子
撮影:新家菜々子
最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。
こちらもぜひチェックしてください!
