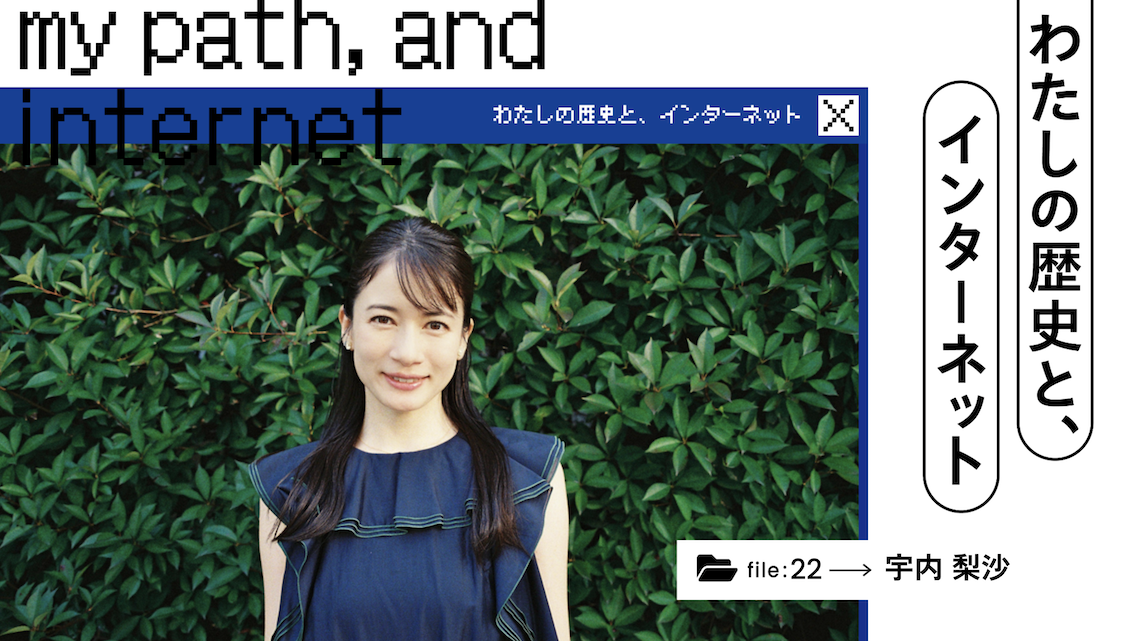
いまや誰もが当たり前に利用しているインターネット。だが、そんなインターネットの存在がもしかしたらその人の歴史や社会に、大きく関わっている可能性があるかもしれない…。この連載では、さまざまな方面で活躍する方のこれまでの歴史についてインタビューしながら「インターネット」との関わりについて紐解く。いま活躍するあの人は、いったいどんな軌跡を、インターネットとともに歩んできたのだろう?
▼これまでの記事はこちら
今回お話を伺うのは、元・TBSアナウンサーで現在はフリーとして活躍する宇内梨沙さん。幼い頃からゲームが大好きだったという彼女はいま、ゲームの発表会の司会や、ゲーム実況など、好きなことに関わる仕事を楽しんでいるようだ。
そんな宇内さんに、ゲームと出会ったときのことから、いまのキャリアに至るまでの歴史について話を伺った。

インターネット上で繋がる、初めての体験
宇内さんが初めてインターネットに触れたのはいつですか?
母の携帯を使わせてもらって着メロをダウンロードしたのが最初です。当時はインターネットの通信料が定額制ではなかったので、通信料が高くなってしまって怒られた記憶があります(笑)。あとは当時「ぱどタウン」(※1)という自分の部屋を作れるサイトがあって、友達と一緒に楽しんでいました。人とインターネット上で繋がる、初めての体験だったと思います。
ゲームはいつ頃から始められましたか?
5つ上の兄の影響で物心ついたときからゲームが身近にあったので、小学生に入る前からゲームをしていたかも。当時はいまのようなオンライン対戦はないので、皆の家に集まってNINTENDO 64やニンテンドーゲームキューブなどをプレイしていましたね。兄がパソコンを持ち始めてからは、一緒にゲームの攻略動画をインターネットで見ていました。
宇内さんといえばゲーム実況のイメージがありますが、動画配信を見始めたのはいつからですか?
高校生になってからですね。とくにニコニコ動画をよく見ていました。巨大プリンを作ってみたという動画や、ゲームの世界に出てくるアイテムを作ってみたというような、面白いことに挑戦する配信者がたくさんいました。いまでこそYouTuberは一般化されていますが、当時の「テレビでは見たことのない、知らない世界に出会っちゃった!」という衝撃は忘れられないです。
ただ見るだけでなくて、他の視聴者のコメントが流れてくることも新鮮でしたね。私もよくコメントしていました。テキストサイトから始まって動画が当たり前になっていくという、インターネットの進化をリアルに体験できた世代だと思いますね。
ちなみに宇内さんはいまもニコニコ動画を見られているんですか?
高校生のときほどではないですが、たまに見ますね。ニコニコ動画にしかない動画があるんですよ。皆さんずっと消さずに残してくれるんですよね。そこに、いまだにコメントがついていたりしてて(笑)。
※1 用語:「ぱどタウン」地域密着型の情報誌「ぱど」のインターネット版として2001年に誕生した仮想空間。掲示板の書き込みやログインによってレベルが上がると自分の部屋やキャラクターが変更できた。2017年にサービス終了

配信者は憧れの職業だった
高校生の頃は、配信者になりたいと考えたことはありましたか?
はい、実は自分も配信者になってみたいなと憧れていました。でも家にはノートパソコンしかなくて、学生の私には機材を揃える余裕もなかったですし、なんだかんだ現実を見るタイプだったので真面目に大学受験の勉強をしてましたね。
そこから、アナウンサーになったのはどうしてですか?
たまたま大学の入学式で、テレビのインタビューに声をかけていただいたんです。それから学生の間に何度かテレビに出演する機会があって、そこでお会いした局のアナウンサーさんが素敵だなと思ったんです。それまではテレビは遠い存在だったのですが、仕事を通じてより身近に感じられるようになり、わたしもこんなお仕事がしてみたいとアナウンサーを志しました。
アナウンサーのお仕事は、配信者の夢とはまた別のきっかけだったんですね。
そうですね。根底にニコニコ動画の体験はあったかもしれませんが、別の感覚でした。入社してからも、いつか配信者をやってみたいなという気持ちもあったのですが、まだYouTuberも出てきたばかりで、動画に対する知名度がそこまでありませんでした。
ただゲーム好きということは知られていたので、会社でeスポーツに注力する組織ができた際にメンバーに入れていただいたんです。そのときにちょうどコロナ禍になってリアルの大会ができなくなって。その代わりにYouTubeチャンネルを立ち上げようという話になり、ゲーム実況の配信をすることになりました。

視聴者と一緒にゲームする楽しさと大変さ
夢だった配信のお仕事を実際に始められてどうでしたか?
嬉しかったですが、とにかく続ける大変さを体感しましたね。 会社の全面サポートがある上でですが、アナウンサーの業務もあるなかで動画撮影もして、見せ場を作らないといけないプレッシャーもありました。それに、配信ではいつも私が普段プレイするよりも難しいゲームをやっていたんです…。
外から見ると好きなことで楽しくお金を稼いでいると思われがちですが、YouTuberや配信者としてお金を稼ぐには、本当に責任感を持ってやり続けている方でないとできない仕事だなと実感しました。
コメントする側から、される側になって、反応はどのように捉えられていましたか?
一人だとクリアできていないゲームも、みんなの応援があって頑張れましたね。何回もトライしすぎてもう無理だと思うときも、猛者たちが攻略方法を色々教えてくれたり、一緒に考えてくれたりして、最後はみんなとクリアした感覚がありました。
学生の頃、みんなで集まってゲームをしていたときの感覚とも近いかもしれませんね。
そうですね。私が小さい頃、まだバイオハザードが怖くて一人でできなかったときに、兄がセコンドでついて応援してくれていたことを思い出します。いまはインターネットを通じて、視聴者の方がセコンドとなってくれている気がします。ときには厳しい声もいただきながら一緒にプレイしてますね(笑)。
また「毎週楽しみにしている」という声が届いたことも励みになりました。私が高校生のときにニコニコ動画をみて得ていた体験を、いまの視聴者の方にも味わって頂けているんだと嬉しかったです。

仕事として自分が好きなことに関わりたい
いまはテレビ局を退職されてフリーで活動されていますが、きっかけは?
退職の理由は、自分の時間を大切にして、ゆとりを持った生き方をしたいからでした。でも同時に、ずっと仕事として自分が好きなことに関わり続けたいという思いもありました。
いまはゲームのお仕事をすることが多いです。自分の好きなことにもっと焦点を当てて仕事をしたいと考えると、やっぱりエンタメの世界で生きていきたいなと感じたんです。
これまで以上に、好きなお仕事の選択肢も広がりそうですよね。
そうですね。いまエンタメといったら、それぞれの会社がYouTubeで公式チャンネルなど独自のメディアを持っていて、配信番組がメインなんです。その番組に出たり、発表会で司会をしたり、テレビ以上にインターネットの世界でお仕事する機会が増えましたね。
あとは、ゆるゆると話ができる場として、Twich(※2)というゲームに特化した生配信プラットフォームもやっています。そこではより気楽に配信していて、「今日あんまり元気ないんだよね〜」とか弱音も聞いてもらってます。
プラットフォームに、Twichを選んだのはなぜですか?
秘密基地感が欲しかったからですね。たとえばYouTubeはいまや誰のデバイスにもアプリが入っていると思うんですけど、Twichはまだゲーム好きな人などにしか入ってないのかなと。
配信では自分自身の内面の話もしているので、視聴者が限られた場所で配信したかったんです。
自身で心地よいと感じる場所を選択して発信することも大事かもしれません。
たしかに安心できる場所として選んだというのはありますね。YouTubeはもはやマスとも捉えられるメディアなので、きちんとネクタイを締めて出ないといけないと思うのですが、Twichはよりくだけた話ができます。
あとは、元テレビ東京アナウンサーの田口尚平君とPodcastをしています。アナウンサーって、司会進行がメインなのでオフィシャルな場で自分の意見は求められないのですが、インプットを誰よりもしていると思うんです。自分の感想や考えがあるのに出しどころがないから、ふたりで好き勝手に話せる場所を作りました。
テレビ局のアナウンサー時代は、自分の発言ひとつとっても会社の意見に捉えられかねないので常に気をつけていましたが、それに比べたらいまは気楽に話ができます。自分の責任は自分で取る、ということだけですかね。
ちなみに、宇内さんは普段もオンラインゲームはしているんですか?
昨日も「Pokémon UNITE」というゲームをしていました!一緒にゲームをしたい人には、オンライン上でフレンド申請を送ることができるゲームです。私は知らない人からの申請も基本的には許可しているんですけど、たまたまそのひとりから急にゲームに誘われて。
声は出さないのでチャットで「よろしくお願いします」とか必要最低限の会話をしながらも、お相手の方が気を遣ってリードしてくれたり、グッドボタンを押し合ったりという、そんな何気ない会話が良いなって思いました。たとえばトイレに忘れ物をしたときに知らない人が拾って渡してくれたというような、何気ない日常の心温まるやりとりを感じています。
※2 用語:「Twich」Amazon.comの子会社であるTwitch Interactiveが運営するライブストリーミングプラットフォーム。2011年にサービスを開始し、ゲーム配信として10〜30代を中心に利用者を集めている

ゲームが自分の気持ちを守ってくれた
改めて宇内さんがゲームを好きな理由はどこにあるんですか?
なんでなんだろう?と自分でも改めて考えたんですけど、ゲームはいろんなエンタメのなかで唯一、自分自身が展開に関わることができるからなんだと思います。
映画やドラマ、アニメも面白いし好きですが、どうしても受動的になってしまいますよね。その点、ゲームは自分がプレイしないと物語を体験できません。ゼロイチで作ることは無理なんですけど、自分は能動的に関われる方が好きなのかなって。それに、現実の世界でうまくいっていないときもゲームのおかげで気持ちを切り替えられています。
ゲームに励まされてこられたんですね。
昔からそうでしたね。小学生で友人関係がうまくいかなかったときも、家に帰って「ファイナルファンタジーX」をやって励まされていました。ゲームのなかで、普段生きている何百倍ものスケールのなかで人類を守るために戦ってるんだ!と思うと元気が出てくるんです。ゲームに気持ちを繋いで貰っていましたね。
BIGLOBEのスローガンは「好きが、未来を変えていく。」なのですが、それにも近いように思います。
アナウンサー時代にも、どうしてもモチベーションが上がらないときは、家に帰ったらまたゲームができるじゃん!と思ってテンションをあげていました。
そう思うと、常々、精神的に自分のピンチを迎えたときにゲームが支えてくれていました。好きでいることが未来を作るのはもちろん、自分を守ってくれたなと本当に思いますね。
仕事と好きなことを一本化することはリスクや責任も伴うと思うんですけど、落ち込むことや大変だったときも、仕事が終われば、また別のゲームができる!と思って励まされています(笑)。

<今回のインターネット・ポイント>
インターネットは、ゲーム文化の発展を大きく方向づけた要因のひとつと言えるでしょう。1990年代末、個人がHTMLで作った攻略サイトや掲示板、チャットルームなどが登場し、ゲームはローカルな遊びから、知識や攻略を「共有する文化」へと発展していきました。
2006年に誕生したニコニコ動画は、実況プレイ動画、ゲームBGMなどの投稿が盛んになり、ゲームを「見る」「語る」「つくる」コンテンツとして再定義しました。この“コメントが流れる”動画体験は、双方向性と共同視聴の感覚を強め、YouTubeやTwitchに続く配信文化の下地となっています。
現在では、VTuberやプロゲーマーによるライブ配信、eスポーツ大会のリアルタイム中継、企業公式チャンネルによるゲーム番組など、ゲームはインターネット上で「見られること」を前提とした表現へと進化しています。
宇内さんのように、ゲーム実況や配信を通じて自身の言葉と感情を共有する人も増え、ゲームはますます「共体験型メディア」としてその存在感を強めています。インターネットは、ゲームを個人の趣味から社会的な文化へと押し上げる推進力となりました。

宇内梨沙(うない・りさ)
1991年生まれ。2015年にTBSテレビに入社し、『アッコにおまかせ!』『ひるおび』などを担当。その後もスポーツや経済など幅広いジャンルに携わる。TBSラジオでは『アフター6ジャンクション』のパートナー等も務めた。2025年3月に同社を退社。以降配信番組の出演やゲーム大会の司会進行、コラム執筆など幅広く活動を行う。
取材・文:conomi matsuura
編集:大沼芙実子
写真:服部芽生
最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。
こちらもぜひチェックしてください!
