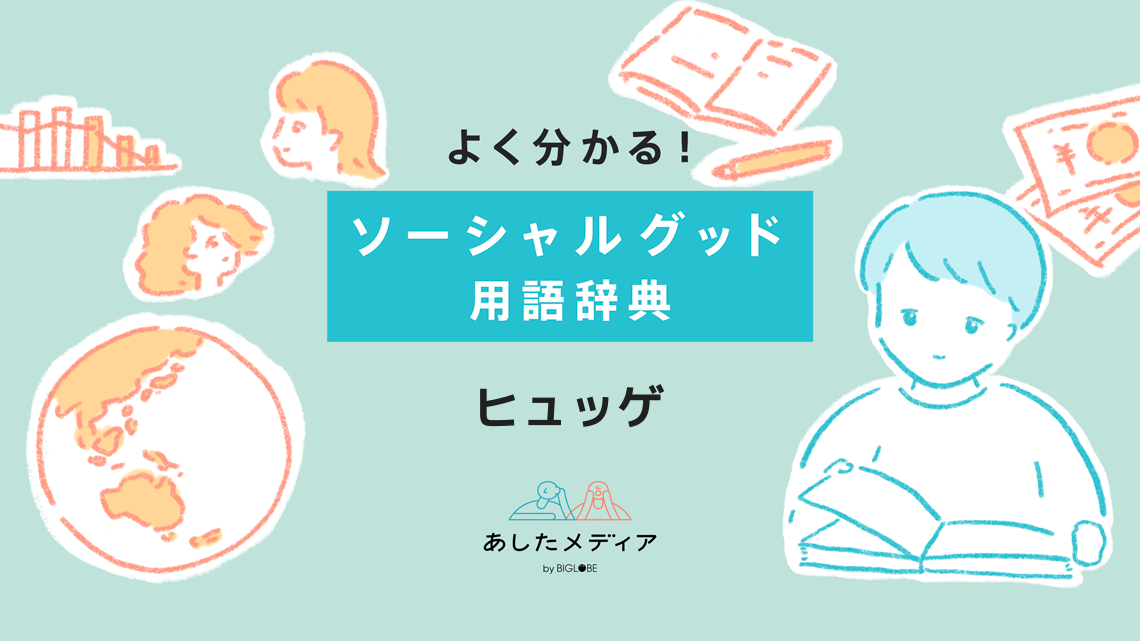
デンマーク語で「心地よい時間」や「居心地の良い空間」を意味する「ヒュッゲ(Hygge)」。世界幸福度ランキングで常に上位に位置するデンマークの、幸せな暮らしの秘訣として世界中で注目を集めている。2025年の世界幸福度調査では、デンマークは137カ国中2位にランクイン。対して日本は55位という結果であった。この大きな差の背景には、デンマーク特有の生活文化「ヒュッゲ」の存在が指摘されている。
本記事では、ヒュッゲの本質的な意味から、北欧の別の概念「フィーカ」との違い、さらに日本での取り入れ方まで、徹底的に解説していく。
ヒュッゲの本質
本章では、ヒュッゲの定義とその歴史的背景を紐解くとともに、日本文化との類似点についても考察する。
ヒュッゲの定義と歴史的背景
ヒュッゲとは、単なる「くつろぎ」以上の意味を持つ生活哲学である。1800年代にノルウェー語の「ヒュッゲリ(hyggelig)」からデンマーク語に取り入れられたこの言葉は、今やデンマーク人のアイデンティティを形作る重要な価値観となっている。英語辞書サイト「LEXICO」では「普段の生活における快適さや、心地よさ」と定義されており、日常生活の中で感じる小さな幸せを大切にする考え方を表している。
2016年にはイギリスの流行語大賞にノミネートされ、その後欧米を中心に世界中で注目を集めることとなった。現代社会特有のストレスや疲労に対する解決策として、多くの人々の心に響いたのである。
日本文化との類似点
日本語で例えるなら、こたつでみかんを食べながら家族と過ごす温かな時間や、縁側で日向ぼっこをする穏やかなひとときに近い。古くから「一期一会」や「わびさび」という概念を持つ日本人にとって、ヒュッゲの持つ「今この瞬間を大切にする」という価値観は、とても理解しやすいものといえる。
しかし、ヒュッゲには物質的な豊かさではなく、人とのつながりや心の充足を重視する独特の価値観が込められている。それは現代の日本人が失いつつある「他者との深いつながり」や「ゆとりある生活」の大切さを、改めて気づかせてくれる概念でもある。
▼デンマークのエコビレッジに学ぶ“ゼロウェイストの哲学”とは
フィーカとの違い
ヒュッゲに似た習慣として、スウェーデン発祥の「フィーカ」という言葉があります。本章では、フィーカの本質と特徴を探り、ヒュッゲとの類似点や相違点を比較していきます。
フィーカの本質と特徴
北欧の暮らしを語る上で欠かせない「フィーカ(fika)」。スウェーデン発祥のこの習慣は、スウェーデン語でコーヒーを意味する「kaffi」が語源とされ、コーヒーブレイクを通じた交流を意味する。スウェーデンの職場では、一日に数回のフィーカの時間が設けられており、同僚とコーヒーを飲みながら会話を楽しむ。この習慣は、仕事の生産性向上や職場の人間関係の改善にも寄与しているとされる。
ヒュッゲとフィーカの比較
フィーカが「日常的な休憩時間」や「仕事の合間の社交」に重きを置くのに対し、ヒュッゲは「人生全体を通じての心地よさの追求」を意味する。フィーカが具体的な行動様式であるのに対し、ヒュッゲはより包括的な生活態度といえる。
また、フィーカが主にコーヒーを介した社交に焦点を当てているのに対し、ヒュッゲは空間づくりや照明、自然との調和など、より広範な要素を含んでいる。両者は相補的な関係にあり、北欧の豊かな生活文化を形成する重要な要素となっている。

デンマーク流・幸せな暮らしの作り方
デンマークが幸せな国として知られる背景には、気候風土や文化的な要素が深く関わっている。特に、デンマークの人々が大切にしている「ヒュッゲ」の概念は、幸せな暮らしを作り出す鍵となっている。本章では、デンマークの気候風土との関係性を探り、ヒュッゲを構成する3つの要素について詳しく解説していく。
気候風土との関係性
デンマークでヒュッゲが重視される背景には、長く厳しい冬の存在がある。冬季は日照時間が極端に短く、日によっては7時間程度しか日光を見ることができない。このような環境下で、いかに心豊かに過ごすかという知恵から生まれた文化なのだ。
しかし、この気候的なハンディキャップを、デンマーク人は逆手に取った。室内で過ごす時間が長いからこそ、その空間をより居心地の良いものにしようと工夫を重ねてきたのである。
ヒュッゲを構成する3つの要素
1つ目は、光の演出だ。デンマークはヨーロッパでも最もキャンドルの消費量が多い国の1つだ。一般家庭では、食事の際にはテーブルに複数のキャンドルを灯し、リビングルームにも間接照明を効果的に配置する。これは単なる照明としてではなく、温かみのある空間を作り出すための重要な要素として位置づけられている。
つぎに、自然との調和。木材を中心とした家具、季節の花々、そして窓から差し込む自然光を大切にする。特に家具選びにおいては、自然素材にこだわり、長く愛用できる質の良いものを選ぶ傾向がある。また、観葉植物を室内に置くことで、自然とのつながりを感じられる空間を作り出している。
最後に、人とのつながりも欠かせない。友人や家族を自宅に招き、手作りのお菓子やコーヒーを囲んで過ごす時間を大切にする。形式ばらない交流の中で、心が温まるような瞬間を共有する。この際、スマートフォンや電子機器は意識的に遠ざけ、対話に集中することが重要とされる。
また、食事の時間も重要なヒュッゲの機会として捉えられている。デンマークでは、家族で食卓を囲む時間を特に大切にする。テーブルには必ずキャンドルが灯され、ゆっくりと会話を楽しみながら食事をとる習慣がある。
▼北欧の学校「フォルケホイスコーレ」について詳しく知る
日本での取り入れ方
本稿の最後に日本の伝統文化とヒュッゲの融合、現代的なヒュッゲの実践方法を考察する。日本にヒュッゲを取り入れるためのヒントを探っていく。
日本の伝統文化とヒュッゲの融合
日本の生活にヒュッゲを取り入れる際は、デンマークの文化をそのまま真似るのではなく、日本の文化や生活習慣に合わせた解釈が重要となる。和室での団らん、季節の花を活けること、お茶を楽しむ時間など、日本の伝統文化の中にも、ヒュッゲの要素は数多く存在する。
特に日本には「一期一会」という、その時その瞬間を大切にする文化がある。茶道における静寂の時間、縁側での日向ぼっこ、縁台での夕涼み。これらは全て、ヒュッゲの考え方と通じるものがある。また、「しつらえ」の文化も、空間作りを重視するヒュッゲと共通する部分が多い。
現代的なヒュッゲの実践方法
現代の日本人の生活に合わせたヒュッゲの取り入れ方として、以下のような実践方法が考えられる。
デジタルデトックスの時間を意識的に設けることは、現代的なヒュッゲの実践方法として特に効果的である。SNSやスマートフォンから離れ、本を読んだり、音楽を聴いたり、あるいは静かに過ごす時間を持つことで、心の余裕を取り戻すことができる。
照明にもこだわってみるとよい。蛍光灯だけでなく、スタンドライトや間接照明を組み合わせることで、温かみのある空間を作ることができる。LEDキャンドルなど、火を使わない代替品を活用するのも一案だ。
自然を取り入れることも重要である。ベランダでのガーデニング、室内での観葉植物の栽培、季節の花を飾るなど、身近なところから始められる。これらは空間に潤いを与えるだけでなく、季節の移ろいを感じる機会にもなる。

まとめ
ヒュッゲは、特別な何かを加えることではなく、すでにある日常の中から心地よさを見出す考え方である。デンマークが世界一幸せな国の一つである理由は、この「小さな幸せ」を大切にする文化にあるといえるだろう。
それは必ずしも大きな投資や特別な時間を必要としない。むしろ、日常の中にある何気ない瞬間に意識を向け、その価値を再発見することから始まる。家族との食事、友人とのおしゃべり、一人で過ごす読書の時間。これらの時間に、より意識的に向き合うことで、生活の質は確実に向上していく。
物質的な豊かさや効率性を追求する現代社会において、ヒュッゲの考え方は、新しい幸せの形を示唆している。それは、誰もが持っている「心地よい時間」を大切にし、そこから生まれる幸福感を育んでいく生き方である。
特に現代社会では、デジタル化やリモートワークの普及により、人々の生活様式が大きく変化している。このような時代だからこそ、ヒュッゲの考え方は、より一層重要性を増していると言えるだろう。オンラインでのコミュニケーションが増える中で、実際の人とのつながりや、物理的な空間の心地よさを意識的に追求することは、心の健康を保つ上で欠かせない要素となっている。
ヒュッゲは、決して非現実的な理想論ではない。それは、誰もが自分なりの方法で実践できる、極めて実践的な生活哲学なのである。日々の暮らしの中で、自分らしいヒュッゲの時間を見つけ、育てていくことが、これからの時代を生きる私たちにとって、大きな意味を持つのではないだろうか。
文・編集:あしたメディア編集部
最新記事のお知らせは公式SNS(Instagram)でも配信しています。
こちらもぜひチェックしてください!
