
ある日突然、あなたは身近な人に巻き込まれて、雨の中を一緒に歩むことになってしまう。
こういうことがどんな人の身の上にも起こります。
人生には、こころのケアがはじまってしまうときがある。
(※)
こう綴られた、東畑開人さんの新著『雨の日の心理学 こころのケアがはじまったら』(2024年、KADOKAWA)。臨床心理士である東畑さんが、家庭や職場など、暮らしのなかで“誰かをケアする人”のために書いた本だ。
40歳を過ぎ、新たな視点で本を書くようになったという東畑さん。これまで数々の著書を通じて人々の心を照らしてきた東畑さんだが、本作は彼の著作における集大成とも言えるだろう。これまでの著書を振り返りながら、今回のテーマとなった、“心の雨の日”について伺った。
※【まえがき全文公開】東畑開人『雨の日の心理学 こころのケアがはじまったら』
https://note.com/kadobun_note/n/nfdb92d1dd108

心の奥にある気持ちを交わし合う仕事
この本で東畑さんは自身を「町の心理士」と称されていますよね。
なんとなくそういう気分になったのはこの数年です。それまでは「臨床心理学者」というのが自称でしたが、大学をやめて、カウンセリングルーム専業になってからは、自分は「町の心理士」だなぁと強く思うようになりました。
僕は東京でカウンセリングルームを開業していますが、そこで申し込みフォームに書かれる内容は、医療的な問題ではなく、人生の問題なんですね。
話を聞いていると本当にいろんな悩みがあって、東京というのは大変な町だなぁと思う一方で、悩んでいる人たちの暮らしの集積として、町ができていることも感じます。
そもそもですが、臨床心理士とは、どのようなお仕事ですか?
僕のいまの仕事の中心はカウンセリングなのですが、それは心という観点から、人々のさまざまな苦悩を分析して理解し、改善するために話し合いをする仕事ですね。世間では「聴く」仕事と思われますが、実際には「話し合い」の仕事です。僕もいっぱい喋ります。
医師が身体を理解して改善するように、あるいは政治家や社会運動家が社会を理解して改善するように、僕らの専門性は心を理解しようとするところにあります。たとえば、その人がどういう人間関係を生きてきたかとか、どういう生き方を選んだり、選ばされてきたかを理解することで、それをどのように変化させることができるかを考えていきます。
東畑さんはなぜ臨床心理士を目指されたのですか?
高校生のとき、倫理の授業でユングを知ったことがきっかけです。高校の授業というのは、ときおり神託的に響くんですよ。半分寝ているからかもしれません。“自分のなかに、知らない自分がいる、それが無意識だ”的なことを先生が言うんで、なにそれ深い!面白そう!となりました。
それから大学で臨床心理学を学びましたが、当初は学者になりたかったので、今みたいに現場の心理士として臨床ばかりやるような人生になるとは思ってもいませんでした。大学院で色々な現場の経験をするなかで、臨床は非常に面白いものだと感じたんですね。
そう感じた理由はなんでしょうか。
多分、率直で切実なコミュニケーションがなされる仕事だからだと思います。嘘が通じないんですね。僕が話を分かっていないときは分かっていないことに直面させられますし、今まで誰にも打ち明けていない秘密が語られることもあります。僕らは人生の大半を適当に生きているわけですが、そしてそれこそが健康だということですが、一方で真剣に生きている部分もあるわけです。この真剣な部分に取り組むのが心の臨床という仕事だと思います。

臨床心理学に、ツッコミを入れる
東畑さんは大学卒業後、沖縄の精神科デイケア施設に就職されます。そのときの発見を、『居るのはつらいよ:ケアとセラピーについての覚書』(2019年、医学書院)で書かれていますよね。
僕の本は、基本的に臨床心理学にツッコミを入れるという形で書かれています。具体的には一世代前の河合隼雄的な臨床心理学に対して、ツッコミを入れて、アップデートするというのが僕の全仕事の通奏低音になっていると思います。
『居るのはつらいよ』は、その点では一番わかりやすくて、「セラピー」という臨床心理学の王道に対して、「ケア」を対置して、現代における心の臨床を描こうとしたものですね。
その前には『野の医者は笑う:心の治療とは何か?』(2015年、誠信書房、その後文春文庫)という本で臨床心理学の分野を超え、沖縄のスピリチュアルヒーラーについて書かれていましたよね。
僕的にはこの本が最高傑作というか、一番自分らしい本だと思っているんです。スピリチュアルヒーラーも、臨床心理士も、全部フラットに並べて比べてみるという本です。それはこの社会の公認のものも非公認のものも、人が生きていくということを考えるときには、どちらもありうるだろうという考えからきています。
何が正しいかは、社会レベルではある程度決まるとしても、個人のレベルだとそれぞれの状況で多様だと、心理士という仕事をしていると思うんですね。自分という存在には非公認な部分が必ず残るものです。

いま、個人に関心を寄せること
既存の考えにツッコミを入れつつも、その後は『こころはどこへ消えた?』(2021年、文藝春秋)や『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』(2022年、新潮社)という、より個人の内面や心にフォーカスした本が続きます。それはどのような背景からでしょうか。
今振り返って思うと、ちょうどその頃、心について書くことへのニーズが多くあったんだと感じますね。コロナ禍における自粛など、社会が“みんなのため”と話すことが多くなった。それはもちろん大事なことでしたが、一人ひとりの心というものを考える力が失われているように思いました。政治的な時代だからこそ、同時に個人の心ということを考えるための回路を作り続けるのが臨床心理学というものの役割だと思っています。
困ったときに手に取れる本を
そのあと刊行した『聞く技術、聞いてもらう技術』(2022、筑摩書房)や、今回の『雨の日の心理学』では、心の“ケアをする側”のことについて触れられています。
ここ数年、講演や研修に呼ばれたときに「周りの人をどうケアすればいいですか」と問われることが多かったんです。社会にたくさんのケアにまつわる困り事があり、これにカウンセリングだけではなく、書籍や講演などを通して応答することも臨床心理士の役目だと感じるようになりました。
あと、自分自身も40歳前後から、臨床心理学に対する責任感が強くなってきたというのもあります。これは学会で中堅世代として責任ある仕事を任されることが増えてきたというのも背景にあるかもしれません。
昔は、本は自己表現であり、尖ったことを書く場所だと思っていて、自分なりに書きたいことを書いていたんです。でもそれだけではなくて、臨床心理学に求められていることを果たす本、つまり困ったときに手に取る為の本も書いていかねばならないと思うようになりました。

『雨の日の心理学』はとても読みやすく、誰もが気軽に手に取りやすい本だと感じます。
嬉しいな。読みやすいと言っていただけるとほっとします。僕自身、読書が好きで、つるつると読めてしまう、そうめんのような文章が好きです。結局、本は中身ももちろん大事だけど、読めたことそのものの楽しさというのものがあります。この本はオンラインの講義が元となっているのですが、文字に起こしたものを読んでみたら全然つるつると読めなくて。何回も読み直しては修正して、編集の吉田さんにもその度に沢山読んでもらいました。
文章を書くにあたって参考にしたことや、工夫した点はありますか?
最初の頃の本では高野秀行さんの文章を真似していました。今回は話し言葉なので、自分の普段使っている言葉で書いた気がします。でも原稿を直していた頃に千葉雅也さんの『センスの哲学』(2024年、文藝春秋)を読んで、改行にセンスが宿ると気づいたので、そこはかなり手を入れました。
あとは、比喩にこだわりました。心は物質じゃないんで、比喩でしか語れません。心について伝えるためには、相手の心に届く比喩を探さないといけない。これについてはいつも心がけています。
大学で教えていた時の名残ですね。授業で分かりやすく伝える工夫をしていた経験が活かされています。はじめの頃、授業で生徒全員が寝ちゃったことがあって。あまりの孤独で死にそうだったので、それ以来どうにかして起きててもらおうと知恵を絞るようになりました。かなり鍛えられましたね。
ケアは、専門家だけのものではない
東畑さんの著書では、医療人類学者であるアーサー・クラインマンの「ヘルス・ケア・システム理論」が度々登場します。この図式がケアを考えるうえでもっとも基本的で重要だと話されていますよね。

(『雨の日の心理学』p.26より筆者作成)
そうですね。この図だと、我々のような臨床心理士は専門職セクターにいて、『野の医者は笑う』で取材したようなスピリチュアルヒーラーの方は民俗セクターにいる。そしてこの円のなかで1番大きいのが、民間セクター。『雨の日の心理学』では、民間セクターの位置にいる人のことを書きたいと思いました。
これまでの著書を見ると、東畑さん自身は、この円が重なる真ん中の位置から語られているのではと感じます。
今メンタルヘルスケアの最先端とは、突き詰めると民間セクターの問題なんですよ。専門家だけがスペシャルなことをやるのではなく、みんなが助け合いをしているのを助ける臨床心理学へ変わっているように思います。そういう時代にものを考えたり、書いたりしてきたのだと自分では思っています。
東畑さんが特にそう感じるようになったきっかけはありますか?
ここ数年、いろんな場所へ講演に行ったり、オンラインで授業をしたりするなかで、講義に来るのは実際に困っている当事者ではなく、周りのケアをしている人だと感じることが多かったんです。それも、特別なことが起きている人たちだけが講演に来てる訳じゃないんだと。
たとえば学校の先生や企業の管理職の方もよく講演に来られるのですが、学校や会社では常にどこかで局所的に雨が降っているような状況でした。ここに書いている内容は、みんなの生活のなかにおけるケアの話です。心のケアが必要な状況に陥ることは誰にでもあるんじゃないかな。

町の心理士として、傘を差し出す
本作では、心がちょっと落ち込んだり、悩んだりすることを、心にとっての“雨の日”と例えられていますよね。雨の日が必ずあるように、心の雨の日も誰にでもあると。
人間というのは、医学的なうつ病ではなくても、うつっぽいときは結構あるものです。たとえば体は元気なのに会社や学校にどうしても行けないときってある。こういうときに、心には雨が降っている。そういうときにずる休みだと責めるのでもなく、何でもいいから休みなさいということでもなくて、微妙な雨模様を理解できるとケース・バイ・ケースでの対応が可能になるように思います。
普段人は、ケアの専門家と話している時間より、日々社会で過ごしている時間が圧倒的に多い。だからこそ、みんながお互いにケアできるような社会が当たり前になると良いのかもしれません。
本当にそう思います。普通の人が普通にケアするのが普通の生活だと思うんですね。でも、雨の日にはそれがうまくいかなくなる。そこに専門家が登場して、身近な人同士のケアを回復できるようにいろいろと尽力するわけです。そういうことの役に立つといいなと思っています。
『雨の日の心理学』が発売されてしばらく経ちましたが、どのような反応が届いていますか?
ありがたいことに良かったという感想をたくさんいただいて、ハッピーな気持ちです。それも、実際にケアをしている方々から助けられたという感想をいただいて。本で人助けができる実感があったのは、僕にとって大きなことでした。臨床心理士としていろいろとやれることがあるのだなと思います。
改めて、この『雨の日の心理学』はこれまでの東畑さんの考えや経験、そして今の社会に必要なことをまとめたような一冊であると感じます。
ありがとうございます。自分でも書いてみて驚きましたね、総集編みたいになっていたので。なんだかんだで、ある程度、自分の思考というか、理論が固まってきたんだと思います。逆に言うと、それゆえに最近はどこに行っても同じ話ばかりをすることになっているのですが(笑)。
40歳になると、業界でも中堅になって、チャレンジャーではなくなってくる。僕は先行世代に対する批判を強くやってきた人だと思いますが、それは新しいことを提唱するというよりも、僕達の世代の人たちが実際に毎日やっていることを言葉にしようという試みだったんです。それもひと段落したような感じがするので、現代的な「臨床の知」といえるものを、広く社会で役立ててもらえるよう、書いていくのが責任だと感じています。
★東畑さんの新著『雨の日の心理学 こころのケアがはじまったら』はこちら。
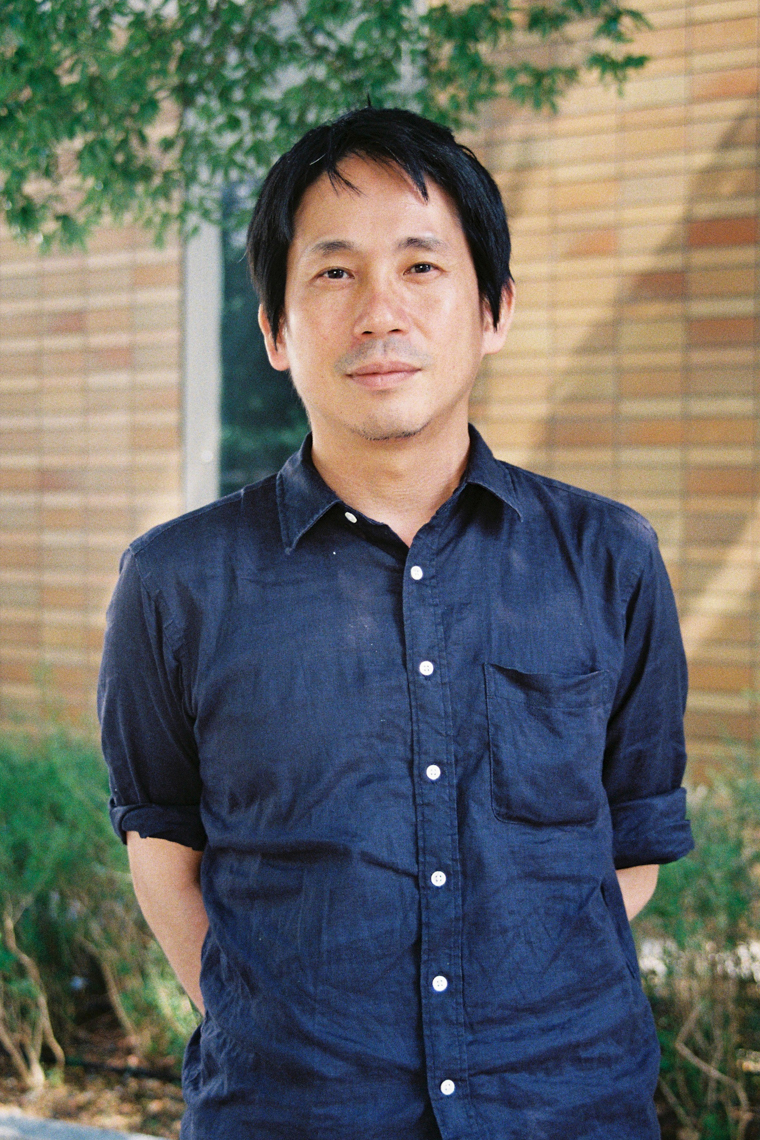
東畑開人(とうはた・かいと)
1983年東京都生まれ。博士(教育学)、臨床心理士。京都大学教育学部卒業、京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。卒業後は沖縄の精神科クリニックで勤務。転職し十文字学園女子大学で准教授を担当後、白金高輪カウンセリングルームを主宰。『居るのはつらいよ』で第19回(2019年)大佛次郎論壇賞受賞、紀伊國屋じんぶん大賞2020受賞。2024年9月2日に、最新刊『雨の日の心理学』を上梓。
取材・文:conomi matsuura
編集:おかけいじゅん
写真:服部芽生
