
パリは美しい街だが、映画で正しく描くのは難しい。観光名所を見せてばかりでは現実から目を背けていると指摘されてしまうし、例えば郊外の抱える問題をリアルに描いたとしてもそれがパリの全てであるわけでもない。時代とともにパリのイメージも、そして、パリを描くフランス映画も多様化していく。
フランスのセドリック・クラピッシュ監督も、パリを舞台とした映画を作ってきた1人だ。最新作『ダンサー イン Paris』(2023年9月15日公開)の公開を控えるが、この爽やかな秀作に至るまで、クラピッシュのキャリアは、パリの状況の変化、近年の映画の規範の変動の波、さらにはヨーロッパの危機などの事態に揉まれ、紆余曲折を経てきたように見える。
新作を紹介しつつ、新たな好調期に突入している彼の興味深いキャリアの変遷を見ていきたい。
ウェルメイドなヒューマン・コメディの作り手
重要監督が多くひしめく現代のフランス映画界において、個々の立ち位置を解説することは容易ではないのだけれど、セドリック・クラピッシュ監督は良質なヒューマン・コメディの作り手として、ヒットメイカー的な認知をされていると言っていいはずだ。大掛かりな商業コメディというよりはアートハウス的に落ち着いた佇まいを持ち、かといって難解さはなく、爽やかな鑑賞後感をもたらす作品を作っている。
21世紀に入ってからのフランス映画を牽引するアルノー・デプレシャン監督(1960年生)や、オリヴィエ・アサイヤス監督(1955年生)らがカンヌ映画祭の常連であるとすれば、クラピッシュ監督(1961年生)はカンヌやベネチアといったメジャー映画祭とは必ずしも縁が深くない。それでも、クラピッシュ監督の名前を聞くと瞬時に心地よい気持ちになるのは、その登場の仕方がとても鮮やかだったからだ。

パリを舞台に、愛猫を探す過程で様々な出会いを経験する若い女性の姿が清々しい『猫が行方不明』(1996)と、家族の団らんの場がとんでもない方向にずれて行ってしまう様子を描く爆笑必至の『家族の気分』(1996)は、新しいスター監督の誕生を確信させ、映画ファンを大いに喜ばせた。暖かく、ウィットが効いており、洗練されている。職人的な技量を感じさせる作家の登場だった。『家族の気分』はフランスのセザール賞(アメリカのアカデミー賞に相当する)で作品賞にノミネートされ、受賞は逃したものの、同作がクラピッシュのフランスにおける地位を確立したと言っていい。原作となる戯曲の作者で主演もしているアニエス・ジャウイとジャン=ピエール・バクリという中年俳優たちの存在も大いにクローズ・アップされ、成熟した大人たちによる皮肉たっぷりのコメディドラマを世界中が歓迎したのだった。
「家族」はクラピッシュがキャリアを通じて重視する主題となっていく。そしてゼロ年代に突入し、クラピッシュは大人たちから、青年たちに映画の視点を移していく。『家族の気分』は原作(戯曲)があったから大人たちの物語になったが、クラピッシュが描きたいのはあくまで悩める若者の姿なのであり、それは現在まで続いている。
『スパニッシュ・アパートメント』サーガのはじまり
『スパニッシュ・アパートメント』(2002)をいま振り返ると、実に様々な意味で興味深い。フランスとフランス映画におけるターニング・ポイントでもあったと言えるかもしれない。
まず、青春映画の傑作と呼ぶことに全く躊躇しないほど、面白い。パリに住む25歳の青年グザヴィエが、スペインのバルセロナに留学をする。しばし離れ離れとなる恋人のマルティーヌと空港で涙を流し合い(たかが隣国に行くだけなのに、とてつもなく大げさなのがおかしいし、すぐ近くの隣国なのにやはり未知の異国なのだというヨーロッパ人の意識も興味深い)、バルセロナに到着し、そこでヨーロッパの留学制度を活用した多国籍な学生たちが暮らすシェアハウスに住むことになる。
イタリア人、ドイツ人、デンマーク人、イギリス人、スペイン人からなる個性豊かな同居人たちに感化され、グザヴィエは大いに騒ぎ、友情を育み、異文化を学び、悩み、ついでに人妻に恋をし、もちろん遠距離恋愛のマルティーヌとの関係は複雑化し、1年間の留学生活を文字通り謳歌していく。一種のモラトリアム期であり、成長のための通過儀礼でもあり、つまりは「青春」なるものを痛快なエピソードの数々で描く快作なのだ。
主人公のグザヴィエに扮するのがロマン・デュリス、そして恋人のマルティーヌ役にオドレイ・トトゥ。ゼロ年代初頭にフランスが世界に売り出した若手スターの2人である。
オドレイ・トトゥは、『アメリ』(2001/ジャン=ピエール・ジュネ監督)が日本を含め爆発的な世界的ヒットとなり、一躍期待のスターの座に躍り出た。ロマン・デュリスも『スパニッシュ・アパートメント』の本国での大成功により、フランスの若手トップの1人となっていく。
ここで話がかなり逸れるのだけれど、2002年当時の日本におけるフランス映画の状況に触れてみたい。
フランス映画は、日本で長らく親しまれてきた過去があり、それは終戦直後にまで遡る。有名監督による名作は老若男女を惹き付けてきたし、60年代のヌーヴェル・ヴァーグは若いファンを熱狂させた。常に、日本における外国映画の成績において、フランス映画はアメリカ映画に次ぐ第2位の地位であり続けたのだった。そしてそれは、監督の力によるものというよりは、スターパワーに源があった。ジャン・ギャバン、カトリーヌ・ドヌーヴ、ブリジッド・バルド、アラン・ドロン、ジャン=ポール・ベルモンドといった名前は、映画ファンでなくとも日本人の間に浸透していた。しかし、おそらくはジャン・レノを最後に、「誰もが知っている」フランス俳優はいなくなっていった。
そして、ゼロ年代初頭、韓流ブームが日本映画界を席巻し、フランス映画は長年守ってきた日本における外国映画第2位の座を韓国映画に譲り渡すことになったのだ。
そこで、フランスとしては(もちろん当時は日本のマーケットはフランス映画にとってとても重要だった)是が非でも新しいスター俳優を日本に誕生させたいと願い、その期待を背負ったのが、オドレイ・トトゥとロマン・デュリスの2人だったのである。この辺りは、当時フランス映画祭で勤務していた僕が肌で感じていたことであり、新しい時代の到来に興奮したものだった。
さらに脱線を許されるならば、「パリと映画」を巡るオドレイ・トトゥとロマン・デュリスの縁も興味深い。『アメリ』はパリのモンマルトル地区を舞台にしたロマンティック・コメディの傑作であり、一躍モンマルトルは世界中の人々の憧れの旅行先となった。しかし、フランスでの公開当時、『アメリ』の描くモンマルトルはあまりにも現実の姿から目を背けていないかと、新聞紙上で大激論が交わされたのだった。冒頭に触れた、現代のパリを描くことの難しさを巡る議論は、『アメリ』から始まったと言っていいかもしれない。

一方、パリと言えばエッフェル塔であり、ベタであろうがなんだろうが、エッフェル塔はあらゆるフランス映画に登場し続けている。そして、そのエッフェル塔を設計したエッフェル氏の姿を描く『エッフェル塔~創造者の愛~』(21/マルタン・ブルブロン監督)に主演したのが、ロマン・デュリスである。パリを象徴する(建造物を設計した)人物としてロマン・デュリスが相応しいと判断されたわけで、彼のフランスにおける重要度は全く衰えを知らない。
2022年12月に行われたフランス映画祭に当作とともに来日したロマン・デュリス本人を前に、この20年のフランス映画の動向が脳裏に去来し、なんともしみじみとしてしまった次第である。
閑話休題。大成功を収めた『スパニッシュ・アパートメント』だったが、グザヴィエという主人公に愛着を持ったクラピッシュ監督は、グザヴィエのその後の物語を描いていく。ロマン・デュリスと(オドレイ・トトゥとも)組み続け、『ロシアン・ドールズ』(2005)では30歳のグザヴィエ、『ニューヨークの巴里夫(パリジャン)』(2013)では40歳になったグザヴィエの姿が描かれる。同一の俳優が同一の人物を長年に渡って演じ続ける稀有な例のひとつであり、クラピッシュの「青春三部作」とも呼ばれるが、驚くべきことに、実はここで終わらない。
時代の変化への対応
思えば、『スパニッシュ・アパートメント』が作られた2002年は平穏な時期だったのだろう。ヨーロッパの雑多性を象徴するアパートメントの場であったけれども、その混沌は牧歌的であったとも言える。
1990年代半ばからゼロ年代にかけては、ヨーロッパにとっては落ち着きの時期だった。冷戦終了後に続いたバルカン諸国の戦争もひと段落し、1999年からは統一通貨ユーロが導入され、単純化を恐れずに言えば、安定と拡大の時期だったはずだ。アメリカによる中東戦争への参加スタンスで揺れたものの、ヨーロッパ本土への影響は限定的だった。映画も、必ずしも社会イシューに意識的である必要が無かったと言えるかもしれない。
しかし2011年のシリア内戦を受け、大量の移民が欧州に流れ込んでくると、事情は一変した。それまでも移民を巡る問題は映画の題材となってきたが、2010年代に入ってからの深刻さは別次元のものとなった。移民/ボーダーを扱う映画が激増し、もはやブルジョワ的な欧州の若者たちが牧歌的な「スパニッシュ・アパートメント」をエンジョイする時期は過去のものとなった。移民問題に乗じて各国で極右政党が躍進し、英国はEUを去り、「ヨーロッパ問題」は複雑化する。

加えて、2017年を境に、価値観と規範の転換が顕在化し、表現者たちは主題の描き方に意識改革が求められていく。スマートなヒューマン・コメディを作ってきたクラピッシュも、ゼロ年代後半以降には現在の規範では採用されないであろう旧来の視点がまだ散見される。例えば、ずばり『PARIS(パリ)』(08)というタイトルを持つパリを舞台とする群像劇では、老男性教授が美人女学生にショートメールを送り続け、肉体関係を持つに至るが、やがて関係は終わり、老教授は若さを失った悲哀に浸るというエピソードが描かれるが、そこにセクハラ/パワハラの概念はまだ登場しない。また、アフリカから海を越えようとする人物の悲劇も描かれるが、エピソードのひとつとして埋没し、切迫感の薄さは否めない。2008年はまだそういう時期だった。
ゼロ年代までにある程度実績を残した作家が、10年代を乗り越え、20年代に継続して結果を出すというのは、誰にでもできることではないかもしれない。いかに自己のアップデートを図るかが問われる。
クラピッシュはまずグザヴィエの冒険を描き続け、グザヴィエの口を借りて、愛とは何なのかを叫び続ける。『ロシアン・ドールズ』では、幾人かの女性との不安定な関係を経て、やがて本当の愛を掴んでいきそうな30歳のグザヴィエの姿がある。『ニューヨークの巴里夫(パリジャン)』ではグザヴィエには2人の子があり、離婚も絡み、40歳になったグザヴィエの家族への向き合い方が物語の大きな柱となる。相変わらずグザヴィエは悩み、奮闘し、走り、少し成長する。悩める若者が悩める大人になっていく過程を描く、とても貴重で心地よい連作である。
監督と俳優が長年に渡りシリーズで並走するケースとしては、ヌーヴェル・ヴァーグの有名監督であるフランソワ・トリュフォーがジャン=ピエール・レオーを主演に自らの少年時代から青年時代を描いた連作に登場する「アントワーヌ・ドワネル」という主人公がとても有名だが、クラピッシュもロマン・デュリスと組んで作った「グザヴィエ・ルソー」を、映画史に残る人物として育てていったのだった。
そして、改めてコメディドラマにも力を入れる。おそらくフランスのTVドラマとしては、最も世界的にヒットした作品のひとつであろう『エージェント物語』(2015~2020)の立ち上げに参加し、アーティスティック・ディレクターとして、シーズン1の最初の2つのエピソードを演出する。芸能事務所を舞台にした『エージェント物語』は、有名俳優が本人役で出演することで話題になったが、当初は本人役での出演を断る俳優が多く、キャスティングに苦労したという。エピソード1の登場スターは『スパニッシュ・アパートメント』シリーズ全作に登場するセシル・ド・フランスであり、クラピッシュの存在がものを言ったに違いない。本作の大ヒットは、メインストリームにもアピールするクラピッシュの力量を改めて証明する結果となった。
さらに、クラピッシュが傾倒したのが、ダンスである。
バレエ映画作家、クラピッシュ
グザヴィエの「青春三部作」の2作目である『ロシアン・ドールズ』の劇中、(おバカなサブキャラの)イギリス青年がロシアの女性バレリーナと結婚するエピソードがあり、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で撮影が行われる。婚約者の女性バレリーナは『白鳥の湖』のバックを彩るダンサーたちの1人で、彼女の踊りの場面は、バカ転じて純愛となるサブエピソードを象徴する美しいシーンとして印象に刻まれる。
以来、クラピッシュはバレエに急接近する。パリのオペラ座の有名なエトワールだったオーレリ・デュポンの全盛期の姿を『オーレリ・デュポン 輝ける一瞬に』(2010)というドキュメンタリー作品に刻印し、その後に『パリ・オペラ座 オーレリ・デュポン引退公演『マノン』』(2015)というTV用の作品も手掛けている。パリのオペラ座から定期的に撮影を依頼されるようになったクラピッシュは、オペラ座に最も近い映画監督のひとりとなった。
そして、長らくダンスのフィクションを撮るべきだと思い続けたクラピッシュがついに完成させたのが、『ダンサー イン Paris』である。
『ダンサー イン Paris』の魅力

Photo : EMMANUELLE JACOBSON-ROQUES
クラピッシュがこだわり続けているのが、「家族」「青春・若者(とその悩み)」であると前述したが、そこにもうひとつの関心事である「ダンス」が見事な形で加わったのが、『ダンサー イン Paris』だ。
オペラ座の有望な若手ダンサーであるエリーゼが、自分のソロの演技の前に恋人の浮気を知ってしまい、動揺を隠しながら見事な踊りを披露するものの、ついにジャンプの着地の際に足首を痛めてしまう。ダンサー生命の危機に直面し、しばらくクラシック・バレエから距離を置く。やがて、コンテンポラリー・ダンスの世界と出会うことで、エリーゼの魂は静かに回復していく…。
まず、冒頭、15分近くに及ぶバレエダンスのシーンが圧巻にして美しい。本作は、「踊れる俳優」を起用せず、「演技できるダンサー」を配役することが当初から想定され、それはオペラ座に通っていたクラピッシュにとっては必然な流れであったのだろう。エリーゼに扮するマリオン・バルボーはオペラ座所属のバリバリの現役ダンサーであり、当然ながら踊りの迫力とリアリティーは並みのバレエ映画の比ではない。
そして、クラシック・バレエに加え、コンテンポラリー・ダンスもじっくりと魅せてくれることが本作の特徴だ。「クラシック・バレエは空を目指すのに対し、コンテンポラリーは地に向かう」というセリフに深く肯きながら、迫力の群舞に参加しているような気分になる。

Photo : EMMANUELLE JACOBSON-ROQUES
そして、本作でほとほと感心するのは、ダンスの魅力をしっかりと見せながら、フィクションを形成するドラマのあり方の絶妙な塩梅だ。競争の激しい(であろうと想像してしまう)ダンサーの世界のネガティブなクリシェに関心を示さず、怪我に伴うダークサイドを過剰に深刻化せず、仲間の大切さを讃え、ユーモアを忘れず、ポジティブな明るさで貫かれる世界観は、まさにクラピッシュの面目躍如だ。
キャリアの危機に直面し、恋人を失い、まだ若い主人公は道に迷う。典型的な青春の挫折の姿だ。そして、決して不仲ではないがどうにも距離がある父親との関係にも悩む。「若さ」と「家族」にこだわるクラピッシュの世界である。物語は極めてシンプルなのだが、無駄が削ぎ落され、これ以上でもこれ以下でも駄目というくらい、ダンス映画の中にぴったりと洗練された結晶のようにはまっている。
それもそのはずで、クラピッシュのインタビューを読むと、古今の数十の有名ミュージカル映画を研究し、それらの作品におけるダンスと物語の時間の比率を計算してもらい、その比率を適用したという。クラピッシュ映画の心地よさが、単なるセンスの問題ではないことが分かる、驚くべきコメントではないだろうか。
本職がダンサーであるマリオン・バルボーは、本作が初演技とは信じられないほどナチュラルな姿を見せ、観客の心を奪う(この1本でセザール賞の最優秀新人女優部門にノミネートされた)。中でも、父親役でフランス屈指の名優のひとりであるドゥニ・ポダリデス相手にこれほど自然に振る舞えるとは、やはり普段の舞台で鍛えた度胸はただならないものがあるのだろうと感嘆せざるを得ない。

Photo : EMMANUELLE JACOBSON-ROQUES
主人公が一時的に身を寄せるアーティスト・レジデンスにて、そこに集まる個性的な面々が賑やかに過ごす場面があるが、それは『スパニッシュ・アパートメント』以来、クラピッシュが好んで描く「多国籍でわちゃわちゃした青春」の再現だ。恋の勘違いから爆笑を誘発する素晴らしいサブキャラの存在も嬉しい。本当に暖かく、心から気持ちよくなれるクラピッシュの新たな秀作の1本である。
(ちなみに、本作原題は『En Corps』というフランス語で、「身体において」というような抽象的な意味合いであり、ダンス全般と身体との関係を暗示している。とはいえ、読みは舞台の「アンコール(Encore)」と同じ発音であり、つまりはちょっとした言葉遊びなのだ。これはなかなか邦題には反映しにくい。)
アップデートされた驚きのグザヴィエ・サーガ
2010年代後半のクラピッシュは、ダンス映画の傍ら、『おかえり、ブルゴーニュへ』(2017)において、フランス東部でワイン造りに従事する兄妹たちの物語を通じて家族の繋がりを確かめたり、『パリのどこかで、あなたと』(2019)でパリに戻り、愛を叫ぶ2人の若い男女のすれ違う姿を描いたり、異なるアプローチで家族と青春の主題を描き続け、精力的に作品を発表していく。
それでは、前述した「2010年代の危機」とは、いかに折り合いをつけたのだろうか?家族と青春とダンスに集中し、社会的イシューからはデタッチしたのだろうか?
まったく、そうではなかった。なんと、『スパニッシュ・アパートメント』に始まるグザヴィエの物語を、10年ぶりに再開したのである。
TVドラマとして製作された『ギリシャ・サラダ』は、8つのエピソードからなるシーズン1が、2023年に配信された。『スパニッシュ・アパートメント』(=スペイン)、『ロシアン・ドールズ』(=ロシア)、『ニューヨークの巴里夫(パリジャン)』(=英題は『Chinese Puzzle』でつまり中国)に次ぎ、今度はギリシャを題名に掲げている。そして、物語の舞台はアテネである。
『ギリシャ・サラダ』の主人公は、グザヴィエのふたりの子ども、長男のトムと妹のミア。
祖父が亡くなり、トムとミアにアテネの建物を遺したことが分かる。ニューヨークに住むトムは起業を目指しており、建物売却が立ち上げ資金になると喜ぶ。しかし妹のミアと共同で相続したため、売却には妹の同意が必要になる。たまたまミアはアテネに留学中であり、連絡の取れない彼女に相続の話を伝えるため、そして建物の状態を確認するため、トムはアテネを目指す。まさに、父グザヴィエがかつてバルセロナに旅立ったように、息子トムもニューヨークから、アテネへと向かうのだ。
ここからの展開が、実に絶妙だ。
アテネに着いたトムは、相続した建物を訪れるが、そこは廃墟に近いおんぼろビルだった。しかし最上階だけは住居として機能しており、人種やジェンダーも多様な若い留学生たちがルームシェアをしている。トムは、建物のオーナーであることを言い出せないまま、素敵な若者たちの仲間入りをする魅力に抗えず、しばし一緒に住むことになる。当然、早々に建物を売るつもりなのだとは言い出せない。
一方、再会した妹のミアは、大学には通わず難民支援のNPO団体を手伝っていた。ギリシャに押し寄せる難民を一時的に保護し、少しでも生活を安定させるべく支援している。しかし、難民を宿泊させる場所には限りがあり、NPO事務所は極右グループから嫌がらせを受けている。いよいよ難民たちを移動させる必要が発生し、ミアは相続したビルの廃墟部分を新事務所に使おうと考え、トムに無断で移動を開始する。当然、兄妹の利害は完全に衝突する…。
トムはかつて父のグザヴィエがバルセロナで体験した「スパニッシュ・アパートメント」状態を、アテネで追体験することになる。その「楽しいわちゃわちゃ」は健在である。しかし、ヨーロッパはいかに変わったことか。
ギリシャは2010年初頭の財政危機でボロボロになり、以来再建を果たしたものの、街にはまだ廃墟が目立つ。難民がヨーロッパへの入り口として最初に目指す国のひとつであり、難民問題の最前線でもある。トムはブルジョワ世界を代表しながら現実に直面し、ミアはブルジョワの出自を隠して社会運動に取り組むが、自らに矛盾を抱えてしまう。牧歌的に「スパニッシュ・アパートメント」を楽しめたグザヴィエの時代とは、何から何まで変わってしまった。
この現実世界の推移を描くために、(高名なフランスの監督を父に持つ)妻のローラ・ドワイヨンの脚本協力を得ながら『スパニッシュ・アパートメント』シリーズを改めて再開し、過去作との比較で楽しませ(そう、もちろんクラピッシュ作品なのでとても楽しく、昔からのファンのための「神回」も用意されている)、家族と青春という永遠のテーマから逸れることなく、格差や難民やジェンダーのイシューをエンターテイメントの形で語るクラピッシュは、現代の作家として自らのアップデートに果敢に挑んでいる。その手腕は、あまりに鮮やかである。
おわりに
『ダンサー イン Paris』の紹介をしようと思ったら、なんとも長い話になってしまった。しかし、全てが繋がっており、優れた監督のキャリアを見ていくと、どうしても筆が止まらなくなってしまう。
是非、『ダンサー イン Paris』を劇場で楽しんでもらって、そしてグザヴィエ・サーガを配信で体験してもらいたい。時代の動きが、手に取るように見えてくるはずだから。
【参考(2023年8月現在)】
- 『猫は行方不明』『家族の気分』『エージェント物語』『パリ・オペラ座 オーレリ・デュポン引退公演「マノン」』:現在は配信なし
- 『スパニッシュ・アパートメント』:Amazon Primeにて配信中
- 『ロシアン・ドールズ』『ニューヨークの巴里夫(パリジャン)』『PARIS(パリ)』『オーレリ・デュポン 輝ける一瞬に』『パリのどこかで、あなたと』:U-NEXTにて配信中
- 『ギリシャ・サラダ』Season1:Amazon Primeにて配信中
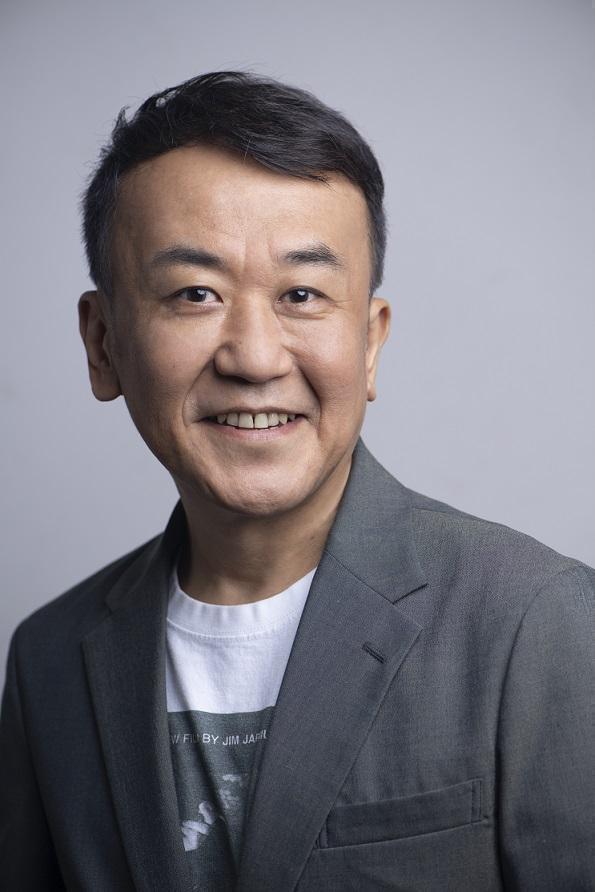
矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。東京国際映画祭に19年間在籍し、「日本映画・ある視点」、「日本映画スプラッシュ」、「ワールドフォーカス」、および「コンペティション」部門などのプログラミング・ディレクターを務めた。2022年3月にはウクライナ映画人支援上映会を企画するなど、現在はフリーランスとして活動中。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
