
© Paul Smith
個人差はあるだろうが、現代を生きるにおいて「正しさ」、いわゆるポリティカル・コレクトネス(以下、PC)を全く意識しないという人はいないだろう。ソーシャル・メディアで発信することが日常となり、「社会的に間違っていないこと」にいかなるスタンスを取るかによって、炎上のリスクが測定される。
よりよい社会を希求するPCは、原理としては好ましいことであるに違いない。しかし、常に正しい判断と選択をすることは簡単ではない。どこかで地雷を踏んでしまうかもしれないという不安がつきまとう。良い方向を目指そうとしているのに、どうして心理的には必ずしも楽しい気持ちばかりでないのだろうか。マジョリティ側にいる人間の心を変えるには、どうしてかくも大きな努力が必要なのだろうか。
常に矛盾と対峙する現代人の心を描き、若くして巨匠の域に達しようとしている映画監督がいる。スウェーデンのリューベン・オストルンド監督だ。
克服すべき偏見に直面したマジョリティ側の人間の心理に生じるひずみや、そのひずみがもたらす影響を、オストルンド監督は冷徹さとアイロニーを込めて描ききる。しかも、彼の作品はアート系映画の愛好家の枠にとどまることなく、強烈なブラックユーモアとシャープな映像によって、より広い観客層に届くスケールを備えている。その証しとして、カンヌ映画祭において目下2作連続で最高賞(パルムドール)を受賞中であり、最新作は2022年の米アカデミー賞にもノミネートされている。
「こんな状況に自分が置かれたどうするだろうか」と、オストルンド作品は見る人を必ず不安に気持ちにさせる。見るたびに胸の中をかき回されるようで不愉快なのだが、自分の心を見透かされたようでもあり、どうしようもなく面白い。現代的に「正しい」行動と思考のあり方とは何か。オストルンドは観客個人に向けて質問を投げかけ続ける。答えは描かれない。答えは我々が持っているはずだ。さて、どんな映画を作っているのか。
『Happy Sweden』
1974年生のオストルンド監督は、ドキュメンタリー映像を制作した後に改めて映画を学び、2001年にスウェーデンのヨーテボリの映画学校を修了している。ほんの20年前ではないかと驚かされるが、オストルンドはそこからトップスピードで世界の映画界を駆け抜けていく。
2004年に長編第1作『Gittarrmongot』を監督し、早くもモスクワ映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞。続く2008年の2作目『Happy Sweden』はカンヌ映画祭「ある視点」部門に出品され、本格的に世界の注目を集め始める(同作はもともと『Involuntary』という英題があり、『インボランタリー』として東京のスウェーデン映画祭で上映実績があるが、以下『Happy Sweden』とする)。

個人が心理的に追い込まれる絶妙なシチュエーションを設定する才能が、オストルンド監督をトップ監督に押し上げていくが、『Happy Sweden』では集団の力が個人の立場を揺るがしてしまうケースを想定する形で、監督の才気が発揮されている。ここでは5つのシチュエーションが並行して語られていく。
1つ目の舞台は小学校で、暴れる問題児を力で抑えつけた男性教員の行為を問題視した女性教員が、逆に教師間で孤立してしまう。2つ目は、ローティーンの少女2人が大人びた写真を撮り、酒を飲んでトラブルに巻き込まれそうになる。3つ目は、長距離バスの中、トイレの備品を壊した客に怒ったドライバーが、犯人が申し出るまでバスを動かさないと宣言し、心当たりのある中年女性客は自分が俳優で有名人であるがゆえに、知らんふりを決める。4つ目は、自然の中で飲み会キャンプを楽しんでいる男性集団内で、冗談のはずだった性的嫌がらせが度を越してしまう。5つ目は、白人富裕層の夕食会の席で、主催者の初老の男性が庭で行った花火が不発であるのを確認しようとすると、突然吹き出した花火に顔を直撃されて片目を負傷するが、それでも男性は夕食会の継続を選択し医者に行くことを拒む。

集団の中で生きざるを得ない個人に求められるモラルとは何か。集団の中でいかに個人を押し通せるか。集団を優先させるべきケース、個人の価値観を優先させるべきケース、集団を優先させる必要のないケース、個人の価値観を優先させるべきだが、そこに犠牲が伴ってしまうケース、など、オストルンド監督は身近に起こり得る様々なパターンを並べ、個としての生き方の「正しさ」を問いかけてくる。
群集心理の影響を授業で教える女性教員は、職員室で自らの正義を通そうとするが、「世渡り」にとっては好ましくない結果に転んでしまう。ホモソーシャルな集団の中で行われる性的冗談の受容に悩む青年は、それでも恋人の女性に男性中心主義的な発言をしている自分に気が付かない。バスの中の有名人女性客は、自分のせいで乗客全員が足止めをくらっているのに、寝たふりを続ける。そして、大けがをした男性は、どうして無理をして、たかが夕食会の無事の開催を優先してしまうのか…。
固定カメラの長廻しを多用し、緻密に計算された人物の動きを捉える演出が冴える。長廻しは、映画的に映えるし、経済的でもあるので(準備は大変だが編集の負担は減る)、キャリア初期の映画作家には映画祭でアピールするのに有効な手段だ。この時期のオストルンド監督は、内容の鋭さとスタイリッシュな映像演出の双方で強い印象を残している。オストルンドはその後も長廻しのテクニックを駆使しつつ、アート調の作りを超え、よりスケールの大きい映画作りを志向していく。
『プレイ』
そして、オストルンド監督がその名声を確たるものとしたのが、見る者の「良心」を震え上がらせる傑作の『プレイ』(11)である。カンヌ映画祭「ある視点」部門に出品され、そこで見た僕は驚愕し、当時作品選定を担当していた東京国際映画祭への招聘を即決したのだった。それがオストルンドの日本における初紹介となったはずで、『プレイ』は東京国際映画祭で見事監督賞を受賞した。

『プレイ』は、スウェーデンで起きた実際の事件から着想を得ている。黒人の少年集団がショッピングモールで「知能犯的かつあげ強盗」を行った事件である。黒人少年たちは白人少年に近づき、携帯電話を見せてみろと言う。そしてやむを得ず携帯を見せると、黒人少年は「これは自分の知り合いの盗まれた携帯であり、その証拠にここに傷が付いている」などと言って携帯を取り上げてしまう。白人少年が返してくれと頼むと、ならばその知り合いに会いに行こうとなり、白人少年たちはやむなく黒人少年たちについていかざるを得なくなる。
巨大ショッピングモールのフロアの片隅に黒人少年集団が控え、フロアの中央部に数名の白人少年がやってきて、かつあげの餌食となるまでを、望遠カメラのワンショットで見せる導入部が素晴らしい。やがて次の獲物になる少年たちが登場し、彼らが黒人少年たちに狙われてしまう経緯がじっくりと描かれていく。

『プレイ』には大きく分けて2つの心理戦がある。1つは、黒人少年たちが仕掛ける「良い警官、悪い警官」のテクニックである。黒人少年の1人が被害者を恫喝すると、別の1人が「そんな言い方はやめろよ、彼らもかわいそうじゃないか」と言って、被害者の信頼を得ようとする。もちろんその親切さは見せかけに過ぎず、白人少年たちはひどい目に遭っていくが、しかし極めて効果的であることは明らかだ。そして、こんなに幼い少年たちがこのテクニックを使いこなしていることに震撼する。
もう1つの心理戦とは、人種差別意識に他ならない。モール内のスポーツショップで騒ぐ黒人少年たちを、白人店員はなかなか注意出来ない。注意をされる黒人少年たちには、「自分たちが黒人だからそういう注意をするのか」と言い返す切り札を持っている。そして彼らの悪さを知っている白人成人が黒人少年を押さえていると、何も知らない通行人がその大人を差別主義者として通報しようとする。黒人少年たちへの偏見を助長しかねない映画のリスク自体を含め、差別意識の副作用が幾重にも捻じれながら描写され、気が遠くなるほどに優れた脚本である。
もちろん、白人中流層と黒人低所得層との生活レベルの乖離は、現実のものとして描かれる。それがゆえに、問題の根深さがさらに強調されるであろうし、大人たちの世界の縮図が子どもたちに反映されていると見て取れる。しかし、これは社会問題を客観的に学習する作品ではなく、日常の中で観客が体験しうるケーススタディでもある。「自分ならどう対応するだろう?」。
このあたりから、オストルンド監督作品の特徴に「過剰性」が加わる。映画が触れたい主題を「ほのめかして」余白を残す監督がいる一方で、オストルンドは「ほのめかす」ことを必ずしもよしとせず、とことん描写を続ける。『プレイ』で黒人少年たちに連れ回される白人少年たちの辛い道程には、終わりが来ないかのごときである。「ほのめかし」で終わるのではなく、観客の脳裏に問題意識を刻印するための過剰性であろうか。この過剰性は、作品を追うごとに増していく。
『フレンチアルプスで起きたこと』

日本で初めて劇場公開を果たした作品が、格段にスケールアップした次作の『フレンチアルプスで起きたこと』(14)である。本作もカンヌ「ある視点」部門に出品され、監督はメインのコンペティション部門での選出でないことに落胆したと伝えられたものの、「ある視点」部門の審査員賞を受賞し、そしてまさしく世界中で上映される話題作となった。
この作品のオープニングとなる長廻しのシーンは、映画史に残りそうな、長く語り継がれるであろう素晴らしいシーンだ。予告編にも使われた、こんなシーンである:
若い夫婦と幼い娘と息子からなる4人家族が、スキー旅行でアルプス山中のリゾートホテルを訪れている。テラスのレストランの席につき、食事を始めようとする。山では、計画的に雪を崩すことで本格的な雪崩を防ぐ措置が取られており、そのための号砲が鳴らされる。小さい雪崩が起き、テラスの客は写真を撮って楽しんでいたものの、やがてその雪崩がテラスに向かってくる。一家の夫は計画的なものだから安心しろと言うが、いざテラスが雪崩の雪煙で包まれると、夫は席を離れて逃げ出してしまう。父を呼んで泣き叫ぶ子どもを、母親がしっかりと抱きしめて守る。やがて雪煙が去り、あたりが明るさを取り戻し、テラスは無事だったことが分かる。すると父親が戻ってきて、大丈夫だったかいと声をかけ、何事も無かったかのように席に座る…。
以上が、ワンショットで描かれる。ド迫力である。そして、1人の人物が一瞬にして家族の信頼を決定的に失ってしまうという、この上なく残酷で悲劇的なシーンである。この場面を冒頭に置き、映画はスキー場で残りの数日間を過ごす一家の危機を描いていく。
表向きには平静を装う家族には、呆然とした空気が漂う。2人の子どもも、ぐったりとしてしまう。妻が出来事に言及しようとすると、夫は自分の認識とは違うととぼける。そこから絶望的な心理戦が始まる。
ここでも、とっさの事態に人は正しい行動を取れるのだろうかという、誰の身近にも起こり得る出来事が設定されている。観客は夫の行動を非難すると同時に、憐れんで同情するだろう。そして、自分ならどうできただろうかと、必ず自問する。「気まずさの帝王」のオストルンド監督の術中にはまるのだ。
不倫や、離婚や、死別などによって家族が危機に陥る物語は無数に存在するが、本作のような形で家族が崩壊しかける作品はほとんど例を見ない。果たして再建はありえるだろうか。極めてユニークな家族映画である。
そして、家族映画としての側面以上に、この作品には核となる大きな問いかけがある。それは、「男らしさ/マスキュリニティ」の視点である。一見、夫はとてもみっともない行為をしたように思える。彼自身も、やがてそれを認め、苦しむことになる。しかし、それほどダメなことだったのだろうか?結婚している男性は「男として」「夫として」「父として」家族を守るものだという役割の呪縛に囚われていないだろうか?本能的に逃げてはいけなかったのだろうか?子どもを守る本能が発揮されなかったことはどこまで責められるものなのだろうか?
この問いかけに気付かせるためなのか、夫の悩みは映画を通じて「過剰に」描かれていくが、ジェンダー映画の変奏として本作に接すると、「ダメ男」なるものが現在いかに定義しうるか(しえないか)、さらには家父長制への疑いもオストルンド監督が視界に入れていることが見えてくる。
『ザ・スクエア 思いやりの領域』
2017年に発表した『ザ・スクエア 思いやりの聖域』で、オストルンド監督は念願のカンヌ映画祭コンペティション部門入りを果たす。そして、初のコンペで、見事に最高賞のパルムドールを受賞するのである。
今作でオストルンド監督が舞台として選んだのは、現代アートの世界。抽象的なアート作品に、巨額の金が動く。門外漢には理解が及ばない作品に、理解が及ばない値が付くその世界は、どこかスノビズムや胡散臭さが付きまとう。いや、これも偏見であることは間違いないのだが、富裕層が中心となるその世界を、オストルンドは最大限に活用していく。

主人公は、ストックホルムにある現代美術館のチーフ・キュレーターの男性。自身は富豪で無ければアーティストでも無く、現代アートの中枢にいる人間としては可能な限り観客に近い立場の人物であるという点が上手い。とはいえ、一般水準以上の生活を送り、権力を有している白人男性という点で強者ではあり、彼の公私にわたるトラブルへの対応を通じ、強者のメンタリティーの脆弱性が描かれていく。
美術館の新たな展示物は、地面に引かれた正方形の空間=「ザ・スクエア」と呼ばれるコンセプチュアル・アート作品で、その「スクエア」の中では誰もが平等であり、そこは他者に優しくなる聖域なのだというメッセージが込められている。
崇高な理念を掲げるアート作品に対し、人はどれだけ真摯に向き合えるであろうか。富裕層はそこに懺悔の念を注ぎ、心を洗うこともあるだろう。しかし街にはホームレスや物乞いが存在し、四角いアートよりは、小銭を欲している。
主人公は、ホームレスに小銭を渡しながら、新企画の成功にも尽力しようとする。離婚した妻との間の2人の娘に対しても、良き父親であろうと努力する。しかし、盗まれたスマホの回収に良からぬ手段を用いてしまい、意に反して貧困層を刺激してしまうし、対等な立場のつもりでセックスをした女性から不本意な指摘をされてしまうなど、少しずつ歯車が狂っていく。

主題や問いかけの対象が明確だったこれまでの作品に比べると、本作は多少入り組んでいて、モラル、偏見、虚勢、偽善、独善、ハラスメント、格差社会など、とても絞り切れないほどの要素がぶちこまれている。それはまさに現代アートの抽象性に近いかもしれない。物語自体は非常に分かりやすいが、問いかけは幾層にも巡らされている。
アートの世界に関わる白人富裕層の存在は戯画化されているものの、それは資本主義国において(物乞いでない立場で)生きる我々をも象徴しているはずだ。我々の良心はどこまで誠実なものでありうるか、社会正義と偽善の境はどこにあるか。そして、1度の判断の誤りが、いかにとりかえしのつかない結果をもたらしうるか。
劇中の主人公は、コンセプチュアル・アート作品の「ザ・スクエア」を丁寧に扱おうとするほど、道をずれていってしまう。この行為は、PCに忠実であろうとしているのに地雷を踏んでしまう現実の人々に似てはいないだろうか。ひょっとすると、「ザ・スクエア」とは、PCのメタファーなのかもしれない。
さらに、本作は現代アートを扱っていることもあり、表現の自由を巡るエピソードが終盤に配されている点も重要だ。展示を巡るトラブルと謝罪、そしてそこに表現の自由を巡る議論が付随するとなると、日本でも数年前の美術展で起きた出来事が記憶に新しく、まさに現実と地続きの内容であることが実感できる。
PCのごった煮とも呼べる『ザ・スクエア』は、現在の社会をあらゆる意味で象徴し、堂々とパルムドールに輝いたのだった。
写真:(C)2017 Plattform Prodtion AB / Societe Parisienne de Production / Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS Blu-ray&DVD発売中(発売:トランスフォーマー/販売:ハピネット)
『逆転のトライアングル』
2022年、5年振りの新作『逆転のトライアングル』(2023年2月23日公開)を完成させたオストルンドがカンヌに戻って来る。そしてなんと、2作連続でパルムドールを受賞する。2作連続でパルムドールを受賞するのは、75回を数えるカンヌの歴史の中で、デンマークのビレ・アウグストと、オーストリアのミヒャエル・ハネケに次ぐ、3人目の快挙となった。
新作でオストルンドが俎上に乗せたのは、ずばり格差社会である。貧富の差、階級社会、と言い換えてもいい。これまでの作品でも何らかの形で扱ってきた主題であるが、今作では真正面から格差社会を取り上げ、ブラックな笑いを散りばめながら階級社会の醜悪さを曝け出す。

冒頭は、モード界が舞台となる。高級レストランで、若い男女のカップルが食事をしている。女性は一流モデルとして成功し、インフルエンサーとしても稼いでいるが、男性はモデルとして有名ブランドの仕事をしたものの、ピークを過ぎたと見なされている。食事が終わって勘定の段になると、男性は当然のように自分に払わせようとする女性に腹を立てる。女性は無意識であったと言い、机の上に勘定書が置いてあることにも気づかなかったととぼける。

これは『プレイ』において黒人少年たちが弱者であることを逆手に取って悪さをしようとしていた場面を連想させ(もちろん、弱者であることを武器に強者に抵抗しているとも解釈できる)、女性であることを意識的に利用して男性に払わせようとしている状況であるが、ここでは女性の方が稼ぎが多いことや、「食事は男がおごるもの」という「男らしさ」幻想の要素が加わっているために、「ゲーム/プレイ」はより複雑化している。
1歩間違えれば弱者が悪者に見えてしまいかねないギリギリのラインを攻め、パワー・バランスをねじって、ねじりまくるオストルンドの状況設定の上手さがいかんなく発揮されている絶妙な場面である。
このエピソードを導入とし、本作は怒涛の展開へと突入していく。一応仲直りをしたらしいセレブ男女のカップルは豪華クルーズ船の旅に出る。船はIT長者や、肥料事業で当てたロシアの富豪や、兵器売買で財を成したイギリスの老夫婦など、富裕層で溢れている。
客である富裕層が船内カーストの最上位に位置し、彼らを接遇する白人クルーが第2カースト、そして階下で清掃などを担当する非白人の労働者たちが最下層に位置するという構図が船内に出来上がっている。やがて、この階級制度が根底から揺らいでしまう事態が訪れる。
前作『ザ・スクエア 思いやりの聖域』は、抽象的な現代アートになぞらえるかのように、洗練された都会の生活の中の矛盾を抽象的な形で指摘したのだったが、新作『逆転のトライアングル』のメッセージ描写は、超ストレートである。細かいメタファーなどは無用とばかりに、階級社会への揶揄を真正面から描く。さらには階級闘争を志向した共産主義まで登場し、クルーズ船の酔いどれ船長にマルクス絡みのセリフを次々に吐かせるほどの念の入れようである。
もっとも、共産主義思想への知識が無くとも、本作の理解への妨げとは全くならない。物語はとても明解であり、オストルンドは執拗に描写を重ねるから、理解し損ねる心配はない。とある事態に直面した際の船上の描写はあまりにも「過剰」なのであるが、「過剰」はオストルンドの持ち味なのである。そこまで言わないと気が済まない性質なのだ。「ほのめかし」ではダメ―ジを与えられない。そこを承知で見てほしい。

第1部のモード界、第2部のクルーズ船、そして驚きの第3部は伏せておくとして、3つのパートで構成される痛快なエンターテイメントである『逆転のトライアングル』は、2作連続のカンヌパルムドール受賞に留まらず、アカデミー賞にもノミネートされた(作品賞、監督賞、脚本賞)。
支配階級を揶揄する作品が、スノッブなカンヌや米アカデミーで評価を受ける事態には常に皮肉がつきまとうものの、当然オストルンドは自覚的であろうし、自浄作用を信じながら、システムの内部から問題提起を続けてゆくだろう。なんといっても、いまや世界中が彼の投げかける質問に目と耳を傾けているのだから。
写真:『逆転のトライアングル』 2月23日(木・祝) TOHO シネマズ 日比谷 他 全国ロードショー
配給:ギャガ Fredrik Wenzel © Plattform Produktion
おわりに
フィルモグラフィー(※1)を振り返ると、作品ごとにスケールアップを続け、20年ほどの期間でカンヌと米アカデミーに足跡を残すに至ったリューベン・オストルンド監督の偉業に改めて驚かされる。
90年代に、人間の不都合な本音を曝け出すことで映画に新たなリアリズムをもたらしたデンマークの「ドグマ95」という映画の潮流が存在し、オストルンドはそこから大きな影響を受けていると思われる。さらには、スウェーデンにはイングマール・ベルイマンという大巨匠が存在し、そしてオストルンドにより大きい影響を与えた同じヨーテボリ出身のロイ・アンダーソンという鬼才もいる。さらには、不条理に近い人間の感情のあり方を冷徹に描いたオーストリアのミヒャエル・ハネケの名前も上げられるかもしれない。詳細な考察は今後に譲るとして、オストルンドは欧州/北欧の映画の伝統の流れを踏まえながら台頭してきたのであり、突然変異で誕生した天才ではない。
しかし、現代の社会が意識するべき問題の核心を掬い上げながら、アート性に拘泥することなく、エンターテイメントとしても成立する明解さとスケール感を備えることで世界中の観客にリーチしているという意味では、オストルンドの存在感は際立っている。
「正しく」生きるとはなんと難しいことか。その意味さえも見失いがちになってしまう現在、オストルンド作品の問いかけに答えを見つけようとする行為が、ひとつの指針となってくれるかもしれない。新作公開を機に、オストルンド体験をお勧めする次第である。
※1 用語:監督・俳優など、ある人間が携わった映画作品のリスト。 また、テーマ別に選び出した作品の概要を記したリスト。
<参考>
『Happy Sweden』:国内未公開、現在配信等も無し
『プレイ』:JAIHO(www.jaiho.jp)にて2023年2月22日~4月22日 配信
『フレンチアルプスで起きたこと』:Amazon Prime、U-Next等にて鑑賞可能/DVD発売中
『ザ・スクエア 思いやりの聖域』:Amazon Prime、U-Next等にて鑑賞可能
『逆転のトライアングル』:2023年2月23日劇場公開
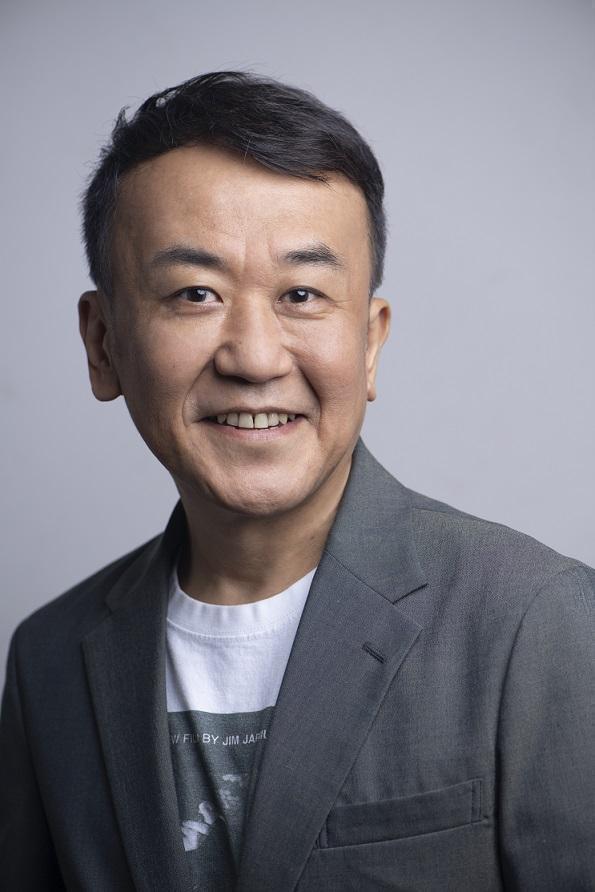
矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
(注)本コラムに記載された見解は各ライターの見解であり、BIGLOBEまたはその関連会社、「あしたメディア」の見解ではありません。
