
日本では実に多くの映画祭が開催されている。東京国際映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭のような大規模なものや、フランス映画祭やイタリア映画祭のように特定の国の映画を紹介するもの、そしてその他各種の小規模の特集上映まで入れると、毎週のようにさまざまな映画祭のニュースが飛び込んでくる。
そんな映画祭の情報が溢れるなか、カンヌ映画祭のいち部門である「監督週間」の作品が東京で上映されるという企画が2023年に初めて立ち上がる。12月8日にスタートする「カンヌ 監督週間 in Tokio」をここで紹介してみたい。

「監督週間」を見る意義
世界で最も重要な映画祭であるカンヌ映画祭の一部の作品がまとめて上映されることは、とても貴重だ。今回が日本で初めての試みである点に加え、ある程度の本数をまとめて見ることで、カンヌ映画祭の雰囲気を知ることができる。必ずしも自分の好みに合う作品ばかりでないかもしれないけれど、映画祭で映画を見るということは(宣伝の行き届いた劇場公開映画を見るのとは異なり)、未知の映画に触れるということだ。好みを超えたところで「カンヌ映画祭のラインアップってこんな感じなのか」と、一気にカンヌが近くなる。
さらに、カンヌの作品を現地の映画祭が開催された同じ年のうちに見ることで、映画の最前線の「いま」をタイムラグ無しで目撃できる。毎年5月のカンヌで上映される作品が商業公開されるとしても、大抵は翌年だ。『枯れ葉』(23/アキ・カウリスマキ監督/23年カンヌ上映を経て23年12月15日に日本公開)のような幸運な例外ももちろん存在するけれど、下手するとカンヌのプレミアから2年後に日本公開ということだってあり得る。良い映画は普遍性を備えているので、数年を経たところでその価値に変わりはないのだけれど、日本に住んでいると、世界の映画動向の「旬」から取り残される感は否めない。5月のカンヌ作品をある程度まとめてその年に見られることで、世界の映画の潮流がより身近に感じられるだろう。
今回上映される作品のうち、公開が決まっている(日本の配給会社がついている)のは2、3本に過ぎない。この特集の反応次第で今後公開が決まる作品があるかもしれないけれども、見られるのが今回限りという作品もあるかもしれない。そもそも海外の映画祭に出かけると、面白いと思った作品が日本では未公開のまま終わることは珍しくない。
もちろん、映画祭上映作が面白く思えない体験だって当たり前のようにある。公開されるか分からない、あるいは、自分が好きか嫌いか予想できない、という体験そのものが映画祭に行くということであって、つまり今回の「監督週間 in Tokio」はまさに海外映画祭訪問の疑似体験となるのだ。
そもそも「監督週間」とは何か
カンヌ映画祭は、主として次の部門で構成されている。
「コンペティション」「特別上映など」「ある視点」「監督週間」「批評家週間」「ACID」
このうち、最初の3部門が「公式上映部門」と総称されて、カンヌ映画祭の事務局が運営している。後半の3部門は、監督協会や批評家協会など、別の事務局が運営している。けれど、後者グループを含めて、カンヌ映画祭と呼ばれている。
「監督週間」は成り立ちがドラマティックだ。
それは、1968年のフランスの「五月革命」の影響でカンヌ映画祭が中止に追い込まれ、翌年に映画作家主導の部門があるべきだとの理念の元に始まったのが「監督週間」部門だからだ。このカンヌ映画祭の中止にはジャン=リュック・ゴダールとフランソワ・トリュフォーを中心にした「ヌーヴェルヴァーグ」と呼ばれる新しい映画の潮流に関わった面々が大いに寄与していて、中止事件は世界の映画史における熱い青春譚のようであり、その落し子のような存在が「監督週間」なのだ。
このような誕生背景を持つ「監督週間」なので、作家性の強い個性的な作品を選んでいる部門と言えるのだけれど、そもそもカンヌは全体的に作家主義なので、現在は「監督週間」の個性がその意味で際立っているわけではない。実際には、およそ4~5年ごとに変わるディレクターの方針や個性が色濃く反映されるラインアップで、今年からそのディレクターにジュリアン・レジという方が新たに就任している。カンヌ本番時にラインアップを見て感じたのは、ジャンルや監督の出身地の範囲が広がり、若手も増えたなというものだった。ジュリアン氏の方針が1年目にして早くも発揮されているという印象だ。今回の東京の上映に合わせてジュリアン氏は来日し、檀上でお話も伺えるので、実際にどのような考えで選定に取り組んでいるかご本人の口から語ってもらうことを楽しみにしたい。
そのジュリアン氏が「監督週間」のプログラムをアジアにも広めたいという意思を持っており、このたび日本のVIPO(映像産業振興機構)が組んで、上映企画を実現させたというのがことの次第だ。カンヌ時の「監督週間」で上映された19本の長編のうち、12本が今回東京で上映される。
僕は東京上映の作品選定にあたってアドバイスをしたり、ウェブやチラシ用の紹介文を書いたり、少しだけお手伝いしている。もとより、カンヌの作品を紹介できることだけでも嬉しい。残念ながら外国長編12本(短編と旧作含めると17 本)の全ては紹介できないので、お勧めを数本ピックアップしてみよう。
オープニング作品は迫力の『ゴールドマン裁判』
2023年のカンヌ本番時の「監督週間」でもオープニングを飾ったのが、フランスのセドリック・カーン監督による『The Goldman Case(ゴールドマン裁判)』 。

セドリック・カーンは官能的心理ドラマ『倦怠』(1998)や、硬質な犯罪実録映画『ロベルト・スッコ』(2001)で頭角を現した実力派の監督である一方で、『チャーリーとパパの飛行機』(2005)のようなファミリー映画も手掛ける幅の広さを備えた存在である。『ハッピー・バースデー 家族のいる時間』(2019)で混乱する家族の集まりを鮮やかに演出して健在ぶりを見せたが、4年振りに届いた新作『ゴールドマン裁判』は前作の家族のドラマからがらりと趣を変え、『ロベルト・スッコ』を想起させるような、実際の事件をベースにした裁判劇である。
事件の中心となるのが、ゴールドマンという中年男。彼は多数の強盗事件で起訴されており、本人も罪を認めている。しかし唯一、薬局における強盗殺人だけは、自分の仕業ではないと断固否定する。強盗はするが、絶対に殺人はしないと否定し、やがてその一件に焦点を当てた裁判が開かれる。殺人罪が加わるか否かで刑期が大幅に変わるため、ゴールドマンと検察側の衝突は激しさを増していく…。
舞台は70年代。裁判の記録映画を再現するかのようなスタイルが採用されている。スタンダード・サイズと呼ばれる狭い画面と、色調の彩度を押さえた映像が特徴的だ。ほとんどが裁判所内で展開し、徹底して裁判のみに映画は集中し、その集中力が並み外れた迫力へと繋がっていく。
当時のフランスの裁判制度では被告人が自由に発言できるようで(現在でも同じ制度なのかは未確認)、ゴールドマン氏はことあるごとに声を荒げて発言し、自身を弁護していく様が面白い。実際に弁護士を信用しておらず、自分の身は自分で守るというスタンスを貫くゴールドマンの強い姿勢が映画の中心になっていく。
判決の行方にも惹かれるが、裁判を取り巻く環境も時代の背景を色濃く伝えて興味深い。ゴールドマン氏は左翼活動家たちから支持されており、裁判ではさながらコンサートのような歓声や応援が飛び交う。また、ゴールドマン氏がユダヤ系であることへの差別があったかどうか、それが警察の捜査にいかなる影響を与えたか、その捜査の正当性はいかほどであったか。様々な争点を含んで進んでいく裁判を捉えるリアリズムに圧倒される。

役者陣はことごとく達者で、裁判劇に特有の説得力ある弁論が続いていくなか、やはり見どころはゴールドマン氏を演じる主演のアリエ・ワルトアルテだろう。『彼女のいない部屋』(2021)で出番が少ないながらも非常に強い印象を残した夫役に続き、主役を張る本作では正義を求める犯罪者という、毀誉褒貶の激しく極めてアクの強い人物像を見事な形で見せてくれる。
オープニングにふさわしい迫力という格を備えた作品が『ゴールドマン裁判』なのである。
トランプ・アメリカ時代の不思議の国のアリス『スイート・イースト』
シャープなセンス満載な作品が、アメリカ映画の『The Sweet East(スイート・イースト)』 だ。
修学旅行でワシントンDCを訪れている高校生のリリアンが体験する不思議な物語。学生たちがカラオケで盛り上がっているところ、武装した男が店を襲い、リリアンは命からがらその場を逃げ出す。そこからリリアンの不思議な旅が始まり、アーティスト活動家集団に助けられたり、ネオナチ男の世話になったり、やがて自然に回帰したり、映画に出演することになったり…。
出来事がシームレスに連なり、様々な出会いを経ることや、ナンセンスな展開も特徴的であることから、現代の「不思議の国のアリス」という形容が最もふさわしい。カンヌ映画祭時のHPは「トランプ時代のアメリカに跋扈する様々なタイプの過激主義者たち」という表現で登場人物を紹介していたが、確かに現代のアメリカのある側面を戯画的に切り取る作品であり、どこかアメリカン・ドリームなるものの残滓を見てとることもできる。しかしそういう解釈はあとから考えればよくて、本編は美しくポップでギャグに満ちたとても楽しい作品なのだ!

映像はクールでラフなタッチでまさに現代的。それもそのはず、本作が長編監督1作目となるショーン・プライス・ウィリアムスは、アメリカの底辺でもがく若者の姿をビビッドに捉えた『神さまなんかくそくらえ』(2014/サフディー兄弟監督)の撮影監督であり、その後もサフディー兄弟との共同作業を重ね、まさに現代のアメリカン・インディペンデントの最前線に身を置いてきた存在だ。
そして最大の見どころは、リリアン役のタリア・ライダーの魅力であると断言してもいいはず。『17歳の瞳に映る世界』(2020/エリザ・ヒットマン監督)で鮮烈な印象を残し、本作が初の単独主演となるはずだが、予測不能な展開に身をゆだね、調子に乗ったり反省したりのリリアンの心情を実に軽やかに体現し、目を奪われずにいられない。
賛否や好き嫌いが分かれること必至のアメリカ作品
『The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed(フィーリング・ザット・ザ・タイム・フォー・ドゥーイング・サムシング・ハズ・パスト)』という長いタイトルを持つアメリカの作品。訳せば、「何かを成すという時期は過ぎてしまったという気持ち」だろうか。もう若くないと自覚した時に感じる、あの感じ。なんともいえない、いいタイトル。
そして、映画祭に通う時に出会いたいのが、まさにこういう作品だ。低予算、インディペンデント、怖いものなしの監督1作目、アイディア満載で挑発的、好き嫌いは確実に分かれる、従って日本公開は極めて危うい、という要素を全て備えているのが、本作だ。
主人公は、ニューヨークで暮らす34歳のアン。昼は会社でパソコンに向かう単調な仕事をこなし、時おりヨガに通い、祖父母の家にはひんぱんに顔を出す。そして夜は、特定の男性と、あるいは不特定の男性たちと、BD(ボンデージ・ディシプリン)SMのプレイを楽しむ。
ソフトSMがフィーチャーされているために最初は少し面食らうものの、ここにあるのはあまりにありふれた日常の時間であり、都会でぼんやりと居場所を失った感覚を抱える後期若齢者の空虚な心理そのものだ。ジョアンナ・アーナウ監督は、自らアンを演じ、冒頭のシーンから裸体をあっけらかんと晒しているが、それはもはやパフォーマンス・アートの域であり、セックスプレイでありながら肉体の実存に迫ろうとするかのような所作は、ほとんど哲学的ですらある。

映画の作りとしては、2~3分の場面がワンシーン・ワンショットと言われる手法で次々と続いていく。必ずしも関連しないシーンが連なるモザイク画と言えばいいだろうか。あるいは、スケッチ集。これは、ハマる人はハマるし、飽きてしまう人も少なからずいるだろう。しかしこの大胆さ、あけっぴろげさ、自虐を含むダークなユーモア、コミュニケーションへの飢餓、そして、孤独と空虚に襲われそうな都会人の心を描く深淵さに、共感を示す人はとても多いと思う。
大いに賛否が分かれる作品だけれども、僕は大好きというか、もう偏愛の域。
ロシア映画の受け止め方を問う『グレース』
22年2月に本格化したウクライナ戦争以降、主要な映画祭がロシア映画をラインアップに含めない動きが通例化している。逆にウクライナ映画は22年に多く取り上げられたが、いよいよ製作本数が減った23年では各映画祭におけるウクライナ映画の紹介も減ってしまった。ロシア映画は限定的に上映されており、ロシア政府の製作への関与の度合いを上映側が勘案して判断していると考えられる。映画は映画として評価したいという綺麗ごとでは済まされない、繊細な問題だ。
ともかくも、カンヌ「監督週間」はロシア映画の『Grace(グレース)』を選んだ。ロシア映画がプログラムされていることにどう反応するべきかは、個々の判断に任されるものの、観客も議論があることを認識し、全くの無意識で臨むべきではないだろう。
『グレース』のイリヤ・ポヴォロトスキ監督は
「私はウクライナ侵攻戦争に反対です。暴力の行使にも、自国の政権の方針にも反対です」
と明言している。
そして
「ロシア内で孤立し、諸外国からも非難されるという2重の罰は、現在の惨状の結果として、避けられないものです。それでも、文化には再生と繁栄に向かうマジカルな力があると信じています」
と続け、ロシアのリベラルなアーティストの心情を代弁する。(※1)

以上に言及した上で、『グレース』の美しさと重要さに触れておきたい。
ロシアの南西部と思われる辺境地を旅する父と娘のドラマであり、これまでドキュメンタリーを手掛けてきたポヴォロトスキ監督らしく、山岳地帯から平原へと至る険しく荒涼とした景観がまず目を惹く。
ヴァンを運転する寡黙な父と、思春期の娘。2人は行き先で生活物資を調達しながら、ヴァンで生活を送る。特殊な環境で生きる娘が成長にむけて悩む姿を温かく見つめるドラマである。
ヴァンで移動する父の仕事がやがて明らかになり、そのサプライズは作品の大きな柱へとなっていく。さらに重要なのは、辺境地の旅を通じて多様な民族との交流が描かれることで、そこではロシア語だけでなく、ジョージア語やその他の言語も話されている。中央のモスクワの考えとは異なり、ここでは国境とは異なる次元で多様性が既に実在しているのであり、国境戦争に反対する監督の姿勢を読み取ることも出来る。

辺境地の景観の荘厳さと、父と娘の関係の得も言われぬ暖かさ、そして少女の通過儀礼を描く演出の鮮やかさを見るにつけ、本作の受け入れは重要だと思えてくる。繰り返すけれども、見る見ないの判断は個々に委ねられるとしても、本作に接するに際し、戦争が進行中であることを改めて想起することは、海外から隔絶されがちな日本に生きる身に求められる態度であるはずだ。
※1 引用: Le Monde「Cannes 2023: Russian filmmaker Ilya Povolotsky's journey of art and opposition」(2023年5月25日付)
https://www.lemonde.fr/en/culture/article/2023/05/25/cannes-2023-russian-filmmaker-ilya-povolotsky-journey-of-art-and-opposition_6027941_30.html?random=1694746565
カメルーン女性の奮闘を描く『マンバール・ピエレッテ』
映画祭の価値は未知の国の映画を発見するというところにもある。カメルーンの映画を見る機会は滅多にないのだが、『Mambar Pierrette(マンバール・ピエレッテ)』を紹介したい。
アフリカ大陸の中部に位置するカメルーンの、西部の都市ドゥアラが舞台。マンバールという名の女性が、仕立て屋を営んでいる。生活はとても苦しく、新学期を控えた子どもたちに必要な文具類を買うことがまだできていない。しかし、大雨で店が水浸しになり、それから様々な不運がマンバールを襲う。果たしてマンバールはサバイブできるだろうか…?という物語。
貧困地区の路地や、家屋や、人びと々の様子など、見知らぬ地の光景…見るもの全てが新しい。大雨でどこもかしこもこんなに浸水してしまうなんて、なんて大変なのだ!と驚かずにいられない。しかも、その水を外に掻き出す手段も全部手作業だ…。もう、画面の中に入って手伝いたくなる。

マンバールは腕のいい仕立て屋で、彼女が作る服のカラフルで大胆なデザインには人を幸せにする力が宿っているかのようだ。しかし彼女のアトリエは本当に小さな掘っ立て小屋であり、お客もちゃんとお金を払ってくれるとは限らない…。
マンバールのタフなキャラクターに支えられ、映画は明るく、力強い。この地においても、男性優位主義が社会を覆っている。その中で、マンバールは自立した存在としてロールモデルとなる。その姿を、ベルギーを拠点に活動する女性の監督、ロジーヌ・ムバカムが生き生きと描く。
逃したくない1本だ。

めちゃくちゃ愛らしい『リドル・オブ・ファイヤー(原題)』
カンヌ本番時に大いにバズっていたのがこの『Riddle of fire(リドル・オブ・ファイヤー)(原題)』だ。ちなみに、日本の映画祭で上映する作品について、しばしばタイトル内に(原題)と入っていることがあって、これは何だ?と思っている人がいると思うのだけど、これは何を隠そう、日本公開があることのサインなのだ。必ず入っているわけではないので、これが唯一のルールと思わないでほしいのだけど、日本の配給会社が権利を購入した作品を映画祭が(劇場公開前に)上映したいと希望したとき、そして(劇場公開時期がまだ先のために)劇場公開用タイトルをまだ配給会社が決めていない場合、もとのタイトルをカタカナにして、それに(原題)と加えて、これは原題をカタカナにしただけの仮のタイトルですよ、公開タイトルは違うかもしれませんよ、と暗に伝えているのである。なので、本作も、いつか劇場公開を期待していいということなのだけど、今年のカンヌの話題作を今年のうちに見ておくというのも貴重だ、というのは上に書いたとおり。
閑話休題。もう徹頭徹尾、キュートな作品なのだ。キュートで、キッチュ(死語かな?意味は検索してみて下さい)で、カンヌが付けたキャッチフレーズは「『グーニーズ』meetsネオ・ウェスタン」!
『グーニーズ』というのは1985年に大ヒットしたアメリカ映画のことで、宝物を探す子どもたちが大活躍するエキサイティングでハッピーな作品。80年代を代表するキッズ映画として引用されることも多く、Netflixの大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス』などにも影響を与えているはず。『リドル・オブ・ファイヤー』は、まさに子どもたちが使命を受けて冒険に出かける活劇で、ルックもノスタルジックな80年代的色遣いを意識しているなど、『グーニーズ』リスペクトは一目瞭然だ。
『リドル・オブ・ファイヤー』は、やんちゃな少女のアリスが主人公。店舗倉庫からモノをくすねて仲間たちと大はしゃぎするアリスは、病気のお母さんの願いを叶えないといけない羽目になる。その願いとは、ブルーベリーパイを手に入れること。かくして、最高のパイを作るための冒険が始まる!

こう書くだけで胸が高鳴ってくる。とはいえ、それではこの作品が『グーニーズ』のようなメジャーな商業映画なのかというと、実はそうではなくて、80年代再現へのアプローチにはキッチュな作家性が伺えて、むしろアート寄り(ポップアートと言ってもいいかも)の作品なのだ。そのマニアックな映画へのこだわりは、(多くの場合ホラーやSFや犯罪ものを指しコアな映画ファンがこだわりを見せる)「ジャンル映画」との戯れにも顕著だ。ワイオミングの美しい景観とまばゆい光線の中、冒険に出かけた少年少女は敵との対決を迫られ、映画は一気に西部劇(ウェスタン)の世界に入っていく。もちろんコメディーの要素も多分に含み、あらゆるタイプの映画で遊びながら、ルックはフィルム撮影の80年代リスペクト、そして仕上がりは最高にキュートという、映画ファンを歓喜させる作品なのだ。
ウェストン・ラズーリ監督の長編1作目であり、監督について情報はあまりないのだけど、映画オタクであることは間違いない。本作を皮切りに頭角を現していくだろう。今のうちに青田買いを!

日本の期待の新鋭監督による『ゆ』
23年のカンヌ監督週間に選ばれた唯一の日本の作品が、平井敦士監督による短編『Oyu(ゆ)』である。
平井監督はフランスに拠点を置き、助監督として経験を積み、フランスの製作助成金制度を活用しながら映画を作っている(※2)。フランスの製作体制で臨みつつ、描くのは監督の地元の富山である。平井監督の初短編『Return to Toyama(フレネルの光)』(2020)は、フランスから故郷の富山に帰省した青年が父の死に思いを馳せる好編であった。

続く新作短編の『ゆ』が見事カンヌに選ばれたわけだが、これが実にしみじみとした味わいが胸に染みる逸品で、なるほどカンヌに入るクオリティだと強く納得させられる。大晦日の夜に、東京で暮らす男が故郷の町の銭湯に入る物語。銭湯コミュニティーの様子を眺めている男の胸の内が、少しずつ観客にも伝わっていく展開が、なんとも上手い。21分の上映時間に人生が詰まっている。短編のお手本のような作品だ。

今回の「監督週間 in Tokio」では、『フレネルの光』と『ゆ』の2作品とも上映されるので、日本映画の未来を担う才能を発見する絶好の機会となるはずだ。
※2 参考: ひとシネマ「学ゼロから在仏10年 仏の映画支援利用し短編で実績重ね『次は長編も』 『ゆ』の平井敦士監督」
https://hitocinema.mainichi.jp/article/filmmaking-france-hiraiatsushi
英語字幕で映画を見るということ
今回の「監督週間 in Tokio」には、大きなチャレンジがある。それは、日本語字幕が付かず、英語字幕のみで上映される作品がいくつか存在することだ。これは、日本の劇場における外国作品の有料上映としては、極めて珍しい試みだ。
主催側にとっても、観客に受け入れられるかどうかは大きなチャレンジである。一方で、もし英語字幕のみの上映に対する世間的抵抗感が和らぐようなことがあれば、未来の映画祭等における外国映画上映に大きな道が切り開かれることになる。
単純に言えば、字幕制作費を節約できるために、上映可能本数が倍増することになる。実際に、自国語の字幕を不要とするような映画祭では上映本数が多い。作品数が300本に近いロッテルダム映画祭の上映にオランダ語字幕は付かないし、同じく作品の多いベルリン映画祭でドイツ語字幕が省略されるケースは珍しくない。多様な作品を紹介する機会が増えることに繋がるため、日本語字幕不要で映画を上映できるようになることは、日本の映画祭(映画上映)従事者の宿願であるとも言えるのだ。
しかし、そのハードルは極めて高いということは、誰もが知っている。日本語字幕が無いと分かった途端にそっぽを向かれることも覚悟せねばならない。
とはいえ、英米の英語映画を聞き取ることが簡単ではないとしても、「英語字幕を読む」ことはそんなに不可能ではないはずなのだ。映画を見に来る大半の人が最低でも3~6年間は学校で英語を学んでいるわけで、以来英語から遠ざかっているとしても、最初から英語字幕の半分は理解できると思う。それほど難しい単語が使われているわけではないし、半分分かれば、映画のおおよそのところは理解できる。そして、そうやって続けると、あっという間に慣れる。最初の抵抗感を超える気持ちさえあれば、あっという間に慣れる。
慣れてしまえばこっちのもので、見られる映画の数が飛躍的に増えるし、いつ海外の映画祭に行っても大丈夫だ。そう、もちろん海外の映画祭の上映に日本語字幕は付かない。「監督週間 in Tokio」で英語字幕のみの作品を見ることは、まさに海外の映画祭体験となるわけだ。
誤解の無いように強調しておくと、「監督週間 in Tokio」では大半の作品に日本語字幕が付いており(本稿で紹介した作品は全て日本語字幕付)、英語字幕のみの上映は外国映画全12本のうち4本のみである。下記HPの作品紹介欄で字幕情報を確認してもらいつつ、ぜひこの4本にも挑戦を!
▼カンヌ 監督週間 in Tokioホームページ
https://www.cannes-df-in-tokio.com/
おわりに
ここでは詳しく紹介できなかったが、ベトナムの新たな才能による映像詩『Inside the Yellow Cocoon Shell(黄色い繭の殻の中)』、インドで特異な状況下で暮らす家族を描く『Agra(アグラ)』、いにしえの犯罪映画にオマージュを捧げる新感覚なベルギーの『The Other Laurens(アザー・ローレンス)』、パキスタンで抑圧下にある女性の反撃がホラー風味を交えて描かれる『In Frames(イン・フレーム)』、韓国の名匠ホン・サンス監督新作『In Our Day(イン・アワ・デイ)』など、見ごたえのある個性作が溢れている。
世界の映画の潮流をリアルタイムで体験できる場としての「監督週間 in Tokio」、多くの方の刺激となることを期待したい。
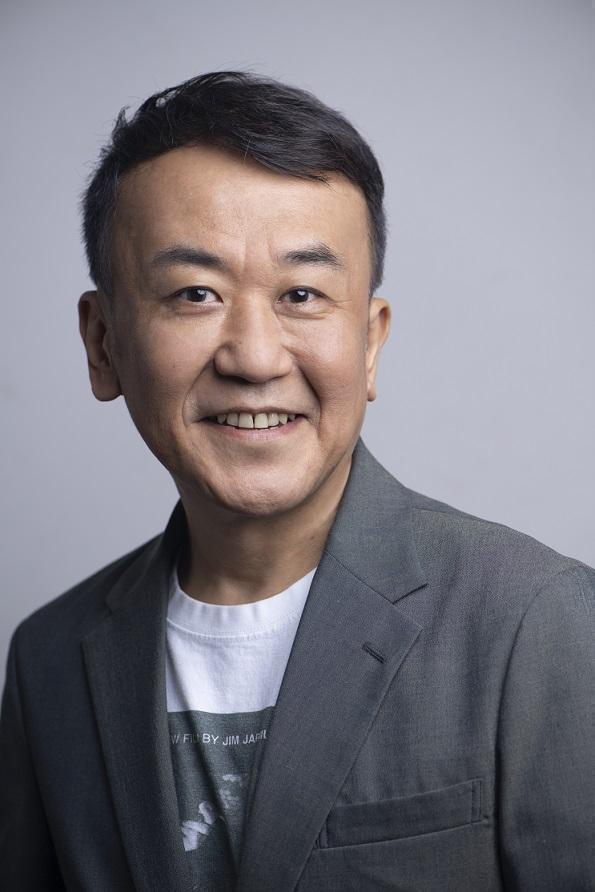
矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
