
©21世紀の女の子製作委員会/©21st Century Girl Film Partners
映画監督の声明や「ジェンダーバランス白書2022」などの各種調査を通じ、映画界におけるジェンダー格差を取り上げるニュースに触れることが多い。格差は良くないが、ニュースになることは良い。継続的にニュースになり、絶えず意識が喚起されることが大切だ。
「上映作品の中で女性監督作は何本ありますか?」という質問を東京国際映画祭勤務時に頻繁に受けるようになったのは、2018年頃からだったろうか。2017年に映画界の悪行が暴露され“#Me Too”が盛んとなり、カンヌ映画祭では歴史を通じてコンペに入る女性監督作品が異様に少ないとの指摘がなされた。東京国際映画祭で作品選定に関わっていた僕自身は、当初は選定プロセスにおいて監督の性別を気にすることはないと答えていた。けれど、やがて、敢えて女性監督作品を取り上げていくことも必要だと思うようになった。クオリティーを無視するわけにはいかないが、積極的に取り上げることで「動き」を作っていくことも重要だと思うようになったのだ。
同じように、敢えて「女性監督」と言わなくてもいいじゃないか、との考えもとても分かる。けれども、言い続けることも大事だとも思っている。監督に女性も男性もないよと嘯くには、まだ日本は文化的にも社会的にも成熟が足りない。女性大臣が少ない、女性役員が少ない、ということをしつこく指摘し続けないといけないのと同様、女性の監督の存在をはっきりとアピールし続けてこそ、次の世代の女性たちが監督を目指しやすくなるはずなのだ、と考える。
そこに、男性である僕が出しゃばらない方がいいのではないかと思ったこともあるのだけれど、西原孝至監督の『シスターフッド』(19)というドキュメンタリー作品を見て、考えが変わった。作品に登場するフェミニストの女性が「こういう話は女性同士だけでやっていると、ウザがられるだけで終わっちゃうから、男性を味方に引き込まないと先に進まない」「ちゃんと男性を巻き込まないと」と発言していて、ああ、巻き込まれていいんだ、と気が楽になったのだった。
『21世紀の女の子』とは
さて、女性監督作品の数が指摘され始めた2018年に登場したのが、『21世紀の女の子』という企画だった。春先に山戸結希監督から企画を聞かされ、これはぜひとも映画祭で紹介するべきだと思ったことを、昨日のことのように覚えている。かくして、山戸結希監督の声がけのもと、14人の女性監督が結集し、8分の短編14本によるオムニバス作品が作られた(正確に言うと、クレジットのアニメを製作した玉川桜監督を入れて15人、15作品)。「ジェンダーの揺らぎを感じたとき」という共通のお題が与えられているものの、それはとても緩やかな縛りであり、ほとんどの監督が自由に自らの世界観を紡いでいる。

全くの新人という存在はほとんどおらず、2018年の段階で既に何らかの形でデビューして話題を呼び、これから伸びるという監督たちに山戸監督が声をかけている点が重要だ。それを証明するかのように、『21世紀の女の子』に参加した監督たちの現在の活躍が目覚ましい。コロナなどで時間の感覚が狂っているからか、2018年からまだ4年しか経っていないことが不思議でならないのだけど、ここで参加監督たちのいまの仕事を見つめてみたいと思う。
もっとも、僕は監督たちが本作への参加を現在どう思っているのか全く知らないし、互いに親近感や連帯感を抱いているかさえも全然知らない。ひとくくりにされることを迷惑に感じる人もいるかもしれない。そして、言うまでもなく本作に参加した「21世紀の女の子たち」以外にも活躍している女性監督はたくさん存在する。ただ、14名の監督全員を檀上に迎えてトークを行った映画祭上映時の「あの瞬間」は、僕にとっては生涯忘れることのないとても重要な場であり、陳腐を恐れずにいえば新時代の到来に立ち会っているくらいの気持ちだった。14名全員に発言してもらうのが司会進行として至難の業であったという緊張は置いておくとして、14名の想いが融合と衝突とを起こし、檀上には異常な磁場が発生していた。あの時以来、「21世紀の女の子たち」の活動を追うことは、僕にとってライフワークになる気がしている。勝手な思い入れをお許し頂きたいが、あの2018年のタイミングで彼女らが結集したことに運命を感じてしまうし、日本映画の今後の核になっていくだろうとの確信めいた思いも止まらないのだ。

ちなみに、タイトルに逆らうかのように、『21世紀の女の子』では全14本を通じてスマホもソーシャル・メディアも一切登場しないのが印象に残った。監督たちは20世紀のメディアである「映画」を強く志向しているようにも感じられた。それも映画の未来を彼女たちに託したくなる理由のひとつである。
その14人とは、敬称略/順不同で並べると、山戸結希、井樫彩、枝優花、加藤綾佳、坂本ユカリ、首藤凛、竹内里紗、夏都愛未、東佳苗、ふくだももこ、松本花奈、安川有果、山中瑶子、金子由里奈。
今回の記事では全員に触れることが出来ないことをあらかじめお断りしなければならず、残念なのだけれど、今後も不定期的に書いていけたらと思う。なんせ、ライフワークなのだから。
首藤凛監督『ひらいて』の衝撃
『21世紀の女の子』中でもっともプロの仕事と思わせた1本が、首藤凛監督の『I Wanna Be Your Cat』だった。温泉宿を訪れた男性監督と女性脚本家の関係が描かれ、仕事も恋も煮詰まっていく様子を、小気味よいセリフの応酬と明るく軽快なテンポで実に楽しく見せてくれた。8分の短編のお手本のような作品だ。
そして、首藤監督が次に手がけた長編作品『ひらいて』が、2021年に公開された。首藤監督の才能を世に知らしめる素晴らしい出来栄えであり、同年の日本映画のベストの1本に挙げることにためらいはない。
女性の高校生が級友の青年に恋をしているが、その青年には密かに付き合う別の女性がおり、ヒロインはその女性に接近して彼らの関係を壊そうとする。典型的な三角関係の形を持ちながら、強烈な自我を持つヒロインの心理が変化する瞬間の描き方が非常に巧みだ。自分の企みが期せずして有効活用できそうだと気付いたヒロインの一瞬の心理の変化を、一瞬のカメラワークで表現させた演出には、まさに息を呑む。ハイスクール映画の枠を軽々と超え、人間の業の深さをスリリングに描いてみせる傑作である。綿矢りさ氏の原作の良さもあるのだろうけれど、エゴイストなヒロインを演じきった山田杏奈の魅力と、それを引き出した首藤監督の演出力により、映画は原作を超えた魅力を獲得している。
短編はコメディータッチだったが、今回の長編は真剣な心理ドラマであった。首藤監督はオールラウンダーとして活動していくのか、それともシリアス路線で行くのか。セリフ回しと映像のキレの両者に長けており、いかなる分野を手掛けても高水準な作品を届けてくれる予感がある。今後がもっとも楽しみな監督のひとりであることは間違いない。
枝優花監督『息をするように』の静けさ
『少女邂逅』(17)で少女の孤独と痛みをビビッドに描いた枝優花監督は、『21世紀の女の子』内の『恋愛乾燥剤』で全く異なる一面を見せてくれた。付き合ってみた相手が自己中のダメなヤツであることに気付いた少女が、相手の恋愛の熱を冷ます「恋愛乾燥剤」を薬局で見つけて大量に購入するという愉快な物語。若手監督は色々と試すから面白い。どんなに短かろうが、きちんと物語のある映画を作ろうという意欲が感じられ、ユニークな発想を楽しめる8分間であり、多彩な才能の片鱗を感じさせてくれる1篇だ。
そして2021年に観ることのできた新作短編『息をするように』は、ジェンダーやセクシュアリティに静かに向き合う真摯な作品であった。監督が主人公にぴったりと寄り添っているような、実に丁寧に気持ちを込めて作られている。孤独であることや、親しい相手が出来ることの心の動揺など、思春期の難しい内面を地方都市の繊細な自然光を駆使して美しく描いていく。
いつの世にも存在しそうな普遍的な主題ではあるけれど、主人公の高校生の少年を伊藤万理華が演じている点で、今という時代と強く繋がっている。20代の若手監督たちが次々と青春映画をアップデートしていく様を見るのはとても刺激的だ。コミック原作の商業青春映画も悪いとは言わないけれども、首藤監督や枝監督が作家性を発揮した青春映画が日本映画を更新していくのだと感じる。
安川有果監督『よだかの片想い』の強さ
安川監督の作品は少女の世界を離れ、大人の内面を描こうとする落ち着きがある。そして全てを言い切らない良さがある。説明過多な作品が多い中、安川監督は行間をたっぷりと用意する。観客に味わい、考える余地を与えてくれる演出家だ。
『21世紀の女の子』の1篇『ミューズ』では、有名小説家の妻が、夫の小説の夢を叶えるかのように死ぬ。事故死か自殺か分からない。石橋静河演じるヒロインは生前の女性と交流があり、妻を失った夫である小説家にうつろな眼差しを投げかける。男性芸術家にインスピレーションを与える女性という「ミューズ」なるものへの痛切な批評であろうか。絶妙な余韻を残す作品だ。
そして安川監督の新作長編『よだかの片想い』が9月16日から公開されている。内向的な女性が覚える恋心をストレートに描く作品だが、観客はヒロインの心情に寄り添いながら、彼女の決断を、固唾を飲んで見守ることになる。
生まれつき顔にあざを持つ大学院生の女性が、あざを自らのコンプレックスとするよりは、むしろ周りの気遣いを重荷に感じ、生きづらさを感じている。しかし、恋愛には奥手であるものの、しっかりと前向きに研究に取り組んでもいる。そんな彼女の生き方を映画にしようとする男性監督と恋に落ちる。

ヒロインは正々堂々と自分の気持ちを伝え、その強い姿勢が清々しい。観客は彼女の性格に惹きつけられるだろう。内向的=弱さでなく、ステレオタイプを避ける安川監督の創造力が頼もしい。それは男性キャラクターにも発揮され、恋愛相手となる男性監督の人物像は極めて魅力的でもあり、密かに虚無的でもある。この男女が相まみえる時の空気感は実に雄弁で、セリフ以上のものをもたらしてくれる。いや、城定秀夫氏が手がけた脚本のセリフもかなりいいのだけれど、安川監督は人物を丁寧に配置し、その場に濃密なエモーションをもたらしていく。そして、心理描写に目が向かってしまうが、実はロマンティックな場面の甘く幸せな情感の盛り上げ方も、上手い。
確固たるキャラクターたちの個性と、冷静に見えてエモーショナルな安川監督特有の詩情が、長く心に留まる作品である。
井樫彩監督『あの娘は知らない』の切なさ
「ジェンダーの揺れを感じたとき」という『21世紀の女の子』企画に与えられた主題にもっとも忠実な形で応えたのが、井樫彩監督の『君のシーツ』だった。1組の男女がセックスをしているが、女性はその最中に別の女性とセックスするイメージを抱く。その夢の中で彼女は髭を蓄えており、女性とセックスする。メッセージをストレートに伝える無駄のない8分間であり、その潔さに拍手を送りたい気持ちを抱いたものだった。
その井樫監督の新作長編『あの娘は知らない』が9月23日に公開された。

地方の港町で若くして旅館を経営する女性。その旅館に泊まりに訪れる青年客。青年の恋人が、旅館に宿泊していた。その恋人は亡くなり、青年は旅館の女性の助けを借りて、恋人が訪れたであろう場所を巡る。このふたりと、亡き恋人の「不在」が大きな存在感を示すのだが、フラッシュバックでその恋人を見せる作りでないところがとてもいい。不在の強調が、ふたりの孤独を際立たせていくのである。ふたりの男女は距離を縮めるものの、心には別の存在を抱いているという図式は、『君のシーツ』の延長上にあると見てもいいかもしれない。近くて遠い、遠くて近い他者。残されてしまった者たちの絶望的な孤独は、埋めることが出来るのだろうか。そもそも孤独とは、共有できるものなのだろうか。ゆっくりとした夏の時間の中で、心の回復の過程が描かれていく。

主演の福地桃子と岡山天音が映画を牽引している。監督と同世代の優れた俳優たちが監督と並走するように作品を作っており、人生のこの時期にのみ放つことのできる輝きを放つ。首藤凛と山田安奈、枝優花と伊藤万理華、安川有果と松井玲奈、そして井樫彩と福地桃子。まるで、監督たちが自らの魂を並走する俳優に預け、キャラクターの内面に真実の灯火をともしているように見える。
驚くべき層の厚さ、そして最終兵器
4人の監督に言及してみたが、「21世紀の女の子たち」の活躍はもちろんこれにはとどまらない。
松本花奈監督は長編監督作『明け方の若者たち』において疾走感溢れる青春を描き、作品は21年12月に公開された。ふくだももこ監督も長編監督作『ずっと独身でいるつもり?』が21年11月に公開され、メジャーなフィールドを切り開こうとする意欲が作品に漲っていた。竹内里紗監督はオムニバス映画『MADE IN YAMATO』(21)の中の1篇『まき絵の冒険』を監督し、21年の東京フィルメックスに参加している。加藤綾佳監督は演出を手掛けたTVドラマ「オールドファッションカップケーキ」(フジテレビ)が放映中だ。坂本ユカリ監督はアート系映像作品を積極的に発表しており、東佳苗監督はファッション方面での活躍が伝えられる。夏都愛未監督は長編新作を完成させ、近々発表があるらしい。そして金子由里奈監督は、新作長編『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』が23年春の公開を待っている。なんという充実度だろうか!
そして『21世紀の女の子』の仕掛け人、山戸結希監督は、2019年の『ホットギミック ガールミーツボーイ』以来、雌伏している。新世代の旗手として一身に期待を集め、カリスマ的な存在にも近づいた山戸監督は、いま何をしているのか。僕は、ほんの少しだけ知っている。ほとんど知らないけれど、ものすごく高くジャンプするために、ものすごく低くかがんでいることを、ちょっとだけ知っている。早晩、ニュースが届くはずだ。その時を楽しみに待とう。
さらに、『21世紀の女の子』にはもうひとりバケモノがいる。言い方が悪くて申し訳ない。畏怖の念を込めた最大限の賛辞と受け取ってもらいたい。それは、山中瑶子監督だ。僕は、彼女は日本映画の最終兵器だと思っている。たんに才能があるというようなレベルではなく、映画の有り方を変えてしまうような、それほどのインパクトとスケールを感じさせるのだ。『21世紀の女の子』の冒頭を飾った山中瑶子監督による『回転てん子とどりーむ母ちゃん』は、突出したセンスによっていきなり観る者の度肝を抜いた。中華料理店を舞台にしたゴージャスで猥雑で悪夢的な世界観は、もう誰も寄せ付けない力と個性を発揮している。続いて、2020年に発表された短編『魚座どうし』では、エキセントリックな世界観は影を潜めた代わりに、小学生の男女の不安定な胸の内を斬新なカメラワークを駆使しながらも、まるで大物監督の手によるものであるかのような貫禄の演出で撮り切っている。同作の試写の帰り道で知り合いのプロデューサーと絶句しながらもただひと言「山中さんは群を抜いている」と言葉を交したことが忘れられない。
本人は甚だ迷惑かもしれないが、日本映画が救われる日が来るとすれば、それは山中瑶子監督が長編を完成させた日に他ならないと信じている。どれだけ時間がかかっても構わないので、ゆっくりじっくり取り組んでもらえたらと思う。その日までは、僕も元気でがんばろう。
数十年後、『21世紀の女の子』がいかに画期的で重要な企画だったか、回顧される時が来るかもしれない。いや、必ず来るはずだ。参加監督たちが活動を続けることで新たな女性監督たちが後に続き、それが現場の環境改善に大きく寄与していくに違いない。そして、参加監督たちの中から、現在は男性監督に独占されている大きな予算の商業映画を託される存在が出てくることも、大いに期待したい。
彼女たちが新しい時代を切り開く様子を、出来るだけ長く見届けていきたい。
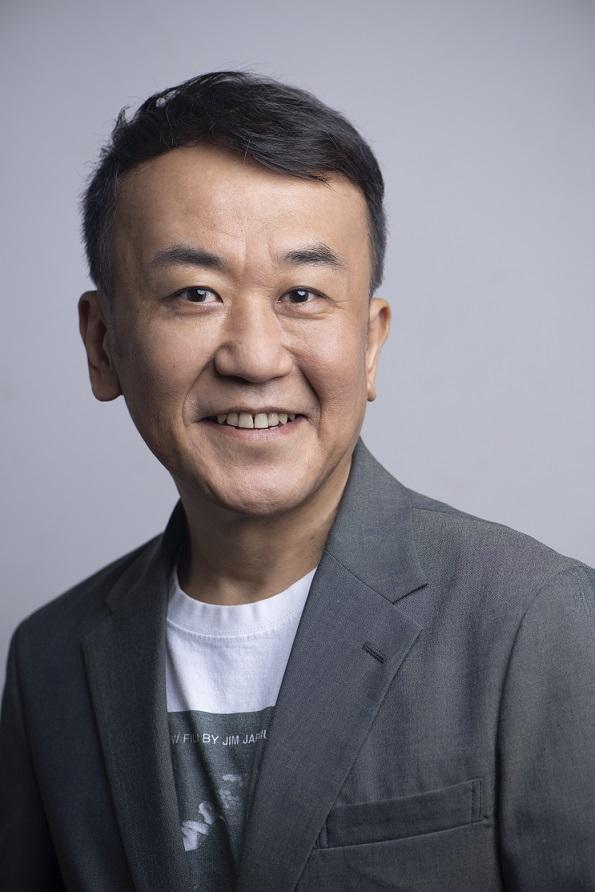
矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
(注)
本コラムに記載された見解は各ライターの見解であり、BIGLOBEまたはその関連会社、「あしたメディア」の見解ではありません。
