
あらゆるイベントがそうであったように、世界の映画祭も2020年はコロナの大波に飲まれ、規模縮小や延期や中止を余儀なくされた。そして2021年は、本来の形に近づける努力がなされながら、多くの映画祭が何とか無事に実施されたようである。しかしカンヌは例年の5月から7月の会期となり、ヤマガタ(山形国際ドキュメンタリー映画祭)はオンラインのみになるなど、まだまだ通常の形には遠く、さらに欧州の現状を見るに、どうやら来年も安泰とはならないようだ。それでも、ともかく世界の映画祭は開催され続け、映画を繋ぐサーキットは途切れてはいない。そして、それらの国際映画祭で今年大きな存在感を発揮した日本映画が立て続けに公開される。果たして海外の映画祭では、どのような作品が評価されるのだろうか、それらの作品に共通点はあるのだろうか?
国際映画祭が日本映画に求める「ローカル性」と「普遍性」

2021年、国際的に最大の成功を収めた日本映画が濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』であることは衆目の一致するところだろう。カンヌ映画祭で脚本賞を受賞したが、実は授賞式を前にした批評家による下馬評では本作がトップであり、最高賞受賞が本気で期待されていた。結果、最高賞の受賞はならず、カンヌの下馬評はなかなか当たらないことが改めて証明されてしまったが、2年振りにカンヌに集まった映画人たちに与えたインパクトは絶大であった。
村上春樹の3つの短編を土台に持ち、チェーホフの戯曲を劇中劇に取り込み、映画と小説と演劇の三位一体を成し遂げるような奥行きの深さが世界の観客の胸に響いた。そして、愛のあり方を問いかける主題に加え、手話をも加えた多言語の演劇を通じてコミュニケーションの可能性を追求したことが、作品が国境を越えるに至った要因でもあろう。「分断」が叫ばれるいまの時代において、コミュニケーションの可能性こそが、世界が求める主題ではなかろうか。独自の理論を実践した孤高の映画作家ロベール・ブレッソンは、「意思疎通の不可能性こそが、この世界で、あらゆる社会で繰り広げられる数多の悲劇の根柢にある」(※1)と発言しているが、1960年代に発せられたこの言葉は、現在ますます重さを増しているようだ。
一般化は難しいけれど、映画祭で選定される作品には、ローカル性と普遍性の双方が求められる気がしている。選ぶ側は、「日本映画的」であってほしいと願うと同時に、日本を飛び出て共感できる社会性や普遍性を備えていないと難しいと感じるはずだ。もともとオリエンタルな情緒の薄い村上春樹の世界を土台にしている『ドライブ・マイ・カー』に「日本映画的」な要素は希薄だけれども、日本語はひとつの言語として他の言語と並列され、日本の存在を意識させる作品ではある。実際に登場人物たちはよくしゃべる。しかしあくまでも日本語は、英語、中国語、韓国語、韓国語手話、などの言語と混じり合い、通訳を介さない対話の交換は、意味を超えたレベルでのメタなコミュニケーションを意識させていく。コミュニケーションの可能性を描く果てに、1番近い存在であるはずの妻と真の意思疎通が図れなかった主人公の悲劇が強調されると同時に、言語を超える希望も描かれていくのが『ドライブ・マイ・カー』という作品であった。
普遍と独創を兼ね備えた作品のクオリティーが最も重要であることは言うまでもないが、濱口監督が着実にステップを積み重ねてカンヌ受賞に至った点も強調しないといけないだろう。カンヌに出品するにはどうすればいいかという質問を受けることがあるが、公募の窓は誰にでも開かれているにせよ、実績の浅い監督をすぐに取り上げてもらうには、カンヌはあまりに競争率が高すぎる。カンヌやヴェネチアなどのクラスでなくとも、世界に優れた映画祭は多い。深田晃司監督にしても、濱口竜介監督にしても、ナント三大陸映画祭やロカルノ映画祭で実績を重ね、カンヌと太いパイプを持つプロデューサーと組み、やがてベルリンやカンヌへと至っている。ロカルノやロッテルダムやサン・セバスティアンなどの映画祭で日本の監督がいかに活躍しているかを追うことが、今後の日本映画を占うことになるのだ。
※1参照「彼自身によるロベール・ブレッソン: インタビュー 1943–1983」(法政大学出版局)
「よくしゃべる」と「伝わる」はイコールではない
濱口監督が描くコミュニケーションの可能性
さて、濱口監督作品としては、7月のカンヌの『ドライブ・マイ・カー』上映に先んじて、2月のベルリン映画祭で『偶然と想像』(12月17日公開)がコンペに選出されている。同一年のベルリンとカンヌでコンペに入るとは、おそらく日本の監督では前例はないのではないか。ベルリンで見事銀熊賞(実質2等賞)を受賞した『偶然と想像』も『ドライブ・マイ・カー』と同等の刺激が込められているのだから、2021年はつくづく濱口監督の年だ。

『偶然と想像』は3本の短編からなる作品である。モデルの女性と元カレ、男性の大学教授と既婚の女性の大学生、高校時代の友人と再会する中年女性。基本的にふたりの人物の関係を描く3つの物語が並んでいる。いずれも優劣付け難く、優れた短編小説を読むような充実感が味わえる。それぞれが独立した物語であるけれど、3作続けて見ると、全体に起承転結があるように思えてくる。偶然があり、絶望があり、希望があり、そして観客は全体に対して想像を巡らせる。『偶然と想像』というタイトルの奥深さたるや。
『偶然と想像』は、『ドライブ・マイ・カー』と近似した形で、映画と小説の関係を意識させる。実際に2話目の大学教授は作家でもあるという設定であり、彼の書いた小説が劇中に重要な役割を果たす。教授は、作家としての自分は言葉の配列に気を配っただけで大した仕事はしていないと謙遜するが、エピソードやシークエンスの配列を巧みに差配する濱口監督の演出を代弁するコメントのようにも聞こえてくる。映画監督にしろ、小説家にしろ、芸術家のスタンスが語られる場面は第2話において重要なシーンとなるのだけれども、必ずしも大学教授の言葉はストレートに届くわけではない。

ここでも、コミュニケーションの可能/不可能性が主題のひとつになってくる。渋川清彦が見事に演じる大学教授は、妙に抑揚のない話し方をする。言葉に感情が希薄で、あえて棒読みに近い聴こえ方もする。これは『ドライブ・マイ・カー』の西島秀俊のしゃべり方に通ずるとも言える。西島本人のセリフもそうであったが、思えば、『ドライブ・マイ・カー』の劇中、俳優たちを集めた「本読み」の場面において、西島扮する演出家は、とにかく感情を込めないで棒読みをするように、と俳優たちに指示したのではなかったか。
濱口監督は、感情というメッセージを言葉に込めないことで、テクストがどのようなニュアンスを持ちうるかを計っているようだ。『偶然と想像』の第2話においてその特徴は顕著である。そして、淡々とした話し方は、自然と小津安二郎のそれを連想させずにいられない。加えて、人物が確信的な発言をするとき、あるいは相手との心理的距離に変化が訪れた時、まさに小津のように、真正面から人物を捉えるショットが用いられるのだ。多用されるセリフから感情的ニュアンスを削ぎ落しつつ、カメラの切り返しがエモーションを物語る。言葉以上に雄弁なシークエンスである。
第3話は、故郷のクラス会に出席した女性を巡る、全く奇想天外な物語で心底びっくりしてしまうけれども、まるであり得ない話ではないかもしれないという気持ちを見る者に抱かせるに違いない。このエピソードにおいて、コミュニケーションの射程は驚くべき範囲へと及んでいく。
『偶然と想像』は、決して重厚なアート映画などではなく、軽やかな現代のドラマである。その風通しの良い奇譚集の中で、濱口監督は人間関係の本音と建前を見抜き、世界共通の言語を獲得したかのようだ。ベルリン映画祭での受賞もむべなるかな、である。
言葉を削ぎ落として感情を炙り出す
杉田監督が描くコミュニケーション
ベルリンとカンヌを席巻したのが濱口監督であるとすると、2021年の後半の国際映画祭を疾走しているのが杉田協士監督である。杉田監督の新作『春原さんのうた』(2022年1月8日公開)は、世界主要映画祭のひとつに挙げられるスペインのサン・セバスティアン映画祭を皮切りに、ニューヨーク、釜山、サンパウロ、ウィーンなどの重要映画祭に招聘され、フランスのマルセイユ映画祭ではグランプリに加えて俳優賞と観客賞も受賞している。コロナ対策を入念に調整しながら、杉田監督は果敢に海外の映画祭に出かけており、見聞と人脈を築いているようだ。どの映画祭も、1度招聘した監督とは極力付き合い続けるという習性があり、直接出かけて行って人脈を築くことが将来の別のチャンスに繋がることになるので、コロナ下の海外渡航は本当に面倒なことばかりだけれど、それにめげずに出かけている杉田監督は正しい。
杉田監督の作風は、ひと言でいえば、とても落ち着いたアート映画である。落ち着いた佇まいの中に、実に芳醇な空気が満ちている。暖かい空気であることが基調であるのだけれど、時に辛く、時に不思議な色をまとうこともあり、時間を自在に操り、人の感情の深いところを風の動きひとつで表現してしまうようなタッチを身に備えた監督である。
映画祭の作品選定において、一定の社会性が求められることは上述したが、ある程度の予算規模を持った(つまりルックとしては海外作品に見劣りのしない)日本映画は、政治や社会問題を正面から描くことが稀なため、それだけで映画祭に選出される可能性は低くなってしまう。映画祭サイドからすれば、社会問題を扱う作品が偉いと単純に考えているわけではなく、問題意識を持った映画作家がその主題に取り組み、商業的な成功が望めない場合には、その作家と作品を擁護することが映画祭の役割だと考えていると書いたほうが近いだろうか。
商業作品でない映画も映画として応援するというのが映画祭の一義的な存在意義であるはずで、アート度の高い作品、あるいは「作家」と呼びうる監督を発見し、称揚していくことが映画祭の大きな役割である。そして、映画祭に携わっている立場の者としても、監督との並走が大きな歓びとなる。杉田協士監督は、そのような文脈において、世界の映画祭プログラマーの心を掴んでいるようである。
東京国際映画祭で作品選定を担当していた僕の立場から言うと、2011年に杉田監督の処女長編『ひとつの歌』を見て、過度な説明を省略したストイックな美学にたちまち惹き込まれた。同映画祭で日本のインディペンデント映画を応援する「日本映画・ある視点」部門(その後「日本映画スプラッシュ」部門と改称し、2019年まで継続)に作品を招待し、監督の知己を得ることになった。実に落ち着いた物腰の人物で、作風とお人柄がマッチしている珍しい映画監督だ。
謎めいたきらめきや、処女長編なりの初々しさも備えていた『ひとつの歌』から6年を経て、2作目の『ひかりの歌』(2017)は、杉田監督の才能を再確認させられる傑作であった。4首の短歌から着想した物語が4つ連なる短編集であり、ひとつの短歌から生まれる物語の広がりに感嘆させられるとともに、孤独をベースにした静かな感情のうねりが全編を貫き、極めて深い余韻を残す。五七五七七の文字数が持つ無限の広がりを映像化した、詩歌と映画を結ぶ至上の作である。

新作の『春原さんのうた』もまた、短歌を原作に持つ作品である。しかし今回は1篇の歌を土台に、ひとつの長い物語が綴られている。いや、長い物語というのは少し語弊があり、ひとつの状況を巡る長編、と書いたほうが正確かもしれない。
夏の日、ひとりの若い女性が、アパートの一室に越してくる。玄関のドアを開き、窓を開け放つと、涼しい風が室内を吹き抜け、エアコンが不要であるような素敵な部屋で女性は暮らし、職場であるカフェに通う。親戚や友人が彼女を訪ね、ともにスパゲティやどらやきを美味しそうに食べる。日々が平穏に過ぎゆく中、時おり、女性は静かに遠くを眺める…。

本作の物語を紹介することは容易ではないのだけれど、目で追っているだけでは感知できないレベルで、ゆるやかで大きな物語が根柢に流れている作品である。風に揺れるカーテンが雄弁に語ることもあれば、お盆の季節の到来によって精霊が語りかけてくることもあるかもしれない。ゆっくりとした時間の中にたゆたうものを、見るものに想像させ、そして感じさせる。説明はほとんどないけれども、答えが風の中にあることを、充分に感じさせる能弁な作品である。純度の高いアートであり、味わうほどに滋味が溢れ出る芸術家の作品だ。
世界が注目した2人の日本人監督が問い続ける
コミュニケーションの可能性と不可能性
杉田監督の作品は、セリフがとても少ない。それは、言葉以外の手段によるコミュニケーションを描いていることに他ならない。処女長編『ひとつの歌』の寡黙な青年は、ポラロイド写真を撮り続けることが自分のコミュニケーション手段となる。『ひかりの歌』で教え子の男子高校生に想いを告白された臨時美術教師は、100の言葉で諦めさせるよりも、互いのポートレートを静かに描き合うことで青年の気持ちを鎮めようとする。『春原さんのうた』のヒロインは、決して届くことはないと覚悟している手紙をしたためる。杉田作品では、不器用な人物たちがみな、懸命に言葉にならない言葉で互いに愛を告げ合っているように見える。声ではないメッセージや叫びを映像のゆらめきの中で掬い取っていくのが、杉田作品の神髄だ。
これに対し、前述した濱口監督の人物たちは、雄弁だ。よくしゃべる。しかし、よくしゃべるが故に、その行間や口調などを通じ、別のメタなメッセージを感じることが出来る。ふたりの監督の作風は全く異なっているけれども、コミュニケーションの可能性/不可能性を描こうとしている点で、正反対のアプローチを用いながら、とても共通しているように見えるのだ。
国境と言語を越えようとする作品に、国際的な映画祭が注目することは自然なことであり、2021年の国際映画祭を濱口竜介監督と杉田協士監督が席巻したことは決して偶然ではない。
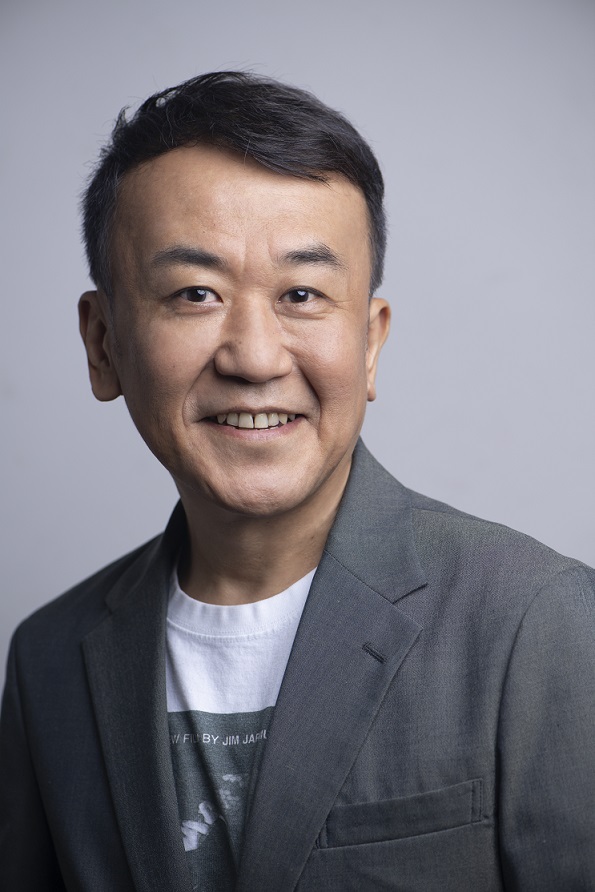
矢田部吉彦
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
