
アメリカのインディペンデント映画と聞いて、すぐにジョン・カサヴェテスの名前を出すのは単純過ぎるとの誹りを免れないかもしれないけれど、もう条件反射のようなものなのでしょうがない。愛の裏側を生々しい人物観察を通じて活写したジョン・カサヴェテスから刺激を受け続けている人は今でも多いであろうし、ここでカサヴェテスをアメリカン・インディの祖のひとりと崇めてもバチは当たらないだろう…、と信じたい。
カサヴェテスを評する言葉は無限にあれども、頭の悪さを恥じずにひとことで言えば、カッコいいのだ。むきだしの人間性が、NYの街角を背景にスタイリッシュなモノクロで描かれる。ビジュアルの鮮烈さがクールなアート作品として世界を席巻し、過剰に消費もされてきたが、ともかくアメリカン・インディペンデントと言えばカサヴェテスのことなのである。我ながら乱暴だとは自覚しているが、そんな断定から本稿をスタートしてみよう。そして、その偉大な父親を継ぐかのように、いくつかの時代の節目にアメリカン・インディの魅力を世界に放つ存在が現れた過程を見てみよう。
60年代終盤〜70年代:アメリカン・インディペンデント映画を支えた3人の監督
カサヴェテスが監督として重要作を発表したのは60年代終盤から70年代にかけてであり、アメリカ映画史の本であれば、並走するような形で台頭したマーティン・スコセッシやフランシス・フォード・コッポラらにも触れるのが筋であるだろう。ここで深入りは出来ないが、彼らの台頭とはいささか別の次元で、70年代後半からハリウッド映画のブロックバスター化が始まり(『ジョーズ』が75年、最初の『スター・ウォーズ』が77年)、その勢いが加速するまま80年代に突入した、とざっくり把握してもらえたらいいだろうか(メガヒットの『E.T.』が82年)。
アメリカ映画がブロックバスター化する一方で、インディペンデントにも動きが起きるが、重要なのが1984年だ。カサヴェテスの最後の重要作『ラヴ・ストリームス』が発表され、そしてジム・ジャームッシュ監督『ストレンジャー・ザン・パラダイス』がカンヌで受賞し、まさに一世を風靡することになる。ジャームッシュがアメリカン・インディの雄の称号をカサヴェテスから継いだという形になったのだ。東京での好調なリバイバル公開も記憶に新しいが、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』の影響は当時からいまに至るまで絶大であり、ワンシーン・ワンカット(シーンの合間に挟まれる暗転の秒数を今泉力哉監督はカウントしていたという)、渇いたトーン、粒子の粗いモノクロ映像。そのクールな佇まいに人々はカサヴェテスの影を見出しつつ、身悶えしたのだ。
そして1989年。東のニューヨークから、スパイク・リー監督が渾身の『ドゥ・ザ・ライト・シング』を放つ。黒人監督として無類の発信力を誇ったスパイク・リーは、新しいドアを続々と開けていく時代の寵児となる。同じ89年、西のハリウッドに居を構えるスティーヴン・ソダーバーグは、『セックスと嘘とビデオテープ』でカンヌの最高賞パルムドールを受賞する。ジャームッシュ、スパイク・リー、ソダーバーグというスターが80年代の後半に、アメリカのインディ映画の新たな存在感を一気に高めたのである。
90年代〜:受け入れられたクールネスと刺激性
そして90年代に入ると、米国映画史上、最大のスター監督が登場する。クエンティン・タランティーノである。1992年、アメリカン・インディの牙城とされるサンダンス映画祭に登場した『レザボア・ドッグス』は、全く斬新なスタイルと残酷な描写を持ち合わせ、映画祭の話題を独占する。タランティーノの躍進はこの92年のサンダンス映画祭で注目を浴びたことから始まり、瞬く間に世界的な存在となっていく。こうして、80年代中盤から90年代初頭にかけてのこれら重要監督たちは、時にはロックスターのような扱いを受け(実際に音楽が彼らの作品の重要な要素となるが)、アメリカのインディのクールネスと刺激性を確固たるものにしたのである。
ところで、92年のサンダンス映画祭には、『レザボア・ドッグス』の他にも注目作があった。例えば、アメリカの砂漠地帯に暮らす姉妹と母の生き方をビビッドに描いた『ガス・フード・ロジング』は高い評価を受け、アリソン・アンダース監督は女性監督の旗手として注目される存在となる。さらに、『レザボア・ドッグス』や『ガス・フード・ロジング』を抑えて、92年のサンダンス映画祭で受賞したのが、アレクサンダー・ロックウェル監督の『イン・ザ・スープ』という作品である(ちなみに、賛否が渦巻きつつも本命視された『レザボア・ドッグス』が受賞を逃したことでタランティーノはひどく落胆したらしく、サンダンス映画祭は彼に愛想を付かされないように、審査員で招待するなど翌年から涙ぐましい努力を重ねたと伝えられる)。
『イン・ザ・スープ』こそは、低予算、モノクロ、クール、負け犬の香り、リアルな役者たち、といったアメリカン・インディの刺激的なエッセンスを全て備えた作品であった。NY出身でアメリカン・インディのアイコン的存在と言えるスティーヴ・ブシェミを主演に迎え、売れない映画監督の情けない日常を描き、世界中の粋を集めたような珠玉の逸品である。主演のひとりのシーモア・カッセルはカサヴェテス作品の常連俳優であり、そしてプロデューサー役にジャームッシュが出演していることからも伺えるように、アメリカン・インディのひとつの流れを集約したような作品であり、若きロックウェル監督は王道の継承者と見なされたのである。
不完全燃焼の『フォー・ルームス』。犠牲になったのは、作品と監督の両者であった
さて、(受賞は逃したものの)タランティーノはアンダースやロックウェルと意気投合し、自分たちを「92年組」と称し、新しい波を起こす若手監督の代表格としての自覚を強めていく。そこに93年の『バッド・チューニング』でブレイクしたリチャード・リンクレーター監督や、同じく93年のサンダンスで話題になった『エル・マリアッチ』のロバート・ロドリゲス監督らが加わり、『フォー・ルームス』という作品の企画が立ち上がる。とあるホテルを舞台に、それぞれの監督が短編を作って持ち寄り、1本のオムニバス映画にしたらどうだろうというロックウェルのアイディアにタランティーノは飛びついたのだ(その後リンクレーターが抜けたので、当初のファイブからフォーになった)。かくして気鋭の監督たちによる、時代を切り開く作品が出来る…、はずだった。
1990年代初頭から2017年に至るまで、アメリカのインディ映画はそのあり方を大きく変えたが、その中心にいたのがミラマックスという会社であり、同社を率いたハーヴェイ・ワインスタインという存在である。周知の通り、#MeTooの告発により、2017年にワインスタインは失脚したが、もともと彼の悪名はアメリカ映画業界を超えて世界中に轟いていた。恫喝と恐怖で相手を支配し、脚本と編集を切り刻む切り裂き魔である一方で、強引なマーケティング戦略で数々の作品に脚光を浴びさせてきたのは事実である。従って、90年代から2010年代にかけてのアメリカン・インディの歴史を総括することは今後とても重要で困難な大仕事(誰もワインスタインのことなど思い出したくないのに、その実績が巨大なので無視できない)になるはずだ。本稿ではその荒波をすっ飛ばして現在に来てしまうけれど、ミラマックスの影響力に触れずしてアメリカン・インディを語ることは出来ないことは強調しておきたい。
何が言いたいかというと、『フォー・ルームス』は初期ミラマックスの犠牲者となってしまったのだ。4本の短編を合わせると長すぎると判断したワインスタインは、タランティーノ編はアンタッチャブルであること、そしてロドリゲス編は長廻しショットが多いので切りづらいことを理由に、アンダース編とロックウェル編を大幅に切ることを要求し、実際に自ら切ってしまった。恫喝でしかなかったとアンダースは述懐しているが、ロックウェルにとっても面白いはずがない。おまけにタランティーノが巨大スター化してしまい(『パルプ・フィクション』フィーバーの直後というタイミングだった)、監督たちの間ですら連絡がとれない状態でチームワークもバラバラとなり、作品は興行的にも批評的にも失敗に終わってしまった。
普遍のインディー・スピリットを表現し続けるアレクサンダー・ロックウェル
『イン・ザ・スープ』は傑作であるが商業的成果からは程遠く、そして『フォー・ルームス』の躓きもあったのか、その後のアレクサンダー・ロックウェルが表舞台に出てくることは少なくなってしまう。これは僕の想像だけれども、早々にワインスタインとの付き合いに見切りをつけたこともロックウェルのキャリアに影響を与えた可能性もある。なんといっても、90年代~ゼロ年代のワインスタインの影響力は絶大であったのだから。
ロックウェルはNY大学で映画制作を教える傍ら、98年に次作を撮りはしたが、スティーヴ・ブシェミやジェニファー・ビールズといった仲間たちを主演に作った『13 Moons』(日本未公開)が、ゼロ年代では唯一の長編監督作品となってしまった。
しかし2010年代になると、徐々に製作ペースが上がり、新たな手法とスタイルも手に入れ、「復活」してくるのである。2010年の『ピート・スモールズは死んだ!』は、ピーター・ディンクレイジ扮する主人公が映画とカネの問題で振り回されるという点で『イン・ザ・スープ』と通じており、またもや登場するシーモア・カッセルが「愛の映画を作れ」と主人公相手に語るあたりなど、ロックウェルの変わらぬインディ・スピリットが伺えて、古くからのファンにはたまらない。
そして、2013年に手がけた約1時間の中編『Little Feet』(日本未公開)が、ロックウェルの新境地を開拓する。監督の長女ラナ(当時7歳)と長男ニコ(当時4歳)を起用し、彼らの視点に沿った瑞々しい1日を粗いモノクロ画面で独創的に描き、リアルな描写とクールなルックというアメリカン・インディの伝統を踏襲しながら、ロックウェルは自身の個性を改めて発揮する作風を開花させたのである。ちなみに、同志であるアリソン・アンダースはしばらくテレビを主戦場にした後、ほぼ同じ時期に『ストラッター』(2012)を完成させ、バツグンにクールでロックなモノクロのロードムービーの中で健在ぶりを示してくれており、「92年組」は20年を経て大復活の様相を呈していく。

さて、『Little Feet』から7年が経ち、ラナは15歳、ニコは11歳になった2020年。前作に手ごたえを感じていたロックウェル監督は、ふたたび自らの子どもたちを主演に起用した新作を手掛け、それが『スウィート・シング』という作品となる。2020年のベルリン映画祭でプレミア上映され、「ジェネレーション部門」の作品を見事受賞し、改めてアレクサンダー・ロックウェルの復活を強く印象付けたのである。
監督の長女ラナが演じるのは、ビリーという名の女の子(長男ニコはそのままニコ)。ビリーは弟と怪しい商売で小銭を稼ぎ、ロクな仕事も無い父親の世話をしながら、その日暮らしの生活を送っている。貧しくも明るい日々であったが、父は酒を飲むと人が変わってしまうため、やむなくビリーはニコを連れて家を出る。父を見捨てた母に助けを求めるが、母の家も安住の地ではなかった…。
まずは、粗い粒子でローキーのモノクロ画面が目に飛び込んでくる。スーパー16mmのフィルム撮影に特有の温かい肌触りだ。監督はカラーフィルムで撮影し、そこから色を抜いてモノクロに仕上げたという。その方が、モノクロが安定するからだと監督は説明するが、光の加減を絶妙に調整しながら、どこか輪郭が曖昧であるかのような、クラシカルでタイムレスな雰囲気も狙っており、見事に功を奏している。ビジュアルの美しさはモダンアートのようであり、幾層にも重なる詩情が全体を貫く。
監督は子役を演出する際に、自ら膝を地面に付き、彼らの目線で語りかけ、彼らが自由に動き出すことを促すという。観客は、ナチュラルな存在感で魅了するビリーとニコの目線に寄り添い、彼らの喜びと恐怖に同化し、登場する大人の醜さに自らを恥じ入り、無垢な子ども時代へのノスタルジアを感じることにもなるだろう。そしてモノクロの映像と、絶妙に配された音楽が、観客のエモーションをさらに揺さぶっていく。

劇中のビリーは、ビリー・ホリデイにちなんで名付けられている。そのビリー・ホリデイは少女ビリーの守護天使として度々登場する。黒人の苦難を歌い続けたビリー・ホリデイは、苦境においても前向きに生きる支えとして少女ビリーの心に現れるのだ。ビリー・ホリデイが歌うのは”I’ve got my love to keep me warm ”––「風が吹いて、雪が降って、寒さが辛くても、愛があるから大丈夫」という内容の温かい曲である。クリスマスソングでもあり、しんどいクリスマスを経験するビリーとニコに寄り添うには、ぴったりの曲だ。
そして、映画のタイトルにもなっているのが、ヴァン・モリソンの「スウィート・シング」。ロックの歴史的名アルバムの1枚に挙げられる「アストラル・ウィークス」に収録されている。1968年に発表された「アストラル・ウィークス」は、ロックとジャズとブルースとフォークなどの多種の音楽ジャンルを混ぜ合わせたコンセプト・アルバムとして画期的な作品だ。難解と評されることもあり、ヴァン・モリソンという魂のミュージシャンによる全編が流れる河のような圧倒的な名盤であるが、確かに歌詞の内容を理解するのは簡単ではない。その中で、「スウィート・シング」は清涼剤のような佇まいで3曲目に位置し、モリソンの子ども時代の心象風景が歌われ、まさに映像が立ち上がってくるような名曲と呼んで間違いない。
特定の相手に捧げるラブソングというよりは、子ども時代の光景を呼び起こしながら、愛という感情に対するプリミティブな喜びを噛みしめるような歌と言えばいいだろうか。「海に浮かぶ船を眺め、雨に濡れた庭を歩き、そして愛しい君を想う」という歌詞は、初恋に近い感情をかき立て、そして印象的なリフレインは”And I will never, never grow so old again ”と歌われる。「決して大人になんかならない」と大人の視点で歌うのだ。子どもの目線と大人のノスタルジアが同居する映画『スウィート・シング』は、この名曲を土台にしていることが良く分かる。
ビリーは、「スウィート・シング」を口ずさむ。ニコを落ち着かせる子守歌として歌うこともある。子どもが歌うと、素直に子どもの歌になるのがこの曲の魅力のひとつだ。しかし、映画『スウィート・シング』が子どもと大人の断絶の残酷さを見事に晒すのは、ヴァン・モリソンが歌う「スウィート・シング」が流れる場面である。酒に溺れ、どん底でもがく父親の醜悪な姿を回想するシーンで、この美しい曲が流れる。その痛烈な皮肉に、胸が張り裂けそうになる。『グッドモーニング、ベトナム』(1987/アレックス・ノース監督)の中で、凄惨な殺戮シーンにルイ・アームストロングの甘美な「この素晴らしき世界」が流れる時の衝撃が想起されるが、時に映画は、残酷さを描くために美しさを利用することがあることを思い知らされる。

しかし、『スウィート・シング』の後半は、ロードムービー的に展開し、子どもたちは大人たちから離れ、フロリダを目指す。若者の逃避行という面で『地獄の逃避行』(1973/テレンス・マリック監督)を連想させるし、子どもたちが線路沿いを歩く場面はもちろん『スタンド・バイ・ミー』(1986/ロブ・ライナー監督)への目配せだ。このように、アレクサンダー・ロックウェルは音楽や映画を自在に取り込み、妻や子どもたちを積極的に起用したジョン・カサヴェテスの映画制作スタンスを自家薬籠中のものとし、粗くも美しいモノクロの映像を駆使し、アメリカン・インディの魅力の神髄を現在に伝えてくれるのである。
『スウィート・シング』の重要性は、アメリカン・インディの魅力に溢れているということだけでなく、アクチュアルな主題を備えている点にもあることを強調しないといけないだろう。
ビリーとニコは、大人という壁に直面する。大人たちはみな身勝手であり、抑圧的であり、やがて不可避的に虐待へと向かう。残忍な大人という絶対悪に遭遇した時、子どもはどうすればいいのか。逃げる、というのは確かな選択肢だろう。物理的に逃げることも必要であるし、実際にビリーとニコは逃げる。そして、想像力を駆使し、物語の力を借りて、頭の中で逃走することも可能だろう。『スウィート・シング』の大人たちは、一様に傷つき、痛みと悲しみを抱える存在として描かれる。大人たちを癒すのが子どもたちであり、純粋でイノセンスな彼らの存在は希望となる。しかし、本来は逆であるべきで、子どもたちを癒し、希望を与えるのが大人でなければならないのではないか。
ロックウェル監督は、いまの世の中と大人たちに警鐘を鳴らし、そして子どもたちには、必要な時には物語の力を借りてどんどん「逃げろ」と語りかけてくるようだ。想像と創造、そこにアートの力がある。真のインディのスピリットとは、アートの力を信じることに尽きるのかもしれない。『スウィート・シング』はそのように語りかけてくるように感じられてならないのである。
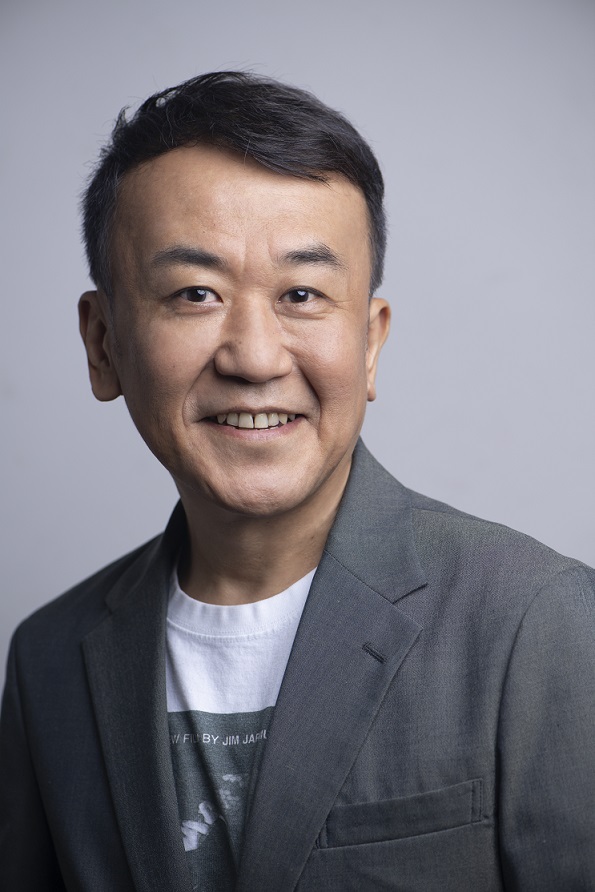
矢田部吉彦
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
