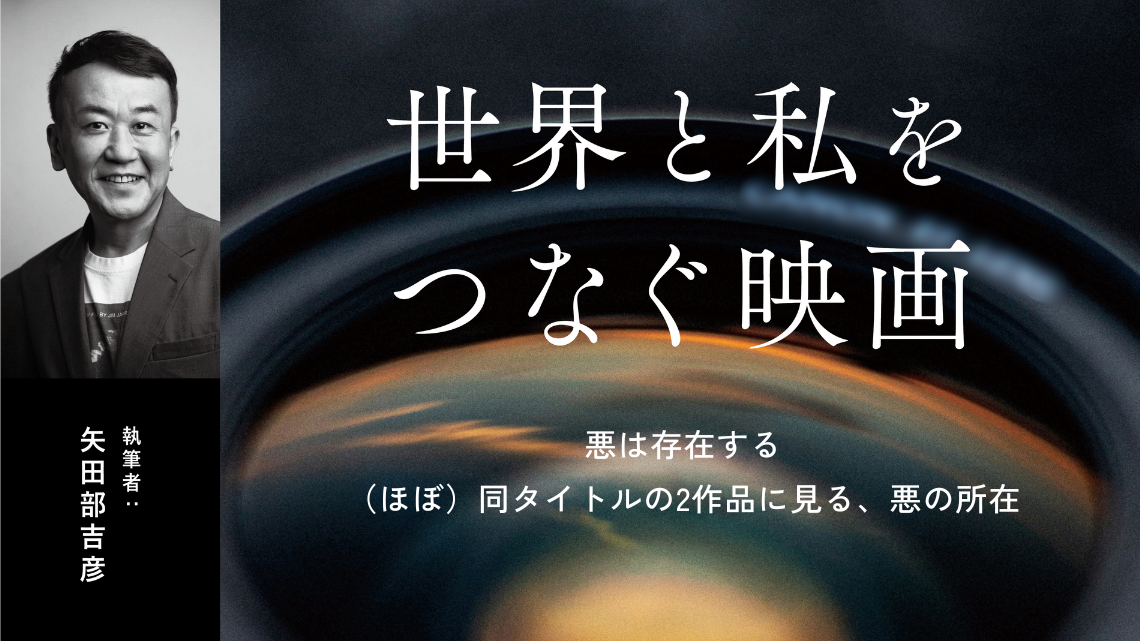
※本コラムは、映画作品の内容に言及しています
奇しくも、ほぼ同様の題名を掲げる映画が近年2本存在する。1本はイラン、1本は日本。全く関連の無い2本だが、「悪」を描くという点と、いずれも傑作であるという点で共通している。2作が描く「悪」とは何なのか、ちょっと考えてみた。
『悪は存在せず』/イラン
2020年のベルリン映画祭で最高賞の「金熊賞」を受賞したのは、イランのモハマド・ラスロフ監督による『There Is No Evil』だった。2024年5月現在で日本での公開は実現していないが、20年に東京国際映画祭で上映した際に『悪は存在せず』との邦題を付けた。イランにおける死刑制度を多角的に見つめる作品であり、4人の人物の視点による、互いに独立した4つの短編から構成されている。
1話目は、役所の業務として死刑執行に関わり、機械的に「ボタン」を押しているが、内面は深く病んでしまっている死刑執行官。2話目は、死刑に立ち会う指令を断固として拒む兵士。3話目は、死刑に立ち会うことで得られる特別休暇を目当てにその業務を引き受け、結果として愛する人の大切な存在を葬ってしまった兵士。4話目は、30年前に兵役から脱走した男の、その後の人生。
死刑制度を巡る非常にヘヴィーな作品であるが、各短編がもたらすインパクトの強さとストーリーテリングの巧みさが際立ち、極めて完成度の高い作品である。優れた短編のお手本のような4本を通じ、死刑制度が存在する以上、そこには制度執行の実務に関わる人間がいるのであり、その人間の数だけ物語が存在するのだという、当たり前の事実を痛感する。
イランでは、長編の製作は検閲も厳しく、何かと目立ってしまうため、『悪は存在せず』は短編を作っていると見せかけたのだと、ラスロフ監督は語っている。つまり、姿勢を低くして目立たないようにスピーディーに短編を4本作り、それを合体させて1本の短編オムニバス長編に仕上げたということだ。
そうまでしても現在のイランの体制をあるがままに描こうとする反骨の精神たるや、日本でのうのうと暮らす自分に想像が及ぶはずも無いが、世界で最も重要な映画作家の1人と呼ぶことに何のためらいもない。
モハマッド・ラスロフ監督は、そのキャリアにおいて、作品を通じてイラン政府を批判しているとされ、イラン当局に幾度も身柄を拘束された経験を有している。自宅軟禁、あるいは刑務所監禁となったり、拘束が解かれたとしても、出国を禁止されたりすることがしばしばで、金熊賞を受賞した20年のベルリン映画祭に本人の参加は叶わなかった。
24年のカンヌ映画祭にも新作がコンペティション部門に選出されているが、当局からは出品を止めるように圧力がかかっていると報道された。さらにこの度、ラスロフ監督に対し、鞭打ちと財産没収に加え、8年の実刑が言い渡されたと弁護士が明らかにした旨がニュースに出た(5月9日)。あまりの衝撃的内容に言葉を失う。カンヌへの来場は叶わないだろう。その不在をカンヌがアピールし、世界が状況を認識することで逆にイランに圧力がかかる効果を期待するしかない。
(※追記:5月13日、ラスロフ監督がイランを脱出しヨーロッパの某所に身を潜めているとの報道があった。監督の無事を心から祝福すると同時に、カンヌに登場するかどうか、見守りたい)
ところで、イランの死刑制度の闇は、映画作家がリスクを冒してでも指摘したい主題であるらしい。ベタシュ・サナイハ、マリヤム・モガッダムの共同監督は、『白い牛のバラッド』(21)において、夫を死刑で失った後にそれが冤罪であったことを知らされる妻と、死刑を宣告した裁判官の男性との交流を描いた(妻は男性の正体を知らない)。サスペンスフルな心理ドラマであり、こちらも非常に優れた作品であるが、ずさんな死刑制度の告発が主旨であることは明らかだった。21年のベルリン映画祭でワールドプレミアされた後、作品はイラン国内で上映されることはなく、2人の監督は当局から国外渡航禁止処分を受け、新作がプレミア上映された24年のベルリン映画祭にも姿を現すことはできなかった。
社会のシステムとして存在している死刑制度の是非論に踏み込むのではなく、そこに関わる人間が壊れてしまう様子が物語を用いて描かれる点で、『悪は存在せず』と『白い牛のバラッド』は共通している。しかし、『白い牛のバラッド』が死刑で身内を失った側の視点が中心になっているのに対し、『悪は存在せず』の場合は、(留まるにせよ、逃走するにせよ)執行側の人間にのみ焦点を当てているのが特徴だ。冤罪もありうる死刑制度を業務として執行する末端の人間は、悪なのかどうか。死刑制度が悪でありうるのは、冤罪の可能性だけが理由ではないだろうが、その議論には踏み込まないとして、存在してしまっている制度が要求する業務に携わっている人に悪は還元できるか。
ナチの悪魔の所業を実行した責任者は完全に思考を停止していたという点において悪魔的であるというよりは凡庸であり、だからこそその悪の伝播は恐ろしいという状況を、ハンナ・アーレントが「凡庸な悪」と評したことが、もちろんここで想起される。
『悪は存在せず』の第1話の主人公は、家族想いの父親であり、何ら特別なことのない私生活を送っているが、心の一部が完全に死んでいることをごまかすために薬の服用が不可欠になっている。職場では音楽をかけて気楽な仕事に見せかけるが、壁のライトがグリーンに点灯すると、彼は壁のボタンを押し、すると別部屋で10名ほどの死刑囚が一斉に宙づりになり、死ぬ。
『悪は存在せず』の第1話は、「凡庸な悪」の概念を映画化したものだ(近作では23年のジョナサン・グレイザー監督『関心領域』もその系譜にある)。第2話以降においても、「悪」の周辺にいる人々の物語が、「悪」のあり方について深く考えるように訴えてくる。つまり、『There Is No Evil = 悪は存在せず』は、システムの歯車の1人に悪を見出すことの複雑さを問うことを通じてシステムの巨悪さを意識させる、逆説的なタイトルとして機能している。もちろん、悪は存在するのだ。
『悪は存在しない』/日本
濱口隆介監督による『悪は存在しない』(23)の英語タイトルは、『Evil Does Not Exist』である。タイトルが逆説的に付けられたイランの『悪は存在せず』の例にならえば、日本の『悪は存在しない』も、悪は存在するという意味なのだと考えた方が理解しやすいのかもしれない。しかしそこはさすが濱口監督、幾層にも工夫とミスリードをまぶし、観客を快楽と困惑の旅へと誘う。
『悪は存在しない』において、表面的に悪の対象となるのは、環境破壊である。信州の山間の村にグランピング施設が開発される計画があり、住民向けに説明会が開かれる。東京から、都会的な雰囲気をまとった男女がやってきて、開発計画を説明する。
グランピング施設は芸能事務所の副業であり、コロナの補助金目当ての事業であることが明らかな状況のなか、男女社員の説明は早々に行き詰り、住民のロジカルな質問や疑念の提示にたじたじとなっていく。この辺りは、不利に見えた側が切れ味鋭い反論で立場を逆転させていくという裁判ドラマから得られるものに近い快感が得られ、とても気持ちがいい。
ここには、「都会の開発業者=搾取する側」が、「地元住民=搾取される側」を下に見ていた状況が逆転していくというパワー・バランスの逆転を見ることができるのであり、パワー・バランスの逆転は常に観客の関心を引っ張り、ドラマを推進させる力となる。グランピング施設によって汚染されるリスクのある水の大切さを訴えるメッセージは当然込められているが、環境問題そのものよりも、セリフの説得力や役者の巧みさに魅了される場面だ。たぶん、環境問題が濱口監督の第一の関心事ではない、と察せられる(もちろん重視していることに疑いは無いけれど)。
通常見られがちな、いわゆるステレオタイプのパターンとして、都会の開発業者が絵に描いたような悪人で、地元住民をイジメ続けるというものがある。しかし、『悪は存在しない』では、都会の男女は一般的な常識を備えた人物たちとして描かれ、説明会で住民から受けた指摘を真摯に受け止め、会社に計画の見直しを迫りさえする。しかし、「このままでは従業員の賃金も払えなくなるんだぞ」と、社長に迫られ、地元の重要人物を味方に取り込むべく再び山間地に向かう羽目になる。その車中で、男女の社員はリラックスして互いの身の上を語り合い、2人は好感の持てる普通の人たちだと観客は改めて安心する。男は現在の仕事を続けるべきか悩んでおり、女は前職が介護士であったことが語られる。
ここで、ああ、やはり「悪は存在しない」のだ、映画やドラマで見るような極端な悪人などは存在せず、濱口監督は紋切り型を避けてさすがだと、いったんは思う。
しかし、どうやらそこでは終わらない。東京の社員が味方につけようとするのは、地元で一目置かれているタクミ(巧)という男で、職業こそ便利屋であるが、森や山を知り尽くす人物であり、自然の守護者として存在している。妻はいないらしく、幼い娘のハナと2人で暮らしている。日常的に薪を割り、川から水を汲み、地元の自然を熟知しているが、唯一の欠点は時間を忘れがちなことで、ハナの下校の迎えにしばしば遅れてしまう。
地元の人の事情に寄り添うべきだと改心した東京の男女の社員は、その気持ちを素直にタクミに伝える。タクミもガードを下げたように思えた。しかしグランピング施設の建設予定地は野生の鹿の通り道であり、鹿がジャンプしても入れないほどの高い塀で囲まれた施設に人が来るだろうかという決定的な指摘に、男女社員は言葉を失う。
男女社員は川の水汲みを手伝い、タクミとさらに距離を縮めたように見えるが、その後の車内の会話で雲行きが変わる。野生の鹿は臆病であり、手負いの状態にならないと人に危害を与えることは無いとタクミが説明すると、女性社員は、ならばグランピング施設で客が鹿に接するのは良い体験になるのではないかと軽率な発言をする。さらに、その場所を通れなくなった鹿はどこに向かうのかというタクミの問いに対し、男性社員は、どこか別のところに行くのではと、完全に思慮を欠いた返答をする。タクミは、車内であるに関わらず無言でタバコに火をつけ、社員たちとの断絶を表現する。
自然の摂理を曲げることに対する思慮の浅はかさを、タクミは許さない。あるいは、自然は許さない。反射的に自然を軽んじてしまうのは、著しく思慮を欠くという点で「凡庸な悪」に通じるのだ。
女性の社員は、前職が介護士であることで、善人に違いないと観客は先入観を抱いているため、軽率な発言による「悪人」への転落から受けるギャップは大きい。誠実で真面目そうな外見に加え、前職が介護士というダメ押しの背景を女性社員に与えた濱口監督は本当に上手い。ここに悪が存在しているのかどうか、見過ごしてしまいそうな些細なやり取りではあるが、思考停止による自然の摂理の軽視は、女性社員を悪なる存在に貶める。
タクミの娘のハナが失踪し、男女社員とタクミは森を探すことになるが、女性社員は木の枝の棘が手のひらに刺さり、ざっくりと出血する形で自然から罰せられる。
地元住民が総出でハナを探すが、見つからない。日が暮れて来る。薄暮の中、タクミと男性社員は、害獣駆除の結果なのか、銃で撃たれた鹿と向き合っているハナを見つける。男性社員が駆け寄ろうとすると、タクミは男を後ろから羽交い絞めにし、首を絞めて殺そうとする。本作最大の驚きの場面である。観客は全く予想していなかったタクミの行為に愕然とする。この場面は、ほぼ日が暮れたはずの時間帯にしては不思議に明るく、現実の場面ではないとの解釈も出来るが、あえて解釈の余地を広く残すための演出であると理解する。
害獣駆除としての鹿狩りは、悪なのか。人間側の事情はともかく、自然の摂理からすれば、少なくとも善ではないだろう。銃撃され、手負いとなった鹿に、ハナは襲われた。悪の所業の結果としてハナは襲われてしまった。父親であり、そして自然の守護者であるタクミにとって、鹿の行動など自分の知ったことではないというニュアンスを含んだ発言で自然を無意識に軽視し、悪の象徴となって目の前に立っている男性社員を殺して報いを与えることは、当然の行為だったのだ。
実際にハナに何があったのか、そして男性社員が本当に死んだのか、映画は曖昧なままにしている。何故なら、悪の所在とその所業について、明確にし過ぎてしまうのは、観客の思考停止にも繋がりかねないからである。
思考停止にこそ悪は潜んでいるのであり、我々は考え続けなければいけないのである。
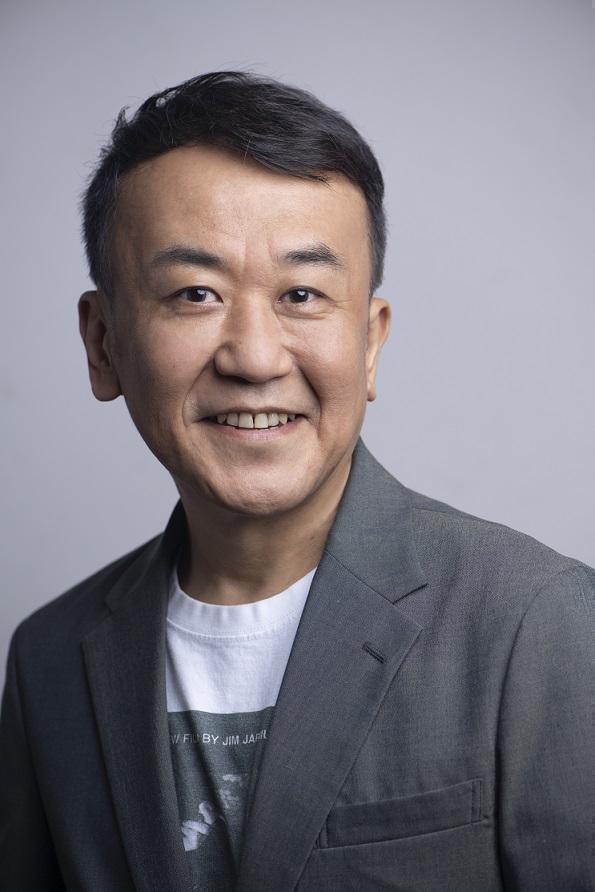
矢田部吉彦(やたべ・よしひこ)
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
