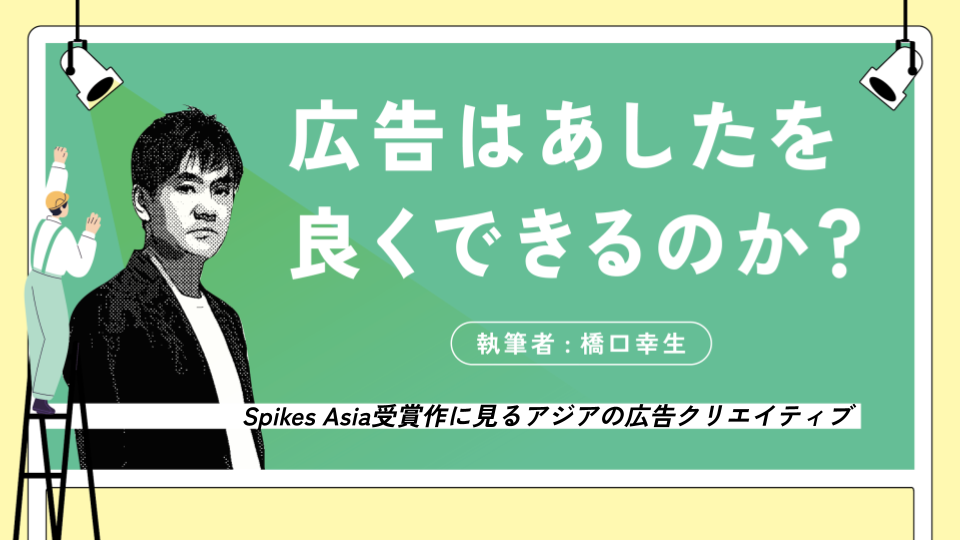
広告クリエイティブの中心は、今でも欧米圏だ。カンヌライオンズはフランス(事務局はロンドン)、The One ShowやClio Awardsはニューヨークなど、「世界三大広告賞」と呼ばれる権威のあるアワードは、どれも欧米で開催される。ナイキ、アップル、P&Gなど、有名な広告主の多くも、欧米に拠点を持っている。この連載でも、欧米の事例を取り上げることが多い。筆者自身も、欧米の広告クリエイティブに対して憧れとリスペクトを抱いている。
しかし世界情勢を見ると、欧米先進国の影響力は相対的に弱まっている。G7のGDPは発足した1970年代半ばには世界の6割強を占めていたが、現在は4割台にまで低下している。人口シェアでは世界のわずか10%に過ぎない。
一方、「グローバルサウス」と呼ばれる国々が存在感を高めている。経済、社会インフラ、民主主義の成熟度などにおいて、現時点では欧米先進国と見劣りするものの、新興市場としての高いポテンシャルが注目されているのだ。
このことは、広告クリエイティブにも現れている。かつて国際広告賞では非欧米圏の受賞作は少なかった。たまに評価されても、その物珍しさが(言葉は悪いが)「珍獣」として愛でられていた側面は否定できない。しかし近年は、欧米と比べても見劣りしないクリエイティビティを持つ事例が登場してきている。
そこで今回は、2024年3月に発表されたアジアの広告賞Spikes Asia 2024(※1)の受賞作を紹介しながら、アジアの広告クリエイティブについて考えてみたい。
※1 参考:スパイクスアジアは、ヨーロッパのEurobest(ユーロベスト)、中東のDubai Lynx(ドバイリンクス)と共に、カンヌライオンズの地域版フェスティバルとして、毎年シンガポールで開催されるアジア太平洋地域を対象とした、アジア地域最大級の広告コミュニケーションフェスティバル。
https://www.canneslionsjapan.com/spikesasia/
「世界最大の民主主義国」インドの広告クリエイティブ

インドは、ロシアによるウクライナ侵略に際してロシアを明確に批判せず、友好関係を保ち続けている国だ。女性に対する痛ましい性暴力事件がたびたび起きていることでも有名だ。現首相のモディ氏は2014年から10年間という長期にわたり首相を務めている。多数派であるヒンドゥー教を優遇する一方イスラム教徒に認められてきた自治権を撤廃するなど、その政策は賛否が分かれている。インドに民主主義陣営の一員というイメージを抱く人は、それほど多くないだろう。
しかし、インドが世界最大の民主主義国であることは、紛れもない事実だ。今年実施される総選挙では約10億人が投票資格を持ち、19年の選挙で各政党・候補者・規制当局合わせた選挙費用の86億ドルを上回る費用がかかると予想されているから、なにもかもがケタ違いだ。広告にも、民主主義国家としての価値観を感じさせる事例が少なくない。代表的なものをいくつか紹介しよう。
新聞社による環境保護キャンペーン#Unplasticindia
インドでは、政府が使い捨てプラスチックの使用を禁止したにも関わらず、プラスチックによる環境汚染が悪化している。年間940万トンのプラスチック廃棄物が、海洋生態系にダメージを与えているのだ。この問題に警鐘を鳴らすために英字新聞「タイムズ・オブ・インディア」が行ったのが、#UnplasticIndiaキャンペーンだ。世界環境デーに合わせて、強烈なビジュアルの新聞広告を公開した。
ペットボトルの口のように、ペンギンが首元をぎゅっと捻られている
ペットボトルの使い捨てが、海の生き物たちの生存を脅かすことがひと目で伝わる、強烈なビジュアルだ。この広告はソーシャルメディアで7100万以上のインプレッションを記録し、50万人以上が使い捨てプラスチックの使用をやめることを誓約したという。高度経済成長の国にあっても、環境問題をなおざりにさせない。そんな「タイムズ・オブ・ア・ベターインディア」のクオリティ・ペーパーとしての気概が、#Unplasticindiaからは伝わってくる。
洗剤ブランドが提唱する家事シェアキャンペーン
洗剤ブランドのアリエルは、女性ばかりが家事を負担する状況の変化を訴えるキャンペーン #ShareTheLoadを、もう8年間も続けている。その最新作となる長編コマーシャルが「静かなる別離」(”Silent Separation”)だ。
アリエルは女性の81%が不公平な家事分担が夫婦関係に悪影響だと感じていることに注目。夫が妻に家事を押し付け続けた結果、夫婦関係が冷え切ってしまう現象を”静かなる別離”と名付け、夫も家事に参加することを呼びかけた。キャンペーンの結果ブランドの販売成長率は35%を記録、新規ユーザーは1,040万人に達したという。
性暴力やハラスメント、農村部における教育アクセス、女児の選択的中絶など、インドにおける女性の人権の状況には課題が多い。しかし、そんな状況を変えるための広告が8年間続けられ、人びとからも支持されていることは覚えておきたい。
女性への暴力に、アートディレクションで抗議
2022年9月22日、イラン人女性のマフサ・アミニが、ヒジャブから髪の毛が出ていた・タイトなズボンを履いていた、という理由で殴打され、殺害された。実行したのは、イラン内務省の管轄下にあり、イスラム法に基づく行動規範を強制する任務を担う道徳警察だ。
この蛮行に対してイラン全土で抗議行動が起こったが、政府はこれを弾圧。500人以上が死亡し、数百人が負傷、数千人1が逮捕された(※2)。多くの国がイランを非難する声明を発表したが、インド政府は沈黙を守った。そこでインドの建築、デザイン、アートの専門誌Stir Magazineが行ったキャンペーンが、”Untangling the Politics of Hair.”だ。
女性が髪の毛でがんじがらめになっているフォトエッセイは話題を呼び、アジア最大のアートフェアであるインディア・アート・フェアの招待展示となった。さらにフランス大使や国連インド代表からも展示開催の呼びかけがあったという。
これらインドの広告を見ていて感じるのは、問題を問題としてストレートにとらえる国民性だ。このことは日本の広告と比較すると、分かりやすい。最近は日本でも、洗剤の広告では男性タレントが起用されることが当たり前になっている。それは日本人なりの「男も家事をやろう」というメッセージではあるのだが、アリエルの広告のように、不公平な家事負担に苦しむ女性が直接描かれることはない。#UnplasticindiaやStir Magazineのようなショッキングなビジュアルも、日本の広告で目にする機会はほとんどない。
どちらが良い悪いかは別として、インド人のストレートな表現方法の方が、欧米先進国のそれと近いことは確かだ。欧米のソーシャルグッド型キャンペーンでは、社会の不公正を明示した上で、それを打破するためのアイデアが提示される構造になっていることが多い。
グーグルを傘下に持つアルファベット、ユ-チューブ、マイクロソフトにIBM、スターバックス、シャネル、FedExなど、現在、欧米圏の大企業の多くがインド出身者をトップに据えている。その背景には、問題を問題としてストレートにとらえるインド人の国民性があるのかもしれない。
※2 参考:ロイター「アングル:アミニさんの急死から1年、イラン国内の変化は」(2023年9月16日)https://jp.reuters.com/world/us/CWVZVCKACFKBFPT6WPMS2XN5IM-2023-09-15/
テクノロジーに人間性を
前回の記事では、本来は行政が担うべき仕事に広告としてチャレンジした、ドミノピザとマスターカードの事例を紹介した。今回はアジアにおける同様の取り組みを紹介したい。
台湾の臓器移植の成功例は1000万人あたり10件で、スペイン(1000万人あたり50件)、ポルトガル(1000万人あたり30件)などの国々に大きく遅れをとっていた。原因は、臓器提供時の親族の同意プロセスにある。ドナーが生前、臓器提供の同意書に署名していても、実際の移植に際して親族の同意が必要とされる。しかし、愛する家族を失い悲嘆に暮れる親族は現実を受け入れられず、拒否する事が多いのだ。
そこで台湾の保健福祉省および臓器共有登録所、患者自律推進センターは、「Hear My Last Wish」というシステムを2023年に公開した。
このシステムによって、ドナーは臓器提供に同意していることを家族に伝える自分自身の音声を、データとして記録できるようになった。音声データは台湾の国民健康保険データベース(NHID)に紐づけられる。ドナーが死亡すると、医師は病院の臓器寄付交渉室でドナーの「最後の願い」を再生して、親族から同意を求めることができる。
「Hear My Last Wish」の導入によって、臓器寄付の同意署名は2023年12月までに127%増加した。ドナーの84%以上が「最後の願い」を録音し、3567件以上の臓器提供の音声データが作成された。 2023年の臓器提供の成功例は、前年から34.6%増加し、10年間で最高記録に達したという。
カリスマ的なIT大臣オードリー・タンの存在もあり、台湾はテクノロジーの国という印象が強い。しかし、真に注目すべきなのはテクノロジーだけではなく、その活用方法の巧みさだ。効率を求めて同意書をデジタル化するだけでは、臓器提供は成功しない。臓器提供とは生と死が交差する人間にとって究極の選択であり、合理性ではなく感情で大きく左右されるからだ。同意書1枚で決断を迫るのは、愛する人を失った親族にとって心の負担があまりに大きく、倫理的にも問題がある。そこでドナーの「最後の願い」を音声として残しておくというのは、人間的で愛情のある解決方法だと思う。
「Hear My Last Wish」は広告会社のレオ・バーネット台北が開発にかかわっている。行政手続きというと、官僚的で無味乾燥なイメージが強い。しかし、結婚、出産、引っ越し、そして死など…行政が扱うのは、人生そのものだ。人間の心の機微やインサイトを知り尽くした広告クリエイターが行政に関わる機会は、これからどんどん増えていくだろう。
健在なアジア的カオス感

ここまでは、問題意識と表現の両方において、欧米でも違和感なく通用しそうな事例を紹介してきた。しかし、アジアのクリエイティブが完全に欧米化されたわけではない。たとえば、こんなCMがある。(5分近くある上に序盤はやや退屈だが、後半に行くにつれてどんどんテンションが上がるので、ぜひ離脱しないで最後まで見てほしい)
不動産会社のサマコーンは、税務署を意味する「サンパコーン」と名前が似ている。そのため、税金の問い合わせがサマコーンに寄せられたり、従業員が税務職員と間違えられたりするトラブルが起きていた。このことを逆手に取り、社名を連呼して覚えさせる目的でつくられたのがこのCMだ。後半はどさくさに紛れて、サマコーンが販売する住宅商品の名称まで連発している。
企業名を連呼するCMは、日本のテレビでもよく見かける。しかし、ここまで極端なものは滅多にない。あまりにあけすけなやり方が、かえって清々しく感じる。
サマコーンのCMには、この連載で取り上げてきたような社会性はない。映像作品としてのルックも、欧米の一流ブランドのCMのように洗練されていない。冒頭に書いた「珍獣」という言葉が思い浮かんだ人もいるだろう。しかし、そこに抗うことが難しい野放図でカオスな魅力があるのも、また事実だ。このCMを見た誰もがサマコーンの名前を覚えて、好きになってしまうと思う。つまり、広告として極めて完成度が高いのだ。
このCMはSpikes Asiaのオンラインフィルム部門でグランプリを受賞している。この記事で紹介した他の事例もグランプリもしくはゴールドを受賞しているので、広告として同等の評価を受けたことになる。こうした事態は、カンヌライオンズのような欧米の広告アワードでは考えにくい。欧米でグランプリを受賞するのは、ソーシャルグッド事例が大半だ。CM部門ではコミカルな受賞作もあるが、それでも映像はもう少し洗練されている。そして、サマコーンCMがグランプリを受賞することこそが、アジアの広告クリエイティブの特徴であり強みであると筆者は考えている。
今後、アジアのクリエイティブは「独自の変化」を遂げる
ジェンダー平等、環境保護、人権重視といった欧米先進国の長所を、確実にアジアの広告クリエイティブは血肉にしている。しかし、それでいて欧米のやり方をそのまま模倣しているわけではない。かつて「珍獣」と称されたカオティックな魅力は今なお健在だ。今後アジアの広告クリエイティブは、欧米の長所とアジアらしさを融合した「良いとこどり」をして、独自の進化を遂げるだろう。アジア諸国の社会的・経済的地位の向上に伴い、アジアの広告クリエイティブも「珍獣」から「猛獣」に進化して、世界からリスペクトされるようになるはずだ。
アジアに位置しながらG7の一員として欧米先進国ともつながりがある日本にとって、チャンスに満ちた時代が訪れようとしている。

橋口 幸生
クリエイティブ・ディレクター、コピーライター。最近の代表作はNetflixシリーズ三体「お前たちは、虫けらだ」キャンペーン、ニデック「ニデックって、なんなのさ?」伊藤忠商事「キミのなりたいものっ展 with Barbie」、世界えん罪の日新聞広告など。『100案思考』『言葉ダイエット』著者。TCC会員。趣味は映画鑑賞&格闘技観戦。
https://twitter.com/yukio8494
文:橋口幸生
編集:Mizuki Takeuchi
