
私はハリウッドの作るロマンティック・コメディ映画の大ファンです。
ちょうど大学生の頃がメグ・ライアンの全盛期で、彼女が監督/脚本家のノーラ・エフロンと組んで次々とヒット作を放っていました。『恋人たちの予感』(1989)でニューヨークの勝気なキャリア・ウーマンを演じるメグ・ライアンはとてもキュートでした。ノーラ・エフロンの書くセリフはどれも洒落ていて、かつ真実味があり、ファッションやインテリアといったディテールの趣味が良くて、見ているだけで幸せな気持ちになったのを覚えています。20歳の頃にそういう視点を自分で意識していた訳ではないけれど、いま考えると、ビリー・クリスタル演じる相手役とメグ・ライアンのヒロインが、丁々発止のやり取りの中で平等な関係性を探っていく様子が何よりも魅力として映ったのでしょう。
新たに文庫で復刊された氷室冴子さんの『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫、2021)に収録されている「シュプレヒコールの歌」というエッセイを読んで、その頃のことを思い出しました。
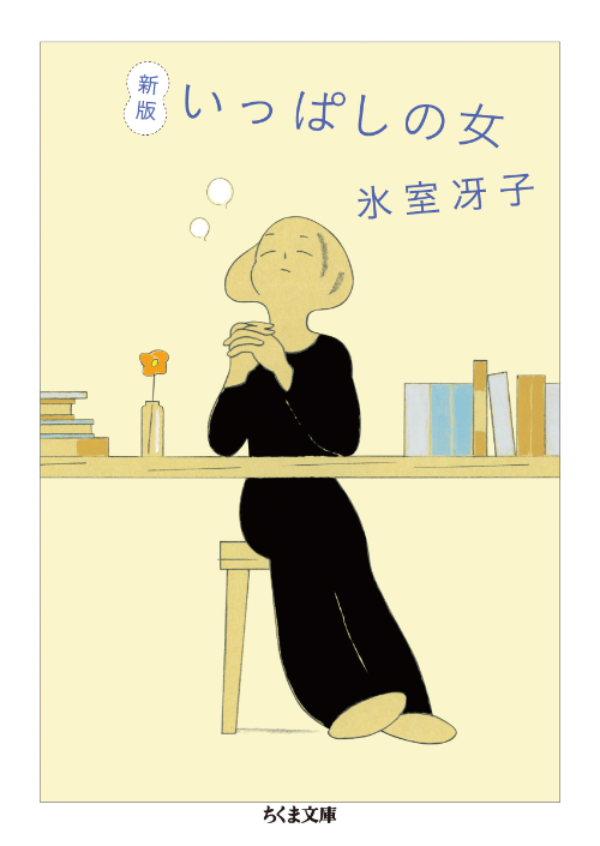
”ロマコメ”が描くのは、男女が理想的な関係性を築くまでのシミュレーション
『いっぱしの女』は少女小説の大家である氷室さんが1992年に発表したエッセイ集です。“立派な大人”として扱われるべき“いっぱしの女”であるところの彼女が世間から、取り分け男性たちから向けられる視線の理不尽さや、それによって感じる違和感といったものを、軽やかに、痒い所に手が届くような細やかさで、かつユーモラスに綴った内容は、いまも色褪せることがありません。「シュプレヒコールの歌」の中で氷室さんは有名なフォーク歌手のとある曲について、「田渕由美子さんが描くところの、オトメチックな少女漫画のエッセンスだけをイタダキして歌詞化したような世界」だったと批判して、こうも書いています。
「オトメチックという、出版社の編集部の片すみでだれかが考えだしたコピーは、いろいろな意味で誤解されていて、そのためオトメチック漫画なるものも不当に誤解されているのだけれど、今読み返すと、あの一群の少女漫画の、すくなくとも田淵さんクラスの作家が描いた作品には、ひとつの思想があった。
それは、同世代の男の子と女の子がどうやって親密になり、理想的な関係性をつくっていけるかのシミュレーションだったのだ」
私がノーラ・エフロンの映画に感じていたことも、まさにこれでした。そして“ロマコメ”というだけで彼女の監督作品が“誤解されて”いると憤ってもいたのです。
「安易なつくりでワンパターン」と誤解されてしまう歯がゆさ
“オトメチックな漫画”に対する世間の扱いに関しては、(やはり不当な扱いを受ける機会の多い)少女小説の分野で活躍した氷室冴子さんには思うところがあったのでしょう。日本の少女漫画は才能の宝庫で、ジャンルも幅広く、漫画という枠を超えて、男性の評論家や文化人に評価される。しかし“オトメチックな漫画”は、“オトメチック”であるがゆえに軽んじられ、そのジャンルにおける優劣の差も分からない人に一括りにされることが多い。何となく「こういうワンパターンなものだろう」という漠然としたイメージで語られたりする。そのことについての歯がゆさ。ロマンティック・コメディ映画の信奉者である私には、痛いほど理解できます。
何せ、(いまは違うと信じていますが)私が若い頃は「ロマンティック・コメディが好き」と言おうものなら、マニアックな映画ファンに笑われる時代だったのです。ターゲットである(ちょろい)女性観客を喜ばせる安易な作りで、ストーリーはいつも同じで、男女が結ばれる決まりきった結末。商業主義と深く結びついたロマンティック・ラブ・イデオロギーに毒されている。そんな風にジャンル全体を貶されることも少なくありませんでした。

もちろん、ロマンティック・コメディの中にはジャンルのお約束ごとにあぐらをかいているような悪しき作品もあります。でも私としては、そういう映画を、ノーラ・エフロンやナンシー・マイヤーズの監督作と一緒にしてもらっては困るのです。氷室さんも“オトメチックな漫画”について、(田渕由美子さん以降に)出てきた亜流作品は「未熟なガキ同士の思いこみラブ=オトメチック・ラブコメみたいになっちゃって、私は一時期、田渕由美子さんのために、ひそかに泣いてたものであった」と語っています。
その一方で、自分の好きなロマコメ作品が当時の映画マニアの評価軸で“この作品ならばお墨付きを与えてあげてもいい”と上から目線で誉められると複雑な気持ちでした。30年代や40年代の巨匠たちが撮ったスクリューボール・コメディを、現代のロマコメよりも一段上のものとして扱う傾向にも違和感がありました。クラシック映画でも現代のものでも、私にとっては同じように、ロマンティックで楽しい作品なのに!
それはまた『いっぱしの女』のエッセイ「やっぱり評論も読みたい」で少女漫画の評論について氷室さんが書いていたことに共通するところであります。
「的はずれな評論は、作者だけではなく読者をも傷つける」
でもその一方で、氷室さんは「評論は必要だ、ひとつの作品をとおして、同じ美意識やちがう価値観とぶつかる興奮をあじわいたい」とも書いています。
ロマンティックな気持ちのなかに瞬くのは、”大切な相手と築きたい関係性”への理想や希望の炎
私はロマンティック・コメディの信奉者として、どうしてこのジャンルが好きなのかを真剣に考えました。ロマコメでは主人公の2人が出会ってから結ばれるまでに、クリアしなくてはいけない様々な約束事があります。強力なライバルが出現したり、どちらかの陰謀や嘘がバレて相手を失望させたり、そうこうしている内にどちらかが海外などの新天地で仕事をすることになって、やっと自分の想いに気がついた相手が空港なり駅なりに急ごうとすると渋滞に巻き込まれたり。こうしたお約束を通過さえすればそれなりに体裁が整うのがロマコメですが、優れたロマコメ作品というのは、このクリアするポイントでこちらをあっと言わせてくれる、「そう来たか!」と驚かせてくれることが多い。さらに今までの作品とは違う要素を入れて、ロマコメの、ひいては恋愛関係の新しい在り方を見せてくれたりします。

恋愛は元来、厄介なものです。二人の間の関係性のダイナミズムは複雑なものとなり、理不尽なことも多い。でも、自分が特別だと思っている相手に、自分のことも特別だと思って欲しいという思いの根底には、最も近しさを覚える人間と平等な関係性を築きたいという切なる願いがあります。いろんな障害を軽やかに乗り越えて、そのゴールへと至るロマンティック・コメディを見ていると、それも不可能ではないという希望を抱けるのです。アスリートが見事なゴールを決めるのを見ているのと同じような、アドレナリンが上がる気持ち。胸をキュンとさせるロマンティックな気持ちの中には、人々が築いていきたい関係についての理想や希望の炎が瞬いています。そんなハッピーエンドを求める気持ちを、嘲笑ってはいけないはずです。
それが自分にとってロマンティック・コメディの醍醐味なのだと気がついてから、私は自分の言葉でロマコメを語れるようになり、このジャンルの映画についての文章を沢山書いてきました。
進化しゆく”ロマンティック”と”ハッピーエンド”。新たな名作にも期待
いま、ハリウッドのロマンティック・コメディ映画は新たなフェーズに差し掛かっています。このジャンルに光を当てた『Romantic Comedy/ロマンティック・コメディ』(2019)は、このジャンルの問題点にメスを入れるシネマ・エッセイ的なドキュメンタリー作品でした。

主人公たちが都会で生活をしている富裕層、かつ白人ばかりで、違う社会階層の人間や、異人種間カップルは出てこない。性的マイノリティはいつも便利使いされる脇役で、偏見に満ちた描かれ方をしている。女性のヒロインは男性に都合のいいキャラクターで、こうでなければ人に愛されないという強迫観念を人に植えつけている…そもそも、恋愛の成就だけが幸福だなんて前提が間違いではないのか。どの批判ももっともです。
でも、最近の新しいロマンティック・コメディの作品を見ていると、こうした批判をクリアしているものも少なくありません。人種やセクシュアリティ、登場人物の構成もより複雑で多様性のあるものになってきています。そうした新しい作品群のなかから、いままでの“ロマンティック”という言葉の定義や、ハッピーエンドの概念を覆してくれるような、すごい名作が出てくるような予感がしています。そんなニュー・ロマンティックな作品が出てきたときに、「そう来たか!」と膝を打ってときめきを感じるような自分でいたいと私は思っています。

山崎まどか
コラムニスト・翻訳家。女子文化をキーワードに映画・文学・音楽・その他のカルチャーについて執筆。主な著書に『オリーブ少女ライフ』(河出書房新社)、『女子とニューヨーク』(メディア総合研究所)、『優雅な読書が最高の復讐である』(DU BOOKS)、共著に『ヤング・アダルトU.S.A』(DU BOOKS)、訳書に『愛を返品した男』(B・J・ノヴァク、早川書房)、『ありがちな女じゃない』(レナ・ダナム、河出書房新社)、『カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ』(サリー・ルーニー、早川書房)など。
寄稿:山崎まどか
編集:大沼芙実子
