
リム・カーワイという監督をご存じだろうか。大阪を拠点のひとつにしながら、軽やかなフットワークで世界中を舞台にした映画作りを続けている監督である。新作『COME & GO カム・アンド・ゴー』は日本がアジアの一部であることを強く意識させる作品であり、日本と世界との繋がりを見せる稀有な邦画だ。リム・カーワイ監督にしか撮ることのできなかった貴重な記録であり、日本映画史に残すべき作品だと思っている。どうしてリム・カーワイ監督にしか撮れなかったと思うのか、記してみたい。
「ドリフター」と「監督」。
その境を曖昧にするカーワイ監督の映画作り。
1973年生まれのカーワイ監督は、マレーシア出身の華僑。19歳の時に留学生として来日し、大阪大学で電気工学を学び、卒業後に通信会社に就職したとのこと。やがて映画への思いが募り、中国の超難関、北京電影学院で映画製作を学び、やがて2010年に『マジック&ロス』を発表する。香港のリゾートホテルを日本人と韓国人の女性が訪れる幻想的なドラマだ。『マジック&ロス』は、プロデューサーと主演に日本の杉野希妃、韓国からはキム・コッピとヤン・イクチュンが役者として参加し、カーワイ監督のボーダーレスな映画作りの姿勢が早くも披露されている。キャリア初期の日本の監督にはなかなか出来ないことである。
その後、大阪を舞台に作品を作ったと思えば、中国でラブストーリーを撮り、ついにはアジアを脱出してバルカン半島に向かい、スロベニアやマケドニアなどの東ヨーロッパ諸国を旅しながらロードムービーを仕上げてしまう。『どこでもない、ここしかない』(2018)と題されたこの作品は、妻に逃げられた男の物語が軸にはあるものの、確固たる脚本は存在せず、監督が現地で出会った人々にその場で設定状況を説明して演技をしてもらい、それを繋げていくという、まったく自由な体制で作られている。当然、物語はスムーズに進捗することはしないが、あまり訪れる機会が多くはないであろう地への刺激的な旅に同行している気分を、観客は存分に味わうことが出来る。
世界を旅するように映画を撮る監督、それがリム・カーワイ監督であり、自らを「ドリフター(漂流者)」と称することがあるように、流れるように映画を撮る。その流れの中に、日本が入ることもあれば、入らないこともある。つまり、カーワイ監督の世界観の中では、日本は独立して閉じた存在ではなく、世界の流れの中にある存在であり、そのような視点が味わえる日本映画は、実に希少なのである。
静観している間も、世界は動き続けていた。
取り残された日本映画界に風穴を空ける、2人の日本人監督。
僕が東京国際映画祭で作品選定に関わっていた際に、「今年の傾向は?」という質問をされて「越境や移民を主題に持つ映画が増えました」と答えるようになってから、10年くらいが経つだろうか。いや、もっとかもしれない。直近では、シリア難民が欧州に押し寄せた「難民危機」のピークが2015年にあり、その前後で「ボーダー」「難民」「移民」を扱う作品が激増した印象が強い。もちろん、欧州だけでなく、アメリカと移民は常に重要な主題であり続け、アジアにおいてもロヒンギャ難民の立場をめぐる作品も多く見られた。もやは「傾向」ではなく、ひとつのジャンルとして移民を主題に持つ映画は定着している感は強い。
その点において日本映画は、いささか対岸の火事的な振る舞いを続け、世界映画の潮流から隔絶されている印象が否めなかった。極東の島国はシリア難民が目指すにはあまりにも遠く、到達したところで日本は世界有数の難民認定数の少なさでも知られる。移民に仕事を奪われるという事態は日本では発生しておらず(少なくとも社会問題化はしておらず)、映画の主題としても親しみのないものに追いやられてしまったようだ。世界の危機感を日本映画だけが共有していない状況に、国際的な映画を見続けている人であれば物足りない気持ちを抱いていたのではないか。
なにも、世界が直面する社会問題を日本映画も取り上げるべきであると言いたいわけではない。世界映画も、使命感に駆られて社会問題を主題に取り上げているばかりではないはずで、そこにドラマが生まれ、映画としてインパクトを持ちうるから取り上げているのだ。ストーリーが膨らみ、緊迫感も孕むであろう移民問題に、どうして日本映画は向かわないのだろうというもどかしさを長く感じていた。
さかのぼれば、崔洋一監督の『月はどっちに出ている』(1993)という一時代を築いた傑作もある。より現代の状況に寄せて見てみると、『サウダーヂ』(2011)で大注目された富田克也監督が長らく孤高の存在であったが、なかなか後が続かないという印象であった。しかし、その状況が少しずつ変わってきた気がしているのだ。
2017年に藤元明緒監督が発表した『僕の帰る場所』こそは、移民映画時代における日本からの回答と呼ぶべき作品であった。日本に暮らすミャンマー人家族の苦境を生々しいリアリズムで描き、主題及びドキュメンタリー的なそのスタイルは、日本映画をワールドスタンダードに引き上げたように見えた。2017年の東京国際映画祭では日本映画部門ではなく、アジア映画部門に出品され、見事作品賞を勝ち取っている。外国との共同製作が常態化しているアジア映画の中でも、遜色無い輝きを放ったのだ。
藤元監督の最新作となる『海辺の彼女たち』(2021)は、日本に出稼ぎを目的に入国した3人のベトナム人少女の苦闘を描き、ダルデンヌ兄弟作品ばりの強度なリアリズムでまたもや日本における移民問題を可視化せしめた傑作である。藤元監督が現在日本映画に開けている風穴は、とてつもなく大きく、世界標準の演出家であると呼んでも決して過言ではないだろう。


さらに、今年公開された日向史有監督の『東京クルド』(2021)は、トルコ国籍のクルド人青年の日々を追うドキュメンタリーであるが、日本の入管体制の非人道性をあらわにする。観客は日本人であることの恥辱にまみれ、しかし酷い実態を知る意義に目を開かされる、超重要作である。



このようにして、日本では存在しないことのようにされていた移民を巡る問題が、日本映画でも語られるようになってきたのである。これらの監督の今後の活動に注目していきたいし、さらに後続にも期待したいところである。
さて、ここでリム・カーワイ監督に話を戻すと、上記の藤元明緒監督は、カーワイ監督が大阪で撮った作品の助監督をしていたとのことで、ここでひとつの系譜が見えてくるかもしれない。もっとも、ヘヴィーなパンチを繰り出す藤元監督に比べて、上述したようにカーワイ監督は軽やかなフットワークが持ち味であり、映画の内容もふんわりと風通しがいい。そして演出も、流れるように自由であり、その場の空気を取り込みながら即興性に溢れているのが特徴である。
そこにあるストーリーを掬い上げる軽やかさと柔軟さ。
リアルをフィクションに取り込むスピード感。
ここで話はまた逸れるのだけど、本稿を準備している時、本当にたまたまリム・カーワイ監督から僕宛にメールが届いた。なんだろうと思って開いてみると、なんと現在新作を撮影中であり、良かったら出演しませんか?というオファーだった。もちろん僕には演技経験などないのだけれど、「元東京国際映画祭でディレクターをしていた矢田部」という本人役で出てみないかというのだ。ただし、ドキュメンタリーではなく、リアルを混ぜたフィクション、という感じらしい。
『あなたの微笑み』と題されているこの作品は、映画監督の渡辺紘文さんが本人役で主演している。仕事が無い状況でもがく渡辺監督を描く内容とのことで、沖縄から撮影が開始され、北海道に至るロードムービーになるらしい。全く独自のアート作品を連発し、超コアなファンを有する孤高の存在である渡辺紘文という存在からインスパイアされた、ドキュフィクションというところだろうか。
脚本はなく、大まかな設定だけが伝えられて、出演者はその場で対応しながらカメラの前で演技をしていく。本当にその場その場の対応のようで、というのも、僕にオファーがあったのが10月17日の日曜日の夜で、撮影日は2日後の19日だというのだ。なんと出演2日前のオファー!渡辺紘文さんに聞くと、「ヤタベさんにオファーするなら急いだほうがいいですよ、と僕は言ったんですけどねえ」とのことなのだが、何故か僕はその日がぽっかり空いていたのだから、これもカーワイ監督マジックということなのだろうか(あるいは、僕がヒマであろうと見抜いていたカーワイ監督の洞察力、と言えるかもしれない。)
そして、撮影に赴いてみると、カーワイ監督の現場での応用力に舌を巻いた場面があった。主演の渡辺さんが、ゲームセンターで景品が当たるゲームに興じているシーンを撮影している時のこと。予定には無かったことだけれど、実際に渡辺さんが景品を当ててしまった。すると、ゲームセンターのスタッフを呼んで、ガラスケースの中の景品を出してもらい、そのスタッフも映画に出演という形になる。そこで選んだ景品というのが特大のポテトチップス。その巨大なポテチの袋を、次のシーンでも、まるであらかじめ用意していた小道具のように、使ってしまうのだ。しかも、ポテチ袋を抱えた人物が実に絵になっている。景品を当てることも想定していなかったはずが、あっという間に現実を映画に取り込んでいく。この発想のスピードと応用力に心底感心したのである(『あなたの微笑み』の撮影は年内続くとのこと)。
国境、国籍、人種、性別…
日本の中のアジアを可視化し、その問題点も際立たせる手腕。
さて、リム・カーワイ監督、公開を控えているのが、目下の新作『COME & GO カム・アンド・ゴー』である。とてもたくさんの人物が登場する群像劇だ。ラフな脚本はあったというが、おそらく監督が関心を持った人たちを次から次へと集め、設定を与え、その場で演技をさせ、ハプニングを取り込み、そうして集積された膨大なエピソード集を練り込んで、1本の大きな映画に仕立てていったのであろうことは間違いない。


この映画で「カム・アンド・ゴー」、つまり「行き来」する人たちの数の多さは半端ではない。白骨事件を捜査する大阪の刑事や、若い女性を騙してAV撮影を敢行しようとする沖縄の男性、あるいは目的を失って夜の街をさまよう女性など、日本人も登場する。しかし、メインとなるのは、数年間帰国が許されないベトナム人の男性、日本語学校の学費が払えず苦境に陥るタイの女性、雑貨店のアダルトコーナーに興味を示す台湾の男性、ツアーから離れてひとりで行動してマッサージ店にクレームを入れる中国の男性、店の金を盗んだと濡れ衣を着せられるネパールの青年、日本に出稼ぎに来ている韓国人女性たち、外国人ホステスを手配する韓国と中国の男たち、ハラル料理のレクチャー講師として来日して夜の街の接待を拒否するマレーシア青年など…、まさにアジア曼荼羅である。


フィクションの設定ではあるけれど、こういう人たちが実際に日本に存在することは明らかだろう。我々の視界に入ってくるかもしれないけれど、特に注意を払われない人たちだ。しかし、かれらは確実に存在するのだと、日本における外国人の苦境を可視化するのが、この作品の極めて重要な点である。そして、日本における外国人を可視化するだけでなく、日本はまぎれもなくアジアの1国であるという事実をも改めて実感させてくれる。実際に、これだけの多国籍な状況を、日本を舞台にして撮れる監督がリム・カーワイ以外に存在するかと聞かれたら、絶対にいないと断言が出来る。我々が暮らす日本の「見えない」状況を可視化する映画を作ってくれたリム・カーワイ監督の存在に、大いに感謝すべきなのである。
しかし、「見えてない」のが日本人だけでないところが重要であると、カーワイ監督は指摘する。日本に来日するアジア人たちは、自国のコミュニティーの中に閉じこもり、日本についてはもちろん、他国のコミュニティーついても全く関心を示さないという。映画のミャンマー人やベトナム人やタイ人たちは、確かに互いに交流しているようには全く見えない。彼らの固く閉鎖されたコミュニティー感覚も、ひとつの問題意識として挙げるべきではないか、というのがカーワイ監督の指摘である。いままでも映画で日本と特定の外国という2項的な状況が描かれることはあっても、日本国内における複数国間の関係というのは、全く新しい主題であり、かくたる視点を持った作品を他に見つけることは難しく、本作の画期的な要素であると言える。フットワークの軽いアジア人で、日本にも造詣の深いカーワイ監督が、俯瞰で物事を見ることが出来るが故の視点なのだ。
『COME & GO カム・アンド・ゴー』は、カーワイ監督の集大成的な力作であり、日本の移民映画の中でも歴史に残すべき作品であるだろう。日本の意識的な作家たちが国境を意識した作品を手掛けることに期待しつつ、カーワイ監督の独創的で自由な世界観が今後どこにカム・アンド・ゴーするのか、『COME & GO カム・アンド・ゴー』を見ながら楽しみにしていきたい。
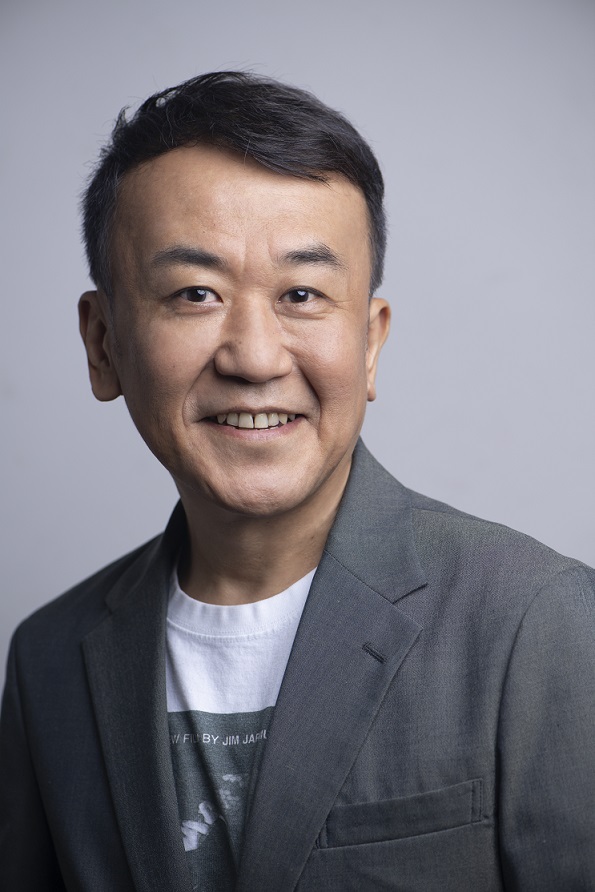
矢田部吉彦
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
