
『香川1区』©ネツゲン
ドキュメンタリーとは何か。その定義を語り始めたら本が1冊書けてしまう。いや、僕には書けないけれど、ドキュメンタリー製作の現場に身を置いたこともあるし、観客としても好んで鑑賞し、いったいドキュメンタリーとは何なのかという古くて新しい問いについて思考を巡らせることは大好きだ。
細かい定義には踏み込まないとしても、ドキュメンタリーを巡る環境は随分と変わってきたように思う。デジタル革命によって撮影が簡易化されたのはフィクション映画と変わらないとして、世界を独自の視点で切り取る先鋭的な作家によるシリアスなドキュメンタリーがメインストリームとされた時代から、エンターテイメント的要素を持つ作品も目立つようになり、ドキュメンタリーは柔軟に細分化されている印象を受ける。
もとより、シリアスなドキュメンタリーはコアな層には刺激的な場である一方で、一般的な観客に対する敷居の高さは如何ともし難いものがあった。それがおそらくはマイケル・ムーア監督作品の商業的成功をきっかけとして、ドキュメンタリーの一般への訴求力はハネ上がり、エンタメ的要素を備えたドキュメンタリー作品が増えてくる。音楽ドキュメンタリーに傑作が相次ぎ、環境問題への関心の高まりが優れた作品を生み、やがて登場した配信チャンネルが硬軟取り混ぜた題材を絶えず送り込んでくる。フィクション映画に商業映画とアート映画の2極があるように、ドキュメンタリーにもエンタメとアートの構図が見てとれそうである。そこでドキュメンタリーの定義を云々するのは、もはやあまり建設的でないのかもしれないとも思う。
作家主義から題材主義へ:求められるリテラシー
僕は、故佐藤真監督の遺した「ドキュメンタリーは現実を批判的に受け止めるための映像表現である」という定義を深く信仰する立場の者だ。現実を撮影した映像を再構成して虚構を作り、そこから改めて現実を見直す作家の視線を追うことに無上の刺激を覚える。しかし、その感覚を基礎に持っているとして、ただ表面に映る題材にも魅かれてしまう自分を否定できない。教条主義や啓蒙映画から距離を置こうとしても、あまりにも勉強になるので映画作品としての評価を超えて讃えてしまう作品もある。例えば、Netflixオリジナル作品であり、トランスジェンダーが映画の中でいかに乱暴な形で表象されてきたかを教えてくれる『トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして』や、海洋プラスティック問題の深刻さを見せる『Seaspiracy:偽りのサステイナブル漁業』は僕にとってそんな作品だった。ただ、それはいい映画を見たという感情とは別の、知識が充足された快感に近いものであり、優れた作家によるドキュメンタリー作品によって感性を揺さぶられる経験とは別のものとして整理する必要があるかもしれない。
啓蒙映画がエンタメに接近すると、恣意的な編集で観客をマニピュレートする場合があるのでとりわけ注意が必要だ。思い出されるのは、日本のイルカ漁を扱った『ザ・コーヴ』(09/ルイ・シホヨス監督)。当時、そのセンセーショナルな内容が国際的に話題になり、東京国際映画祭で上映するかどうか、すったもんだがあったのだけれど、ともかく見せて観客の判断を仰ごうということになった。僕は観客を誘導する編集がえげつないと感じていて、ドキュメンタリーのあり方としての議論に発展してくれればと期待したのだけれども、見事に話題はイルカ漁の是非の話に終始してしまい、来日した監督も人の話を聞かない頑迷な人物だったので、ひどくげんなりしたものだった。そんな僕の気分はともかくとしても、その後の劇場公開の可否が検討される過程で表現の自由を巡る議論も派生し、大衆的な話題も振りまいた稀有な「ドキュメンタリー」であったと言っていいが、ドキュメンタリーは実に様々な意味で危険であることを警告する例でもあった。
少し古い例を出してしまったけれど、大衆化したドキュメンタリーから、詩的でクリエイティブなドキュメンタリーまで、いまやこのジャンルはいっそう細分化され、多岐に渡って進化を続けている。それでは、いまの日本では、どのようなドキュメンタリーが作られているのだろうか?
いよいよ国際化する日本のドキュメンンタリー
世界を切り取って再構築する若い作家を多く目撃することが出来たのが、2021年12月に開催された「東京ドキュメンタリー映画祭2021」における体験だった。日本と海外を結ぶ広い視野を持った作品の多さに驚き、そこに希望を見出したほどだ。2020年の同映画祭グランプリを受賞した粂田剛監督作『なれのはて』(20)は、フィリピンのスラムに流れ着いた日本の老人たちを7年間追った驚愕作だったが、粂田監督が同時期に取材していた他の老人たちをスピンオフ的に見せる『ベイウォーク』も2021年の同映画祭に出品され、人の一生とは一体なんなんだろうか、という根源的で絶望的な問いを投げかけてくる魂の込められた逸品であった。

21年のグランプリを受賞した『Yokosuka 1953』(21/木川剛志監督)は、第二次世界大戦時、米兵と日本人女性との間に生まれた少女のその後の歩みを辿り、日米を繋ぐ感動のドラマが紡がれていた。準グランプリの『大鹿村から吹くパラム』(21/キム・ミョンユン監督)は、日本の映画大学で学ぶ韓国人監督が環境破壊の危機に直面する長野県の大鹿村に通い、そこで暮らす人々の姿を活写している。他にも、『再びおかえり』(21/マルコス・ヨシ監督)では、日系ブラジル人監督が両親の日本への出稼ぎの日々を描き、『故郷とせっけん』(21/八島輝京監督)は、戦火を逃れシリアからトルコに移住を余儀なくされた石鹸工場を営む一家の故郷への想いと、彼らの仕事ぶりを、日本人監督が実に丁寧に見せてくれる。
何と視野が広く、豊かな作品群だろうか。同映画祭の選定者に話を伺ってみると、国際性の豊かな作品をあえて選定したのではなく、優れた作品を選んだ結果、このような作品が残ったということだという。つまり、日本でも越境の概念に意識的な作家が正当な評価を得る時代に突入したということだ。何とも希望に胸が膨らむ事態ではないだろうか。
多様化する社会派ドキュメンタリー
ドキュメンタリーを巡る変化として、ジャンルの多様化というドキュメンタリー側の状況に加えて、現実世界側の変化という事情もある。いつの頃からか、映像作品が政治や社会問題から遠ざかり始めたのだ。日本において報道の自由度が著しく低下していると報じられ、自粛が蔓延し、娯楽と政治の分離を良しとする声も目立ち、そして表現者を追い詰める意見を瞬時に集約して拡散するテクノロジーが進み、映画の内容は内向きになるか、保守化するしかなくなっていった。作家の政治的主義主張を押し付ける作品のアンチテーゼとしてのドキュメンタリーが議論されていた時代を経て、政治的映画そのものが無くなってしまった。
このような状況の中で、政治を少しでも描けば、その作品は勇気あるものとして一定の評価を得られるようになる。この逆説的な状況を揶揄しようと思えばできるのだろうけれど、僕はやはり勇気ある作品を評価する立場でいたい。劇映画の『新聞記者』(19/藤井道人監督)は、閉塞的な状況に久々に風穴を開ける快作であったことは記憶に新しい。僕自身も傍観者ではいられない気持ちになり、肝の座ったベテラン監督の仕事を通じて刺激を伝えたいと考え、2019年の東京国際映画祭に森達也監督『i-新聞記者ドキュメント』(19)と原一男監督『れいわ一揆』(19)を招聘した。ドキュメンタリーの裏表を知り尽くすビッグネーム2人を同時にお迎え出来たことは僕にとっては快挙であったのだけれども、世間の反応は僕が期待したほどにはバズらず(上映はそれぞれ非常に盛り上がったけれど)、果敢な作品作りの勢いを拡散していこうという、うねりに繋げることは出来なかった忸怩たる思いが残っている。
萎縮せずに政治や社会問題を扱うことなど、あまりに当たり前過ぎて、ドキュメンタリーに求められる要件などでは決してなかったはずなのだけれども、そういう時代になってしまった。サブジャンルに過ぎなかった社会派ドキュメンタリーが存在感を高め、いまや「不都合な真実」をいかに伝えるかが現在のドキュメンタリーにおいて貴重視されるようになっている。ジャーナリズムに接近したドキュメンタリーがその価値を高めているというべきか(もちろん、ジャーナリズム=ドキュメンタリーでは決してないのであり、ジャーナリズムはあくまでサブジャンルに過ぎない)。その中で、作家の姿勢がどのように感じられるか。撮影された映像をいったん相対化して、そこから映像に向き合い直す作家の批評性がいかに感じられるかという点が、作品の評価を左右していくのだろう。
『愛と法』(17/戸田ひかる監督)は、男性のゲイの弁護士カップルが日本社会で奮闘する姿を描く。イギリス育ちの戸田監督としては、日本の現状にもどかしい気持ちでいっぱいだったのであろうことが如実に伝わってくる。それでも監督は一切画面には登場せず、客観的に事象を見つめることに徹している。監督の姿勢を含め、実に清々しい作品であり、後続に与える影響も大きいはずだ。
より近年に目を投じると、『なぜ君は総理大臣になれないのか』(20/大島新監督)こそは、誠実な青年が政治の世界でもがく様を見せていく一方で、常に撮影対象との距離感を計りながら、作品のあり方を問い直していく監督の姿勢が伺える現代の傑作であった。

新作『香川1区』(21/同)では、前作が成功したことにより、映画の存在が選挙に影響を与え得る事態が発生し、監督自身が当事者のひとりとなってしまった複雑な状況を内包している点でアクロバティックな作品だ。小川淳也議員という撮影対象の魅力、監督の姿勢、作品にかけた年月の意味(前作は長く、新作は短い)、「不都合な真実」の暴露、世間への浸透度など、いまのドキュメンタリーを語る上で避けて通ることが出来ない連作となっている。

全く異なるアプローチを取ったのが『パンケーキを毒見する』(21/内山雄人監督)だろう。

『新聞記者』を仕掛けた河村光庸プロデューサーが菅政権に正面から疑義を呈した内容だ。注目すべきは、総選挙を視野に入れた政治日程を勘案し、そこから逆算して21年春までの映画完成を目指して製作されたことと、シネコンのスクリーンで上映されて多くの観客を獲得したことであり、劇場用のドキュメンタリー映画作品としては異例であったと言っていいだろう。アニメーションや任侠映画を模した印象シーンなどを挿入し、「地味な」ドキュメンタリーの雰囲気は徹底して排除したアメリカンな作りであり、日本におけるエンタメ政治ドキュメンタリーという分野の開拓を試みている。
このように政治を扱う作品に新境地が伺える中、表現の不自由を巡る状況を逆手に取った『テレビで会えない芸人』(21/四元良隆・牧祐樹監督)のような作品が、テレビサイドから生まれてきていることにも注目したい。政治ネタを売りにするためにテレビに出られない松元ヒロのドキュメンタリーをテレビ局(鹿児島テレビ)が製作するという倒錯した企画であるけれども、もとはテレビで放映された番組であるということも興味深く、作り手の罪滅ぼしというか懺悔というかの思いも滲み出る作品である。
さて、社会派のドキュメンタリー作品の中で、政治そのもの以上に重要な主題が人権だろう。小川紳介監督の三里塚闘争にしろ、土本典昭監督や原一男監督の水俣病にしろ、彼らの作品は究極的には人権の蹂躙に対する闘いの記録だ。そして、2021年、日本の入管制度という新たな人権への脅威が映画を通じて露わとなった。もちろん、新たに問題になったのではなく、常にそこに存在していた事象を、映画が映し出してくれたのである。
『東京クルド』(21/日向史有監督)は、中東地域の問題だと信じて疑うことの無かったクルド人迫害問題が日本にも存在していることを教えてくれる。在日トルコ人の間で、クルド系の人々との衝突が暴力的な騒動に繋がっていることを伝える導入部からこの作品は驚きに満ちているが、次第に主題は日本の入管制度にシフトしていく。迫害によって出国を余儀なくされ、亡命を求めた日本で難民申請が通らず、永遠に塩漬け状態に放置されてしまう人々の状況が明らかになる。不法入国者として施設に隔離され、一時的に施設から出ることが許されるとしても、働いてはいけない、保険は適用されない、生活保護も申請できない、など、生きる権利を認められない存在として放置される。ただ普通に生きることを願う真面目な好青年たちを主人公に据えているため、なおさら観客の感情移入は激しい。やがて、入管施設の職員が彼らに投げる非人道的な言葉を聞かされるに至り、我々は日本人であることを恥じ入り、絶望的な怒りに駆られることになる。
2015年から16年をピークに、欧州は主にシリアから流入する難民危機に揺れ、移民とその苦闘を主題に持つ映画が激増した。社会派とは縁遠いと思われたアキ・カウリスマキのような監督までが移民を作品の主題に取り入れ、移民映画のうねりは世界に広がっていた。日本映画は長らくそのうねりの枠外にいたものの、ようやく風向きが変わってきたことを本コラムのリム・カーワイ監督を紹介した回でも書いたけれども、『東京クルド』は、「移民が移民になれない移民問題」という日本特有の事態をドキュメンタリーのフィールドでさらけ出してくれた。その重要性は計り知れない。
ちなみに、日向監督は次回作でウーマン・ラッシュアワーの村本大輔氏を取り上げるそうである。政治や人権やエンタメのドキュメンタリーについて概観してくると、日向監督と村本氏の組み合わせは驚異的にタイムリーであると興奮せざるを得ない。詳細は分からないものの、心して完成を待ちたい。
ドキュメンタリーは見る者の姿勢を問う
入管問題に話を戻すと、『牛久』(21/トーマス・アッシュ監督)が2月26日から公開される。

『東京クルド』でも見られた、不法入国とされた外国人を収容する施設「東日本入国管理センター」が茨城県の牛久にあり、施設の総称として使われる牛久という名がそのまま映画のタイトルになっている。
施設に収容されている人々に監督が面会し、彼らが受けている非人道的仕打ちを赤裸々に描き出す内容であり、かなりショッキングである。監督は傍観者でいられるはずもなく、収容者たちと信頼関係を結び、彼らの状況を改善すべく自ら行動し、政治家も巻き込んで法改正を目指していく。

映画が扱う内容は映画の出来を正当化しないというのは僕が常に意識することではあるものの、この映画を出来の良し悪しで評価することにあまり意味があるとも思えない。映っているものを恐怖の目でただ見つめることしかできない。そして周囲に勧め、多くの人が現状の知識を共有するように働きかけることしかできない。我々は今こういう国に住んでいるのだという認識を恥辱の念とともに抱き、いったい自分に何が出来るのかを、問いかけ続けるしかないのだ。
ただ、映画を見た限りは上記の感想を抱くのだけれども、本作が作られた経緯について、関係者間で合意がなされていなかったという指摘がされていると聞く。詳細を知らないので安易な記述は避けるが、ドキュメンタリーを見て、その内容を無批判に鵜呑みにすることは危険であり、どこかに余白を持ちながら、自分の想像力や行動でその余白を埋めていく能動的な作業が必要だろう。内容がセンセーショナルであるほど、受け手には冷静さが必要だと言えるかもしれない。
ドキュメンタリーの世界はかくも奥が深い。思考は千々に乱れ、まとまることを知らない。ただ、ドキュメンタリー映画が存在意義を強め続けていることだけは、確かのようだ。いつの世にも増して。
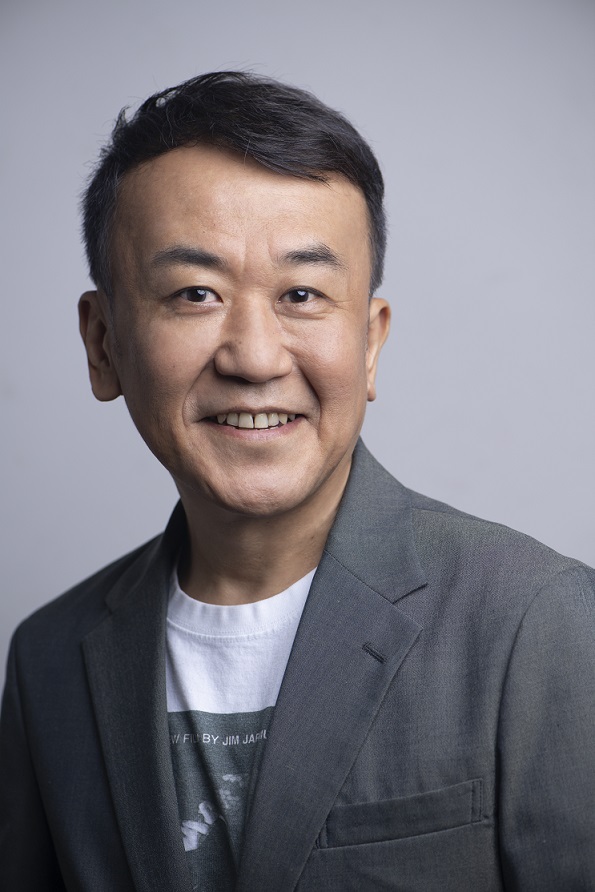
矢田部吉彦
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
