
コロナの影響を受けて世界の映画祭も中止やオンライン移行を余儀なくされている中、その動向がもっとも注目されたのが、カンヌ映画祭(以降、カンヌ)だ。
2020年は残念ながら中止。カンヌ側は意地を張るかのように「中止」という言葉を使わず、ノミネート作品を発表して継続性のアピールに腐心したのだけれど、とはいえリアルな上映は無く、事実上の中止だった。2月のベルリン映画祭と8月のヴェネチア映画祭(以降、ヴェネチア)はリアルで実施しただけに、さぞかしカンヌは無念だっただろうと業界でささやかれたものだ。
そして今年。例年の5月開催こそ叶わなかったものの、少し時期をずらし、7月6日から17日にかけて無事に開催されることになった。僕もかれこれ20年近く、毎年カンヌに出張することを中心に1年が回っていたのだけれど、今年はまだ動けない。配給会社関係者もほとんど日本に残ったようだ。しょうがないなあと諦めていたところ、5月の下旬にカンヌ映画祭に併設されている映画マーケット(映画の権利を売買する業界関係者向けの見本市)である「マルシェ・デュ・フィルム(Marché du Film)」から、僕のところに連絡が入った。「現地入り出来ない日本のバイヤー向けにカンヌ出品作の試写を東京で行いたいのだが、手伝わないかい?」ということで、ならばやりましょうと試写運営を引き受けることにした。期せずして、僅かながらもカンヌに触れられる機会をもらったわけだ。
そのバイヤー向け試写は本番のカンヌと同時期に開催され、無事に終了。僕もいくつかの作品に触れることができた。映画祭では最高賞のパルム・ドールがフランス人女性監督に与えられ、多様性重視を掲げる映画界を象徴する出来事となった。この機会に、カンヌのフランス映画から読み取れる現状を概観してみようと思う。
ヴェネチアは革新的で、カンヌは保守的という誤解
多少手垢の付き始めた「多様性」という言葉だけれども、やはり臆せず使っていこう。そして映画の多様性の確保にカンヌが果たす役割について、作品を通じて語る前に、触れておきたいことがある。それは、Netflixとの関係だ。
劇場公開が優先されないNetflix作品はカンヌで上映されない(2021年もそうであった)。それに対し、ヴェネチアでは上映される。カンヌで上映できず、ヴェネチアで最高賞の金獅子賞を受賞したアルフォンソ・キュアロン監督の『ROMA/ローマ』(18)のケースが象徴的だ。なので、この状況だけを見て、カンヌは保守的で、ヴェネチアは革新的であるという指摘がなされることがある。しかし、これはちょっと待ってほしいのだ。
フランスでは、映画館の収入の一部が映画関連公的機関に「映画税」的な形で徴収され、ストックされる仕組みがある。機関はその収入を、映画製作への助成金という形で還元していく。それは、自由な映画作りの原動力となる。その助成金システムは、フランス映画のみならず、合作という形で他国の作家の創造性にも貢献していくのである。
自由な創造を可能せしめる助成金によって製作された映画が、最先端のアート映画として世界中の映画祭で紹介されていく。その牙城となるのが、カンヌ映画祭なのである。劇場公開がされないNetflix作品を上映しない(できない)のは、映画のあり方をめぐって単に精神論的な意地を張っているのではなく、劇場上映がアート映画の製作体制全体を担保しているからなのだ。
イタリアにはこの仕組みはないため、ヴェネチアはNetflix作品を上映することに足かせが無い。それはそれで素晴らしいのだけれども、これによってヴェネチアが偉くてカンヌは遅れている、という話ではないことは強調しておきたいのだ。もっとも、Netflixはその無尽蔵の資金によって、作家の自由な創造を可能せしめているという側面もあるし、カンヌのケースはフランスの国内法の整備の問題でもあるので、カンヌとNetfixの関係は複層的な論点を含んでいることになる…。
まずい。このコラムは4000字程度といわれているのだが、このままでは1万字になってしまうぞ。先を急ごう。
2021年 カンヌが示した「多様性」。切り口は1つではない
さて、今年のカンヌのフランス映画を概観しようということで、その特徴を分けてみたい。第1に女性監督の躍進、第2に移民系監督の存在感、そして第3に音楽映画の流行、である。
まず1点目の女性監督の躍進について。もともとフランスには優れた女性監督が少なくないけれど、それはあくまでも僕の個人的な印象であり、当事者たちのストレスフルな現実が#MeToo運動を契機として露わになった。映画業界における女性監督の数の少なさが指摘され、カンヌ映画祭もコンペティション部門に選ばれる女性監督作品の数が男性監督作品に比べて著しく少ないという批判を浴びることになったのだ。
そして、今年2021年はまさにその状況に風穴を開けるかもしれない結果が待っていた。処女作『RAW〜少女のめざめ〜』(16)で衝撃をもたらした新鋭ジュリア・デュクルノー監督が、長編2作目となる新作『Titane』で最高賞のパルムドールを射止めたのだ。女性監督のパルムドール受賞はジェーン・カンピオン監督『ピアノ・レッスン』(93)以来、28年振り2度目というのだから、女性監督の低評価を指摘する声は根拠なきものではなかったのだと、改めて呆然とするしかない。

『Titane』は息子を亡くした父親と、シリアルキラーの女性の交流を描き、激しいファンタジーとドラマを融合させたまったく新しい領域を開拓した超野心作であると評価されている。度肝を抜く大胆な内容をひっさげた若き女性監督が頂点に立ったということは、確かに新時代の到来と叫びたくなるではないか。僕も映画祭勤務時は「監督に女も男もない」とコメントしたことがあるけれど、積極的に女性監督を応援することが次代の流れを作ることもあるとの思いがいまはある。作品が斬新で素晴らしいことが第一であることは間違いないとして、審査委員長のスパイク・リーには女性監督を本気で応援したいとの気持ちもあったのではないか、とも思う。
ちなみに、コンペ部門の全9名の審査員のうち、女性が5名と男性審査員の数を上回ったのも史上初であり、時代の趨勢がうかがえた。そして同部門のフランス映画には他にも女性監督の秀作が目立っている。簡単に紹介してみよう。
日本で熱心なファンを持つミア・ハンセン=ラブ監督『Bergman Island』は、世界も待望した1本だ。スウェーデンの大巨匠、イングマール・ベルイマン監督が暮らしたフォーレ島を舞台に、男女の映画作家が創作活動を続ける果てに現実と虚構の境目が曖昧になっていくという物語。映画史上の聖地といえるフォーレ島や、監督の実体験に基づくのではないかとの憶測など、映画ファンの心を惹き付ける作品であるが、入れ子構造の複雑な世界とその中でたゆたう繊細な感覚とを見事に描いている。監督の最高傑作との呼び声も高い。
堅実なストーリーテリングに定評のあるカトリーヌ・コルシニ監督は、『The Divide』において、カオス状態に陥った救急病棟を舞台に、分断を抱えるフランス社会の現状を描いている。コミカルな場面も多く、政治的な論争、愛を巡るいざこざ、デモ隊と警察の暴力的衝突、過剰勤務のナースなど、様々な状況が一気呵成に描かれる演出力は見事の一言だ。
『太陽のめざめ』(15)が国際的に高い評価を受けたエマニュル・ベルコ監督は、『Peaceful』で真正面から癌患者に向き合った。演技教師が癌に蝕まれ、死へと向かい合っていく様に、ガチで寄り添っていくのだ。幾度となく映画で描かれてきた主題に思えるが、独自の治療姿勢を貫く医師の姿や、現代フランスにおいて屈指の存在感を放つブノワ・マジメルの演技によって、不思議と風通しが良く、新鮮で崇高な感動を呼び起こす。
いずれも強力である。確かな実力で本格作品を発表したこれらの監督たちや、破天荒な世界観で長編2本目にして頂点を掴んだデュクルノー監督を擁するフランス映画界は、世界の女性監督たちに大いに刺激を与えるに違いない。
アイデンティティの表現と、それを支えるフランス映画界
2点目の移民系作品について。「移民」や「ボーダー」がワールドシネマのキーワードのひとつとなって久しく、フランス映画もその流れの可視化に重要な役割を果たしている。アルジェリア系移民の生活を濃厚な演出で見せたアブデラティフ・ケシシュ監督の存在が大きいが、フランスと北アフリカの結びつきが生んだ秀作が今年のカンヌでも目立っている。
僕は数年前にモロッコのマラケシュ映画祭に参加する機会があり、そこで若い映画人と交流する場があった。モロッコ、アルジェリア、チュニジアなどの国はフランス映画文化圏下にあるといってもよく、会話を交わした作家たちのフランス語はネイティブだ。彼/彼女らが物語を語れば、フランスという国と、自らのアイデンティティという主題が自ずと備わってくるということになる。

アルジェリア系フランス人のヨアン・マンカ監督の『Traviata, My Brothers and I』(「ある視点」部門出品)は、海辺の町に暮らす4兄弟の姿を描いている。質素な生活と4兄弟という設定は『若者のすべて』(ルキノ・ヴィスコンティ監督/1960年)を連想せずにいられないが、本作に悲壮感はなく、移民系家族の青年たちの個性を活写し、末の弟がオペラ歌曲に目覚めていく展開が爽やかな感動を誘う秀作である。移民としての苦境は前景から退き、新世代のリアルが見られる。
チュニジア系のレイラ・ブジド監督(女性だ)は長編2本目の『A Tale of Love and Desire』が若手監督の発掘を目的とする「批評家週間」に出品された。パリの大学の文学部に入学した青年が童貞をこじらせる様を大真面目に描く作品だ。肉体関係を持つことに躊躇する青年の心理を女性監督が描く点が興味深いが、女性の心理を男性監督が100年以上も描いてきたことを考えると遅すぎるくらいだ。出自を巡るアイデンティティ、肉欲とアラブ文学の関係、そして普遍的な青春の悩みを含み、複層的な主題の練り上げ方が実に上手い。
モロッコ系のナビル・アユシュ監督は長編7本目となる『Casablanca Beats』でコンペティション部門入りを果たした。カサブランカ郊外の町のカルチャーセンターでラップ教室に通う少年少女たちの姿を生き生きと見せる作品だ。こどもたちが書く歌詞の数々が現状を伝え、ほとんどミュージカルのような形で演出されている。彼らの心情の吐露が切迫していると同時に、イスラム社会における自由な発言の許容範囲を巡って青年たちがディスカッションする様が、映画を高度な社会派へと押し上げている。
フランス人ではないが、国際共同製作という形でフランスも出資しているイスラエルのナダウ・ラピド監督作にも触れておきたい。前作『シノニムズ』(19)がベルリン映画祭で金熊賞を受賞したラピド監督はフランス映画祭で来日もしており、フランス映画圏に属する存在であると呼んでもさほど間違いではないかもしれない。パリのイスラエル人としての立場の難しさを描いた『シノニムズ』で国際的な評価を得た後に、イスラエルの地で監督が味わった辛酸を余すことなくぶち込んだのが新作『Ahed’s Knee』である。

寓意から始まり、やがては強烈にダイレクトなイスラエル批判が展開される。その作風は新感覚としか呼びようのないスタイルであり、突飛な映像感覚とメッセージの強烈さに言葉を失ってしまう。こういう作家をサポートできている点で、フランスの助成システムの重要さを改めて痛感せずにいられない。
クロスボーダーを推進し、多用な文化をその矛盾も含めて描いていくフランス映画の懐の深さを象徴する作品群ではあるまいか。
音楽映画に向かう作家たち
さて、3つ目の特徴の音楽映画とは、前の2つほどの深い意味はなく、傾向ですらないだろうけれど、幸せな偶然ということで触れておきたい。
今年のカンヌ映画祭のオープニング作品だったのが、レオス・カラックス監督の『Annette』だ。カラックスの新作がミュージカルになると発表されてから、いったい何年が経っただろうか。昨年の出品が有力視されていたものの、カンヌの「中止」を受け、作品自体の発表もカンヌに合わせるべく1年先送りにした形となっていた。まさに待望という言葉が相応しい。
アダム・ドライバーとマリオン・コティヤール主演による、英語映画。人気コメディアン(アダム)と、人気オペラ歌手(マリオン)が恋に落ちて大スクープとなり、やがてふたりは結婚してアネットと名付ける娘を授かるが、次第に関係に暗雲が立ち込めてくる…。
前作『ホーリー・モーターズ』(12)で車を擬人化したカラックスの美学は健在で、表現者の虚栄や嫉妬を独創的なビジョンで歌い上げる。下馬評の高かった『ホーリー・モーターズ』が無冠に終わった2012年のカンヌはカラックスを無視した年として記憶されたけれど、『Annette』は見事に監督賞を受賞。孤高の鬼才に遅すぎる栄誉をもたらし、シネフィルたちが溜飲を下げる結果となったのだ。
『汚れた血』(86)のデヴィッド・ボウイや『ポンヌフの恋人』(91)のレ・リタ・ミツコなど、カラックス作品は常に名曲と共に想起される。やがて既存曲に飽き足らず『ホーリー・モーターズ』でカイリー・ミノーグにセリフを歌わせた後に、ついに全編ミュージカルにたどり着いた『Annette』は、エモーションを朗らかに歌い上げる米国産エンターテイメントとも、抒情的なミッシェル・ルグラン的世界とも一線を画し、スパークスによるどこかアンチポップな旋律がカラックスの演出意図を代弁していく。ちなみに、俳優は撮影時に実際に歌っており、ライブ録音であるという。ショービズ界のグラマラスさとグロテスクさの対比を照らし、ライブ感を用いて虚構を作ったカラックスは独自のミュージカル世界を確立したと言っていいだろう。
カンヌでもう1本、ミュージカルとして好評を博したフランス映画がある。ラリユー兄弟監督の『Tralala』という作品。「大自然に放り込まれた人間」を得意なモチーフとし、人を喰ったような作風が個性のラリユー兄弟は、新作でマチュー・アマルリックにホームレス(に近い)ミュージシャンを演じさせ、彼の故郷への帰還を巡るスペクタクルを情感たっぷりに描いていく。

コロナ下で撮影され、マスク姿の人だらけという光景を映す最初のフランス映画の1本、ということになるかもしれない。マチューはそこからマスクをしたり外したりして、自在にパリの路上で歌を歌う。ドゥニ・ラヴァンに愛用ギターを捨てられてしまっても、バンジョーで歌を続ける。舞台は奇跡の町、ルルドに移り、マチューは人生を見つめ直すことになる…。
奇跡を求める訪問者を観光収入源とするルルドという町をコロナ禍の主舞台にしている点で、監督の確信犯的意図は明確であるけれども、主人公の身に降りかかる事態は現実なのか妄想なのか、それとも奇跡なのか、それは見るものの判断に委ねられる。ロック的、ブルース的で抒情的な曲の数々が、放蕩息子の帰還の物語を甘美に彩っていく。うっとりするような後味を残す作品であると同時に、神話性と現代性とがミックスされた最先端の作品であると見ることが出来る。
音楽映画は傾向ではなく偶然だろうと上述したけれど、果たしてそうか。偶然の繋がりが傾向となることもあり、偶然が傾向を呼んでいるかもしれない。カラックスの作品は構想10年であり、現在の傾向の中で語ることに無理はあるだろう。それでも(『Casablanca Beats』も含めて)2021年のカンヌに優れた音楽映画が揃ったことに、後年意義を見出すことができるかもしれない。
30年の時を越えて描きなおした「多様性」
女性監督が飛躍し、移民系監督が意欲的な作品を発表し、ファンタスティックな内容からミュージカルまで幅広く、現在の社会状況もあますことなく含んで作られていることが、今年のカンヌ映画祭のフランス映画を概観して分かるのではないだろうか。
さて、多様性のキーワードを伴うことが多いLGBTQ+を主題に持つ作品もフランス映画には多い中、折しも日本でフランソワ・オゾン監督の新作『Summer of 85』が公開される。
去年 2020年のカンヌ映画祭はラインアップだけを発表したと上述したけれど、本作はその中の1本だ。実はオゾン監督はさらなる新作『Everything Went Fine』を今年のカンヌに出品している。オゾンは多作で知られ、なんといっても、1998年の長編第1作『ホームドラマ』から、2021年の『Everything Went Fine』まで、23年間で20本の長編を作っているのだ。ほぼ年に1本だ。こんな監督はおそらくウディ・アレンを除いては他にはいまい。欧州では随一だろう。しかも、最新作を除く19本の長編が全て日本で商業公開されている!現代において最も多作で、日本で最も多く紹介されている欧州の監督として、フランソワ・オゾンは唯一無二の存在である。
そもそもは短編の名手として、オゾンは90年代中盤から頭角を現している。98年から長編を手掛け、その初期には短編時代の特徴だった生理に訴える世界観を覗かせていたものの、徐々にメインストリームに接近し、スター俳優を起用してボックスオフィスを賑わすようになった。しかし大衆向けの商業映画に偏り過ぎることなく、生死や愛のあり方を巧みなストーリーテリングで職人的に紡ぎ続け、フランス映画に欠かせない存在となっていったのである。
1996年にオゾンが発表した15分の短編に『A Summer Dress』という作品がある。ゲイの少年が送る夏の一コマのドラマの中に、むせかえるような肉体の魅力を見事に凝縮し、いまだにオゾンでこの短編が一番好きという人がいるくらいの傑作である。しかし、オゾンが自らのセクシャリティを映画にストレートに反映させたのはこの『A Summer Dress』が唯一かもしれない。オゾンは同性愛をことさらに強調せず、愛そのものが持つ魅力や不思議さや危うさを、多くの長編作品で語ってきているように見える。
英国の小説家エイダン・チェンバースによる小説『俺の墓で踊れ』をオゾンが読んだのは、1985年で17歳の時だったと語っている。大いに感動し、自分で映画作品にしたいと思ったそうだが、当時はまだ学生で映画監督になることは自明でなかった時期であり、いったん脇に置くことにした。やがて功成り名を遂げ、30年が経ち、オゾン作品としては最もヘヴィーな『グレース・オブ・ゴッド 告発の時』(18)を作り終えた後に原作を読み返してみると、変わらぬ輝きがそこにはあり、今こそ映画化にふさわしい時期が来たのかもしれないと悟ったという。それが『Summer of 85』となった。
夏休みの海辺の町、16歳の少年と18歳の少年が出会い、恋に落ち、濃密で幸せな日々を過ごす。しかし、一方は命を落としてしまった。何があったのか。少年の独白で映画は始まる…。
チェンバースの原作自体もそうであったとのことだが、『Summer of 85』は同性愛をポジティブに描き、自由と夢とティーンの熱い愛の気持ちを描いている点で極めて普遍的な作品だ。いや、同性愛をポジティブに描くという言い方すらも語弊があるかもしれない。本作では、同性愛があるがままのものとして描かれる。もはやネガティブやポジティブという概念すら超え、自然に、そこにあるものとして扱われるのだ。それは理想的で、現実はかならずしもそうでないかもしれないけれども、フランス映画におけるセクシャリティという主題の描写はそこまで成熟していると言えないだろうか。
夏の輝き、80’sのきらめき、青春、自由。オゾンは自らの青春にノスタルジックになるほどヤワではなく、相変わらずプロの仕事に徹してブレはないが、個人的な映画であることは間違いないだろう。普遍的な物語に感情を移入しながら、現代フランスを代表する存在のひとりが放つ愛の理想の形を堪能したい。

フランス映画を追うことで多様性のゆくえを体感することができる。今年の夏は特にそれが顕著になった気がしている。文中で触れたカンヌ作品の多くについては、日本公開が現時点で未定だけれども、1本でも多く実現しますようにと期待しよう。それらを待ちながら、まずはオゾンを!
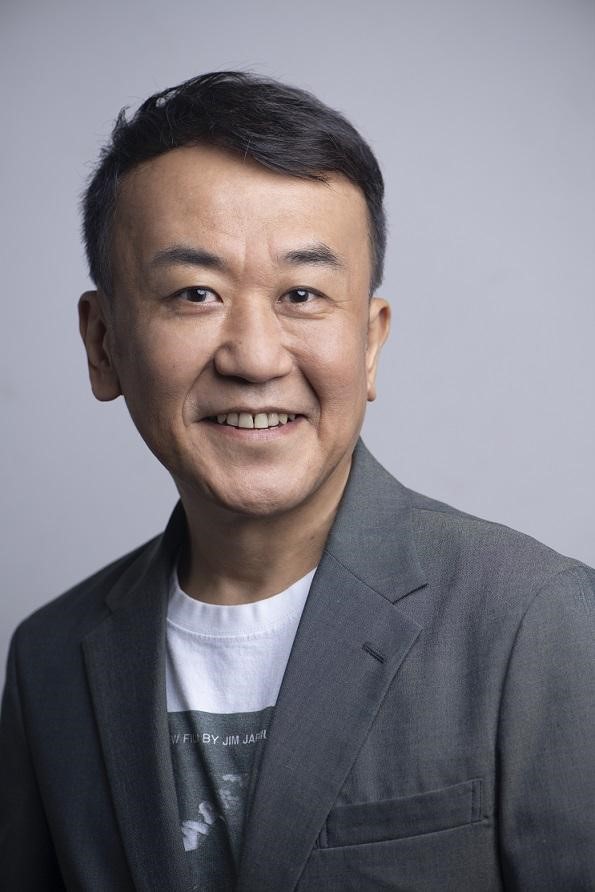
矢田部吉彦
仏・パリ生まれ。2001年より映画の配給と宣伝を手がける一方で、ドキュメンタリー映画のプロデュースや、フランス映画祭の業務に関わる。2002年から東京国際映画祭へスタッフ入りし、2004年から上映作品選定の統括を担当。2007年から19年までコンペティション部門、及び日本映画部門の選定責任者を務める。21年4月よりフリーランス。
寄稿:矢田部吉彦
編集:おのれい
